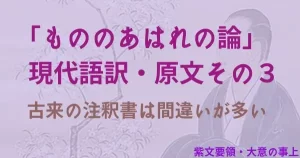この記事では、
本居宣長:もののあはれ論(紫文要領)の
原文・現代語訳を掲載しています。
★大意の事 上
1.物語とは「もののあはれ」を知らせるもの
2.蛍の巻の物語論から紫式部の意図を読み取る
3.古来の注釈書は間違いが多い
4.『源氏物語』の善悪の基準は「もののあはれ」
5.女は「もののあはれ」を知った上でほどよい態度をとるべき
6.「もののあはれ」についての詳述 ←この記事
★大意の事 下
7.恋愛は「もののあはれ」が深い
8.「もののあはれ」と浮気っぽいのとは別物
9.『源氏物語』は教訓の物語ではない
10.光源氏と藤壺の密通を書いた紫式部の意図
11.人の真実の感情を知ることが「もののあはれ」を知ること
もののあはれによって善悪を分かつ
【現代語訳】
また、悪い人というわけではないが、頭中将が、夕霧と雲居の雁の恋愛について、きびしく非難なさったことを、あまりにも、もののあはれを理解しないというふうに書き、夕霧と雲居の雁との関係は、悪いように書いていない。これも、普通の道徳論で言うならば、頭中将の非難は当然のことであって、夕霧と雲居の雁とは(親の許可を得ない恋なので)道に背いた関係である。なのに、そういった普通の道徳論には関知せず、ただもののあはれを基準として善い悪いを区別したのだ。これは善い、これは悪いとは言わないが、その文章の書き方によって、善いとするものと、悪いとするものは、大変はっきりと区別されているのである。
ところが、昔の注釈書は全て、儒教・仏教の道徳的な書物の論述を読んで、自分もそういう論述がしたいと思い、無理やり物語を訓戒の方向にこじつけようとしている。だから、作品中で善い事とされていることも悪い事のように注釈して、これはこれこれの教訓である、これはこれこれの教育である、などと注釈して、読者の心を迷わせて、作者の本来の意図を見失っていることが多い。(本来の意図を見失っている)その原因は、無理に訓戒の方にこじつけて悪を罰することに注目する時は、もののあはれの深い心も興ざめになるものだからである。それでも、見識のしっかりしている人は注釈に惑わされないが、ほとんどの人は注釈を指針にして読むものであり、その注釈のままに理解するので、注釈によって非常に読者の心を戸惑わせるのである。そもそも『源氏物語』を読む時に、けっして訓戒の意味があると思ってはいけない。作者の本来の意図ではない。物語は、そのような道徳的なことではない証拠は、最初に引用した「蛍」の巻で明確になっている。何度も繰り返し言うが、もののあはれを第一として読まねばならない。
【原文】
また悪しき人といふにはあらねど、致仕の大臣のことを、夕霧と雲居の雁とのことにつき強く折檻し給ふことを、あまり心なきさまに書きなし、夕霧と雲居の雁のことは悪しきやうには書かず。これも尋常の論にていはば、大臣の折檻はさることにて、夕霧と雲居の雁とは不義なり。しかるをその論にはかかはらず、ただ物の哀れを主としてよし悪しを分かてり。これはよし、これは悪ししとはいはねど、その文章の書きざまにて、よしとする方と悪ししとする方はいとよく分るるなり。
しかるを古来の注釈はみな、儒仏の道々しき書物の議論を見てそれを羨み、しひて物語をも教戒の方へ落さんとするゆゑに、よくいへる事をも悪しき事のやうに注して、これはしかじかの戒めなり、これはしかじかの教へなり、などと注して、読む者の心を惑はし、作者の本意を失ふこと多し。 そのゆゑは、しひて戒めの方へよせて懲悪のことに見る時は、物の哀れの深きところもさむるものなり。それも眼の明らかならん人は注には迷はねども、大方の人は注を指南にして見るものなれば、その注のままに心得るゆゑに、大きに注にて人を迷はすなり。大方この物語を見むには、決して戒めの心とは見るべからず。作者の本意にあらず。物語はさやうの道々しき事にはあらざる証拠は、最前に引ける螢の巻にて明らかなり。かへすがへすも物の哀れを主として見るべきことなり。
事の心・物の心を知らねばならない
【現代語訳】
だいたい『源氏物語』五十四帖は、「もののあはれを知る」という一言で言い表せる。そのもののあはれの妙味は、これまでに説明してきた通りである。さらに詳しく説明するならば、世の中にありとあらゆる事柄の様々なことを、目で見たり、耳で聞いたり、体でさわったりした時に、その全ての事を心に感じて、その本質を深く理解する。これが事の心を知るということであり、物の心を知ることでもあり、もののあはれを知るということである。
その中でも、さらに細分して説明するならば、(本質を)深く理解することは、物の心・事の心を知ることである。(本質を)深く理解して、その本質の種類に応じて、ふさわしい感情が動くのが、もののあはれである。例えば、たいへん立派な桜が満開に咲いているのを見て、立派な花だと思うのは、物の心(物の本質)を知っていることである。立派な花ということを理解して、「なんとまあ立派な花だなあ」と思うのが、感情が動くことである。これがつまり、もののあはれである。ところが、どれだけ立派な花を見ても、立派な花だと思わないのは、物の心を知らない。そのような人は、ましてや「立派な花だなあ」と感動することはないのである。これが、もののあはれを知らないということだ。
また、他人が肉親などの死に直面して非常に悲しんでいるのを見たり聞いたりして、さぞかし悲しいだろうと推測するのは、悲しいはずであることを知っているからである。これは、事の心(本質)を知っていることである。その悲しいはずの事の本質を知って、さぞかし悲しいだろうと自分の心で推測して感情が動くのが、もののあはれである。その悲しいはずの理由を知った時は、感ずるまいと感情を抑制しても、自然と我慢できない気持ちがあって、嫌でも感情が動いてしまう、これが人情である。もののあはれを知らない人は何とも思わない。その悲しいはずの事の本質を理解しないから、どれだけ他人が悲しんでいるのを見たり聞いたりしても、自分の心にも少しも関係しないので、「さぞかし悲しいだろう」と感じる心がない。
これらは、ただ一つ二つを例にあげたまでだ。この基準に則って全ての事のもののあはれを理解しなければならない。その中に、軽い感動と、重い感動と違いはあるだろうが、この世のありとあらゆる事に、みなそれぞれのもののあはれがあるのだ。その感動する対象の事に、(道徳的な)善い悪いの違いはあるけれど、感じる心は自然と我慢できないところから出てくるものなので、自分の心ではあるが自分の思う通りにならないものであって、道徳的に悪い事でも感動することはあるのだ。これは悪い事だから感動はするまいと思っても、自然と我慢できずに感動するのである。だから、普通の儒教・仏教の教えは、悪い事に感動するのを注意して、悪い方向に感動しないように教えている。和歌・物語は、その事に直面して物事の本質を理解し、感動することを善いこととして、その事自体の(道徳的な)善悪は無視して関知しない。いずれにしても、その感動することを、もののあはれを知ると言って、重要なこととするのである。
【原文】
おほよそこの物語五十四帖は、「物の哀れを知る」といふ一言にて尽きぬべし。その物の哀れといふことの味ひは右にも段々いふごとくなり。なほくはしくいはば、世の中にありとしある事のさまざまを、目に見るにつけ耳に聞くにつけ、身に触るるにつけて、その万の事を心に味へて、その万の事の心をわが心にわきまへ知る、 これ事の心を知るなり、物の心を知るなり、物の哀れを知るなり。
その中にもなほくはしく分けていはば、わきまへ知るところは物の心・事の心を知るといふものなり。わきまへ知りて、その品にしたがひて感ずるところが、物の哀れなり。たとへばいみじくめでたき桜の盛りに咲きたるを見て、めでたき花と見るは、物の心を知るなり。めでたき花といふことをわきまへ知りて、さてさてめでたき
花かなと思ふが、 感ずるなり。 これすなはち物の哀れなり。しかるにいかほどめでたき花を見てもめでたき花と思はぬは、物の心知らぬなり。さやうの人ぞ、ましてめでたき花かなと感ずることはなきなり。これ物の哀れ知らぬなり。
また人の重き憂へにあひていたく悲しむを見聞きて、さこそ悲しからめと推量るは、悲しかるべきことを知るゆゑなり。 これ事の心を知るなり。その悲しかるべき事の心を知りて、さこそ悲しからむとわが心にも推量りて感ずるが、物の哀れなり。その悲しかるべきいはれを知る時は、感ぜじと思ひ消ちても自然と忍びがたき心ありて、いやとも感ぜねばならぬやうになる、これ人情なり。物の哀れ知らぬ人は何とも思はず。その悲しかるべき事の心をわきまへぬゆゑに、いかほど人の悲しむを見ても聞きてもわが心にはすこしもあづからぬゆゑに、さこそと感ずる心なし。
これらはただ一つ二つをあぐるなり。これに準じて万の事の物の哀れといふことを知るべし。その中に軽く感ずると重く感ずるとのけぢめこそあれ、世にあらゆる事にみなそれぞれの物の哀れはあることなり。その感ずるところの事に善悪邪正の変りはあれども、感ずる心は自然と忍びぬところより出づるものなれば、わが心ながらわが心にもまかせぬものにて、悪しく邪なる事にても感ずることあるなり。これは悪しき事なれば感ずまじとは思ひても、自然と忍びぬところより感ずるなり。ゆゑに尋常の儒仏の道は、その悪しき事には感ずるを戒めて、悪しき方に感ぜぬやうに教ふるなり。歌・物語は、その事に当りて物の心・事の心を知りて感ずるをよきこととして、その事の善悪邪正は棄ててかかはらず、とにかくにその感ずるところを物の哀れ知るといひて、いみじきことにはするなり。
もののあはれにも種類がある
【現代語訳】
もののあはれを知ることの妙味は、前述した通りである。けれども、前述したことは概要であり、さらにその中には、さまざまの種類がある。世の中のありとあらゆる事に、みなそれぞれに、もののあはれがあるのだ。だから、「帚木」の巻には「家事という点でもののあはれをよく知っていて」と言っている。であれば、家の中の所帯じみた仕事の中にも、もののあはれはあるのだ。それは、どのような事かというと、まず家族を持って、例えば無駄な出費などがあるような場合に、これは無駄遣いだということを理解しているのは、事の本質を知っているということだ。その無駄遣いを、心の中で「ああ、これは無駄遣いだなあ」と感じるのは、これらの事にもある。要するに、家事という点において事の本質を知り、mもののあはれを知るということだ。無駄遣いがあっても何とも思わず、無秩序に資産を使って減らすのは、「これは無駄遣いだ」ということを心に感じられずに、家事の点でのもののあはれを知らないからである。このことを基準として、(様々な種類のもののあはれを)想像して理解しなければならない。
家事という点でのもののあはれも、さらにさまざまの事があるはずだ。けれども、その家事のもののあはれも、もののあはれの一つであり、理屈(対象の物事に心が動く)は同じであるが、『源氏物語』の本来の意図であるもののあはれは、そのような事ではない。同じもののあはれだけれど、その事と物とによって、風情が変わるからである。だから、あの家事のもののあはれを知っている女を、もののあはれを知らない人だと言ったのだ。同じ理屈のものであっても、その事によってこのように表と裏ほどの違いがあるのは、例えば火の使い方のようだ。同じ火に変わりはないけれども、薪をたいたり、炭火をおこしたりする場合は、寒さを防ぎ、食物を加熱したりなど、たいへん有用である。その火を悪く用いて家についてしまえば、大火事となってしまう。それと同じである。
【原文】
物の哀れ知るといふ味ひ、右のごとし。されど右にいふところはその大綱にして、なほその中にはさまざまの品あるなり。世の中にあらゆる事に、みなそれぞれに物の哀れあるなり。ゆゑに帚木の巻には「後見の方は物の哀れ知り過ぐし」といへり。されば家内の世帯むきの世話する中にも、物の哀れといふことはあるなり。それはいかやうの事ならんといふに、まづ世帯を持ちて、たとへば無益の費えなる事などのあらんに、これは費えぞといふことをわきまへ知るは、事の心を知るなり。その費えなるといふことを、わが心に「ああ、これは費えなる事かな」と感ずるところは、これらの事にもあるなり。これすなはち後見の方につきて事の心を知り、物の哀れを知るなり。無益の費えあれどもそれを何とも思はず、みだりに財宝を費やすは、これ費えぞといふことを心に感ぜぬなれば、後見の方の物の哀れ知らぬなり。この心をもて推して知るべし。
後見の方の物の哀れも、なほさまざまの事あるべし。されどもその後見の方の物の哀れも物の哀れの一端にして、その理りは変らねども、物語の本意とする物の哀れはさやうの事にはあらず。同じ物の哀れなれども、その事と物とによりてその趣き変るゆゑなり。さればかの後見の方の物の哀れ知れるをば、物の哀れ知らぬ人にいへり。同じ義理にして、その事によりてかやうに表裏の相違あることは、たとへば火の用のごとし。 火に変りはなけれども、薪にたき炭におこしては、寒さを防ぎ食物を熟しなど、その益はなはだし。その火を悪くして家屋へ付くれば、また世の大災となるがごとし。
もののあはれの有無は人の心による
【現代語訳】
ところで、四季折々の風景や、何ということもない植物や鳥獣にも、もののあはれを感じることがある。「桐壺」の巻に「虫の声ごえが、涙を誘わせるようだ」、また「風の音や、虫の声を聞くにつけて、何となく一途に悲しく思われなさるが」、「柏木」の巻には、「御前の木立が、何の悩みもなさそうに茂っている様子を御覧になるにつけても、とてもしみじみとした思いがする」(という記述があるが)、これらは、その時々の景物に対してもののあはれを感じている。その時の感情に従って、同じ物でも感じ方が変わるのである。悲しい時は、見るもの聞くこと全てが悲しい。面白い時は、見るもの聞くこと全てが面白い。
その見るもの聞くもの自体は、心を持っていないので、「悲しく見せかけよう、面白く見せかけよう」と、人によって様子が変わるわけではないが、それを見たり聞いたりする人の心で(感じ方が)変わるのである。だから、「帚木」の巻に「無心なはずの空の様子も、ただ見る人によって、美しくも悲しくも見えるのであった」といっているように、もののあはれを知らない人が見ると空の様子も何でもないが、もののあはれを知る人が見たら、悲しい時は悲しく見え、しゃれた気分の時には美しく見えるのだ。また、自分はこんなに物思いに耽っているのに、空の様子は悩み事がないように見えると感じるのも、一種の感じ方である。
「松風」の巻に、「秋のころなので、もの悲しい気持ちが重なったような心地がして(以下略)」、これは季節に心が動いているのだ。「須磨」の巻では、「琴の音が、風に乗って遠くから聞こえて来ると、場所の様子、源氏のご身分の高さ、琴の音の淋しい感じなど、全て思いあわせて、情緒を解する者たちは皆泣いてしまった」といっている。これは、場所の様子に感動し、源氏の身分に感動し、琴の音に感動している。色々な感動するべきことが集まっているから、皆泣いたのである。けれども、「心ある限り(情緒を解する者は)」と言っているのが重要である。このように感動するはずの物を集めても、もののあはれを知らない人は、何とも思わないのだ。心がある人は泣く、ということである。
であれば、もののあはれを知る人が、つまり、心がある人である。もののあはれを知らない人は、心の無い人である(楽器の音は特に人を感動させるものである)。「蓬生」の巻には、次のように書いてある。
特に風流ぶらずとも、自然と急ぐ用事もない時には、気の合う者どうしで手紙の書き交わしなど気軽にし合って、若い人は木や草につけて心をお慰めになるはずなのだが、(以下略)
若い女などが頼るところがなくて、不安で退屈な生活をすると、自然と心の中で鬱々と考え込むことばかりあるものである。そのような時に、もののあはれを知っている人であれば、見たり聞いたりする取るに足らない植物につけても、物思いに耽る心がそれらに感動するものだ。その感動した心をそのまま放置しておいたら、よりいっそう深く考え込んで心におさめておけなくなる。だから、その感じたことを花や紅葉に結び付けて、感じた心を和歌に詠み、手紙に書いて、同じ感性を持つ友人などのもとに送って読ませるのである。そうすれば、その鬱々とした心も晴れて、退屈も慰められるのだ。そして、(友人が)その返事などを書いてよこすと、よりいっそう心が慰められるものである。これは、もののあはれを知る人の有りさまである。
「竹河」の巻では、「もの悲しい時だったせいか、(手紙を)手に取って御覧になる」といっている。蔵人の少将は、亡き髭黒の娘(大君)を一途に恋い慕い、頻繁に手紙を贈ったが、(大君は)ご覧になることはなかった。しかし、この時は(大君は)ちょうどしみじみとした感情に浸っていらっしゃったから、(蔵人の少将からの手紙を)手に取ってご覧になる、ということである。心に感じることがあって、しみじみと思うことがある時は、他のことにも深く感じるものである。今いった「物あはれなる折(もの悲しい時)」というのは、蔵人の少将のことではないけれども、その「物あはれなる」感情ゆえに蔵人の少将に対しても感じる心が自然に湧いてきて、(手紙を)手に取ってご覧になったのである。
【原文】
さてまた四季折々の風景、はかなき木草鳥獣につけて物の哀れを知るといふは、桐壺の巻に、「虫の声々、もよほし顔なる」、また「風の音、虫の音につけても、物のみ悲しくおぼさるるに」、柏木の巻に、「お前の木立ども思ふ事なげなる気色を見給ふも、いと物哀れなり」、これらは折々の景物につけて物の哀れを知るなり。その時の心にしたがうて同じ物も感じやうの変るなり。悲しき時は、見る物聞く物がみな悲しきなり。面白き時は、見る物聞く物がみな面白きなり。
その見る物聞く物は心なければ、悲しく見せん、面白く見せんとて、その人によりて変るにはあらねど、その人の心にて変るなり。されば帚木の巻に、「何心なき空の気色も、ただ見る人から艶にもすごくも見ゆるなりけり」といへるごとく、物の哀れを知らぬ人が見ては空の気色も何ともなけれど、物の哀れ知る人が見れば、悲しき時は悲しく見え、艶なる時は艶に見ゆるなり。またわれはかくばかり物を思ふに、空の気色は思ふ事なげに見ゆるよと感ずるも、一つの感じやうなり。
松風の巻に、「秋のころほひなれば、物の哀れとり重ねたる心地して云々」、これは時節に感ずるなり。 須磨の巻に云はく、「琴の声、風につきてはるかに聞ゆるに、所のさま、人の御ほど、物の音の心細さとり集め、心ある限りみな泣きにけり」といへる、これ、所のさまを感じ、人のほどを感じ、物の音を感じたり。ゆゑにさまざまの 感ずべき事の集まりたるゆゑにみな泣くなり。しかるに「心ある限り」といへるが緊要なり。 かやうに感ずべき物をとり集めても、物の哀れ知らぬ人は何ともなきなり。心あるほどの人は泣く、となり。
されば物の哀れを知る人が、すなはち心ある人なり。物の哀れ知らぬは心なき人なり(物の音はことに人を感ぜしむるものなり)。蓬生の巻に云はく、
わざと好ましからねど、おのづから急ぐことなきほどは、同じ心なる文通はしなどもうちしてこそ、若き人は木草につけても心を慰め給ふべけれ云々、
これ、若き女などのよるべなく心細くつれづれなる住居するは、おのづから心のうちに思ひむすぼほるることのみあるものなれば、さやうの時、物の哀れを知る人なれば、目に触れ耳に触るるはかなき木草につけても、思ふ心がそれに感ずるものなれば、その感じたる心をそのままにさしおけば、いよいよ深くむすぼほれて心にあまるな
なり。それをあるいはその感ずるところの花紅葉につけて、感じたる心のやうを歌によみ文に書きて、同じ心の友だちなどのもとへつかはして見すれば、そのむすぼほるる心も晴れて、つれづれも慰むなり。さてその返事などしておこすれば、いよいよ心は慰むものなり。これ物の哀れを知る人のあるやうなり。
竹河の巻に云はく、「物あはれなる折からにて、取りて見給ふ」といへるは、蔵人の少将、故鬚黒の大臣の姫君に深く心をかけて、たびたび文つかはせども、見給ふことはなきに、この時は折しも物あはれに思し召すことある時節なりしゆゑに、取りて見給ふ、となり。これ、心に感ずることありて、哀れに思ふことのある時は、他の事にも深く感ずるものなり。今いふ「物あはれなる折」といふは蔵人の少将のことにはあらねども、その「物あはれなる」心につきて蔵人の少将のことをも感ずる心がもよほして、取りて見給ふなり。
身分の低い者も、もののあはれを感じる
【現代語訳】
だいたいもののあはれというものは、前にあれこれと言ってきた通りである。さらに『源氏物語』を読んで、その妙味を理解しなければならない。「夕顔」の巻には、「物の情趣を解さない山人も、花の下では、やはり休息したいのではないか」、「紅葉賀」の巻には、「何も分るはずのない下人どもで、木の下、岩の陰、築山の木の葉に埋もれている者までが、少し物の情趣を理解できる者は(感動で)涙を落とすのだった」と記述がある。これらを見なさい。花はきわめて美しいものであるから、何の心もあるはずのない山人でさえ、花の下で休憩しようと思うくらいの心はあるので、もののあはれを少しは理解しているのである。また、「紅葉賀」の引用文は、源氏の君が「青海波」を舞われたのを見て、という意味である。これも、非常に身分の低い者も、少し情緒を理解している物であれば、感動して涙を流すということだ。このことは(「紅葉賀」の引用文の前文で)「空の様子までが感涙を催している」と書かれている。
【原文】
大方物の哀れといふものは、右にかれこれいへるがごとし。なほ物語を見て、その味ひを知るべし。夕顔の巻に云はく、「物の情知らぬ山賤も、花の陰にはなほやすらはまほしきにや」、紅葉賀の巻に云はく、「物見知るまじき下人などの、木の本、岩がくれ、山の木の葉に埋もれたるさへ、すこし物の心知るは、涙おとしけり」。これらを見よ。花はいたりてめでたき物なれば、何の心もあるまじき山賤さへ花の本に休まんと思ふほどの心はあれば、物の哀れをすこしは知るなり。また紅葉賀の詞は、源氏の君の「青海波」を舞ひ給ふを見ての心なり。これも、いたりて賤しき者もすこし物の心知るは、感じて涙をおとす、となり。これをば「空の気色さへ見知り顔なり」と書けり。
もののあはれ知らぬ人は虎狼にも劣る
【現代語訳】
また、「帚木」の巻で、「(源氏は)鬼神さえも手荒なことはできないような(美しい)ご様子なので」、「須磨」の巻で、「虎、狼でさえ、泣くにちがいない」などといっているのを見なさい。あの「蛍」の巻で、「よいように言おうとするあまりに、よいことばかりを選び出して」と言っている通り、よいことを強調して言おうとして、こう書いている。それは何故かというと、身分の低い山人や心のない者も、きわめてよい事には感動し、虎や狼のように獰猛な獣さえ涙を流して泣くに違いないと言うことによって、ましてや心のある人は感動する道理を(読者に)理解させ、それを感じられない人が残念で心が無いということを強調して伝えたいからである。そうであれば、もののあはれを知らない人は、虎や狼にも劣っていると理解しなければならない。
「柏木」の巻では、次のように書いてある。
「やはり、いとしい者と思って下さい」と(源氏が)申し上げなさると、(女三の宮は)「このような出家の身には、物の哀れもわきまえないものと聞いておりましたが、ましてもともと知らないことなので、どのようにお答え申し上げたらよいでしょうか(以下略)」
これは、女三の宮が出家なさった後のことである。源氏の君が、「出家はなさいましたが、やはり私の気持ちを可哀想だとお思い下さい」とおっしゃると、女三の宮の返答として、「このように出家した人は、物の哀れも知らないものだ、と聞いております。まして私はもともと物の哀れを知らない無風流な人間なので、どうお答えしたらよいのでしょうか」ということである。
【原文】
また帚木の巻に、「鬼神も荒だつまじきみけはひなれば」、須磨の巻に云はく、「虎狼だにも泣きぬべし」などといへるを見よ。かの螢の巻に、「よきさまにいふとては、よきことの限りを選り出で」といへるごとく、よき事を強くいはんとてかく書けり。それは何ゆゑぞとなれば、山賤・心なき者もいたりてよき事には感じ、虎狼の
たけき獣さへ涙をおとして泣くべしといひて、ましてや心あらん人は感ずべき理りを知らせ、それを感ぜぬ人の口惜しく心なきことを強くいへり。されば物の哀れ知らぬ人は虎狼にも劣れることを知るべし。
柏木の巻に云はく、
「なほ哀れとおぼせ」と聞え給へば、「かかるさまの人は物の哀れも知らぬものとこそ聞きしを、ましてもとより知らぬことにて云々」、
これは女三の宮の入道し給ひて後のことなり。源氏の君の詞に、「出家はし給ひつれど、なほわが心ざしを哀れとおぼせ」とのたまへば、女三の宮のいらへに、「かやうに入道したる人は物の哀れも知らぬものなり、と聞き侍るなり。ましてわれはもとより物の哀れはしらぬ無骨者なれば、何とかいらへは申すべからん」となり。
僧侶がもののあはれを知らない理由
【現代語訳】
ところで、僧侶がもののあはれを知らないという理由を説明しよう。まず仏道というものは、心が弱く、もののあはれを感じるようでは、修行することができないものだ。であれば、(仏道は)まったくもののあはれを知らない人になって行うものである。第一に、離れづらい父母・兄弟・妻子への愛情を捨てて家を出ること、これは非常に耐えがたい辛さである。それを、心を強くもって離れるのが仏道である。その時に、もののあはれを感じていては、出家はできない。そして、我が身を僧侶の姿に変えて、財産を捨てて、山林にこもり、魚や肉を食べず、音楽も男女間の欲望も断ち切ることは、すべて人間の感情として我慢できないものである。それを我慢して修行するのが仏道なので、もののあはれを感じていては、できないのである。
また、他人を勧誘して仏道に導き、輪廻の苦しみから離脱させようとするにも、この世のもののあはれを知っていては、救済することが難しい。人の心を知らない人になって、強い心で勧めなければ、救うことはできないのだ。だから、「椎本」の巻には、「阿闍梨のあまりに悟り澄ました僧侶らしい心を、憎く辛いとお思いになるのであった」と書いてある。これは、宇治八の宮が亡くなった時の記述だ。阿闍梨は仏道の心を持っていて、(父八の宮に対する娘たちの)執着を離れさせるために親子の愛情を無視して、非情なことを申し上げるのを、姫君たちはもののあはれを感じる心を持っているので、阿闍梨の態度をあまりにも憎く、辛いとお感じになる、ということである。この記述によって、僧侶がもののあはれを知らない理由を理解しなければならない。
【原文】
さて法師の物の哀れ知らぬといふいはれは、まづ仏の道といふものは、心弱く物の哀れを知りては修行することのならぬ道なり。さればいかにも物の哀れを知らぬ人になりて行ふ道なり。まづ第一、離れがたき父母・兄弟・妻子の恩愛をふり棄てて家を出づる、これ大きに人情の忍びがたきところなり。それを心強く離るるが仏道なり。その時物の哀れを知りては出家はならぬなり。さてまたわが身の形をやつし、財宝を棄て、山林にひきこもり、魚肉の味を口に触れず、声色の楽しみを絶ちなどすること、みな人情の忍びがたきところなり。それを忍びて行ふが仏道なれば、物の哀れ知りては行はれぬなり。
さてまた人を勧めて仏の道にみちびき、生死流転を離れしめむとするにも、この世の物の哀れを知りては救ひがたし。ずいぶん哀れ知らぬ者になりて心強く勧めざれば、済度はならぬなり。されば椎本の巻に云はく、「阿闍梨のあまり賢しき聖心を、憎くつらしとなんおぼしける」とあるは、八の宮の隠れ給ふ時のことなり。阿闍梨は仏道の心をもちて、執着を離れしめんために親子の恩愛をかへりみず、つれなき事を申すを、姫君たちは物の哀れを知る心よりして、これをあまり憎くつらしと思し召す、 となり。 これにて法師の物の哀れ知らぬといふいはれを知るべし。
仏教は、もののあはれが深い一面もある
【現代語訳】
けれども、それはもともと仏が、深くもののあはれを理解している御心によって、全ての生物がこの世の愛情を妨げとして、生死流転から離れることができないのを、可哀想だとお思いになってのことだ。だから、(仏道修行者は)一時的にこの世のもののあはれを知らない人間になっても、本当は深くもののあはれを理解しているのだ。儒学も心構えは同じである(愛情・思いやりを重要な徳目とする)。であれば、これらは普通のもののあはれを知らない人と同じようには論じづらい。要するに、儒教・仏教はもののあはれを知らない有様がその道の教えであるが、突き詰めて言えば、それももののあはれを知っているからこそ発生したものなのである。
和歌・物語は、そのような訓戒のための書物ではないから、ただ目の前のもののあはれを感じるものだ。そして、仏様の慈悲や、人格者の仁義の心も、もののあはれであると知っているから、何にせよ一方にかたよることはなく、とにかくもののあはれを知ることを書いている。だから、『源氏物語』の作中には儒教の心構えに触れた箇所も多く、夕霧を大学寮に入れて儒教を学ばせなさったことや、その他にも学問のことが多く見られる。また仏教はもののあはれを捨てることなので、逆にもののあはれがある場合が多い。移り変わりやすい無常の世の中の様子を観察し、真実を悟り、大切な人に先立たれ、不幸に直面して、(人生の)最盛期の身を墨色の衣をまとった僧侶の姿に変えて、世間から離れた山や川により心を清浄に保つなど、出家については、もののあはれが深いことが多い。だから、『源氏物語』では仏道のことに触れた箇所が多く、特にもののあはれを知っていて善い人は、ともするとこの世を嫌って、世間を避ける願望があると書いてあるのだ。これは、この世の頼りないことや、思い通りにならずつらいことを身にしみて知るからである。つまりは、もののあはれを知るということである。
だいたい仏教というものは、儒教よりも教義が厳しくて、人の感情から遠いものである。しかし、逆に儒教よりも人を深く感動させるもので、もののあはれが深いことが多くて、やさしい点があるから、まったく物の本質を知らない山人や召使いの少女まで感動するものだ。だから、『源氏物語』では儒教よりも仏教のことを多く書いている。「蛍」の巻で、「親不孝なのは、仏の道でも厳しく戒めています」といっているのを参考にするとよい。親孝行のことは儒教でさかんに論じられているが、仏教では儒教ほどには言わない。なのに、儒教に触れずに「仏の道」と言っているのは、女に対しておっしゃった言葉なので、とにかく召使いの少女まで心に深く染まったことを言わないではわかってもらえないからである。この言葉によって、仏教が人の心にしみこんでいることを理解しなければならない。「にも(でも)」という助詞に、儒教が含まれているという注釈は、理屈にあわない(「も」は強調である)。考えが浅い。ところで、僧侶は前述した通り、我慢しづらい感情を我慢して修行をするものなので、これもまた感慨深いことである。
【原文】
されどそれはもと仏の、深く物の哀れを知れる御心より、衆生のこの世の恩愛につながれて生死を離るることあたはざるを、哀れと思すよりのことなれば、しばらくこの世の物の哀れは知らぬ者になりても、実は深く物の哀れを知るなり。儒道も心ばへは同じことなり。さればこれらは常の物の哀れ知らぬ人と一口にはいひがたし。されば儒仏は物の哀れ知らぬやうなるがその道にして、畢竟はそれも物の哀れ知るより起れることなり。
歌・物語はさやうの教戒の書にはあらざるゆゑに、ただその眼前の物の哀れを知り、またその仏の慈悲、聖人の仁義の心をも物の哀れと知るゆゑに、とかく一偏にかたよることはなく、とにかくに物の哀れを知ることを書けるなり。ゆゑに巻々に儒道の心ばへをいへる所も多く、夕霧の君を儒道に入れて学問せしめ給ふこと、その外学問の事も多く見え、また仏道は物の哀れを棄つる道にして、かへりて物の哀れのあること多し。 定めなき憂き世の有様を観じ、しかるべき人に後れ、身の歎きに当りて、盛りの形を墨染の衣にやつし、世離れたる山水に心を澄ましなど、その方につきて物の哀れ深き事、また多し。ゆゑに巻々に仏の道の事をいへること多く、ことに物の哀れ知りてよき人は、ややもすればこの世を厭ひて、世を遁るる望みあることを書けり。これ、この世のはかなきこと、心にまかせず憂きことを思ひ知るゆゑなれば、すなはち物の哀れを知るなり。
すべて仏道は儒道よりも教へのきびしくして、人情に遠きものなれども、かへりて儒道よりも人を感ぜしむること深く、物の哀れの深きこと多くて、やはらかなるところあるゆゑに、つやつや物の心も知らぬ山賤・女童まで感ずるものゆゑに、物語には儒道のことよりも仏の道を多くいへり。螢の巻に云はく、「不孝なるは仏の道にもいみじくこそいひたれ」といへるを思ふべし。孝をいふことは儒道にこそいみじくいひたれ、仏の道には儒道ほどにはいはず。しかるを儒道をばいはで仏の道といへるは、女に対してのたまふ詞なれば、とかく女童まで人情に深くそみたる事をいはでは心得ぬゆゑなり。この詞をもて仏道の人情にそみたることを知るべし。「にも」といへるに儒道はこもるといふ注は、いはれぬことなり。浅々しきことなり。さてまた法師は右にいふごとく、忍びがたき情を忍びて道を行ふものなれば、これまたあはれなることなり。
もののあはれ知り顔するのはよくない
【現代語訳】
ところで、もののあはれを知るという妙味は、だいたい前述した通りである。例は他にもたくさんあるけれど、その他はこれに準じて理解できるだろう。そしてまた、もののあはれを知ったような様子をして、それを人に見てもらおう、聞いてもらおうとする人は、たいへん不快である。それは本当のもののあはれではなくて、他人に見せようとするための表面的なごまかし事だからである。外見は似ているが本質は異なるものを強く憎む心境である。「帚木」の巻に、
すべて男も女も、未熟者は、少し知っている方面のことをすっかり見せようと思っているのが、困ったものです。(中略)万事につけて、どうしてそうするのか、そうしなくとも、と思われる折々に、時に応じて、分別できない程度の思慮では、気取ったり風流めかしたりしないほうが無難でしょう。総じて、心の中では知っているようなことでも、知らない顔をして、言いたいことも、一つ二つは言わないでおくのが良いというものでしょう。
といっているようなのは、これに近い。また、(頭中将が)「ただ表面だけの感情で」と言い、(左馬頭が)「それらしい様子を気取ったような表面だけの愛情」などと言っているのは、すべて同じようなことであって、あの木枯らしの女のように浮気っぽい人にその例は多い。「気色だつ(気取る)」といい、「よしばむ(気取る)」といい、「情だつ(風流ぶる)」というような言葉は、すべて誠実な気持ちだけではなく、表面的な飾りである。これらの言葉は、あの「もののあはれを知ったような様子をする」というものである。『源氏物語』の作品中に、もののあはれを知り過ぎることを悪いように書いているのは、このことだ。もののあはれを深く知っていることを、「過ぎる」と言っているのではない。「ほどよく」というのも、ほどほどに知るということではない。「過ぎる」というのは、すべての事に対してもののあはれを知っているような様子を作って、気取ってわけありげに振る舞い、出過ぎたことをいうのである。それは本当にもののあはれを知っているというものではない。必ずもののあはれを知らない人にそんなふうな態度が多いものである。だから、雨夜の品定めでもこれを悪い事としたのである。本当に深くもののあはれを知る人は、絶対にそのような態度はとらない。「薄雲」の巻には、「女御(秋好中宮)は、秋の情趣を知っているようにお答え申し上げたのも、残念で恥ずかしい(略)」と書いてあるが、これは「おっしゃるとおり、(春と秋)どちらも素晴らしいですが、いつとても恋しくない時はない中で、不思議にと聞いた秋の夕べが」とおっしゃったことを指している。善い人は、たったこれだけの事さえ恥ずかしくお思いになるのである。であれば、あの気取って風流ぶる人と、本当にもののあはれを知っている人とは、区別を知らねばならないことである。
質問して言うことには、「もののあはれを知る」という心の持ち方は理解できた。その中に恋愛の事ばかり多いのはどうしてか。(この答えは、次の巻に書いている)
【原文】
さて物の哀れを知るといふ味ひはあらあら右のごとし。 なほ多けれど、余はなぞらへて知るべし。さてまた物の哀れを知り顔つくりて、それを人に見せん聞かせんとする人をば、大きに憎むことなり。それは誠の物の哀れにはあらで、人に知らせんためのうはべのつくろひ事なればなり。似て非なる物を強く憎む心ばへなり。帚木の巻に云はく、
すべて男も女も、わろ者は、わづかに知れる方の事を残りなく見せ尽さむと思へるこそ、いとほしけれ云々。万の事に、などかは、さても、と覚ゆる、折から・時々思ひ分かぬばかりの心にては、よしばみ情だたざらんなん、目やすかるべき。 すべて心に知れらん事をも知らず顔にもてなし、いはまほしからん事をも一つ二つのふしは過ぐすべくなんあべかりける。
といへるたぐひ、これに近し。また「ただうはべばかりの情にて」といひ、「気色ばめらん、見る目の情」などいへるは、みなこのたぐひにして、かの木枯しの女のやうにあだあだしき人にそのたぐひ多し。「気色だつ」といひ、「よしばむ」といひ、「情だつ」といふやうなるは、みな誠の心ばかりにあらず、うはべの飾りなり。 これら はかの「物の哀れを知り顔つくる」といへるものなり。巻々に、物の哀れを知り過ぐるといふことを悪しきやうにいへるは、これなり。 物の哀れを深く知るを、「過ぐる」といふにはあらず。「よきほど」といへるも、大概に知るといふことにあらず。「過ぐる」といふは、万の事に物の哀れを知り顔つくりて、気色ばみよしめきて、さし過ぎたることなり。それはまことに物の哀れ知れるにはあらず。 必ず知らぬ人にさやうなるが多きものなり。ゆゑに品定めにもこれを悪しき事にせり。まことに深く物の哀れ知る人は必ず然らず。薄雲の巻に云はく、「女御は(秋好む中宮)、秋のあはれを知り顔にいらへ聞えてけるも、くやしく恥づかしと云々」、これは「げにいつとなき中に、あやしと聞きし夕こそ」とのたまへることなり。よき人はこれほどの事さへ恥づかしく思し召すなり。さればかのよしばみ情だつと、まことに物の哀れを知るとは、わきまへあることなり。
問ひて云はく、「物の哀れを知る」といふ心ばへは聞えたり。その中に好色の事のみ多きはいかに。(この答への詞は次の巻に見ゆ)
→次のページへ(7.恋愛は「もののあはれ」が深い)
←前のページへ(5.女は「もののあはれ」知った上でほどよい態度をとるべき)