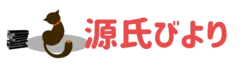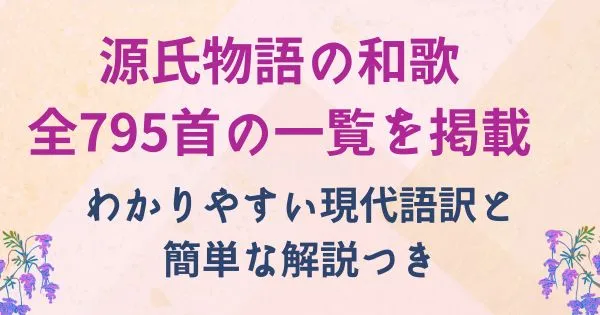この記事では、「源氏物語」の和歌
全795首を一覧で紹介しています。
詠み手と受け手、
現代語訳と簡単な解説もつけていますので、
和歌の学習にお役立てください。
↓下記の巻名↓をクリックしていただくと、
それぞれの巻の和歌一覧にジャンプします。
※()内の数字は和歌の数です。
下記の目次には巻名と
それぞれの巻の和歌一覧を表示しています。
巻名もしくは和歌をクリックしていただくと、
現代語訳にジャンプします。
源氏物語の中で
有名な和歌は、こちらの記事で
ピックアップして紹介しています!


源氏物語の和歌の特徴
「源氏物語」は大長編小説であり、
作中には全795首の和歌が登場します。
和歌の種類は、
- 独詠歌
- 贈答歌
- 唱和歌
の3種類に分類されます。
独詠歌はひとりで詠む和歌、
贈答歌は2人の間でやり取りする和歌、
唱和歌は3人以上の人物が詠み交わす形式です。
理知的で真面目な性格であった
紫式部の作る和歌は、
ほとばしる感情を表した名歌という領域には
達していないようです。
しかし、紫式部は古歌の知識が豊富であり、
古今集の和歌などを踏まえた表現が
多く見られますし、
掛詞や縁語など技巧に富んだ和歌も散見されます。
鎌倉時代になると藤原俊成が
「源氏見ざる歌詠みは遺恨の事なり」
と発言するなど、『源氏物語』は
歌詠み必読の書とされていました。
「源氏物語」の中で最も
和歌が多く詠まれているのは「須磨」の巻です。
光源氏が都から須磨に流浪している間に
詠んだ都の人々との贈答歌や、
感傷にひたった光源氏の独詠歌などが
大きなボリュームを形成しています。
「源氏物語」のあらすじを知りたい方は、
こちらの記事が参考になります!
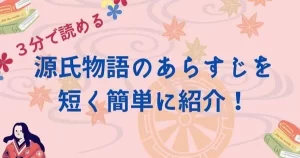
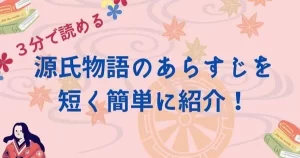
「源氏物語」の主要な登場人物については
こちらの記事で解説しました。
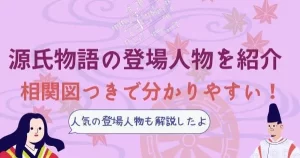
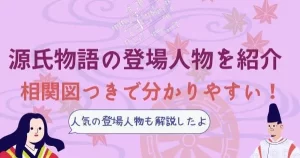
源氏物語和歌一覧(全795首)検索用
桐壺(9首)
限りとて 別るる道の悲しきに いかまほしきは 命なりけり
桐壺の更衣 ⇒ 桐壺帝 (贈歌)
【現代語訳】
寿命は限りがあるものだと、今、別れ道に立ち、悲しい気持ちですが、
私が行きたいと思うのは、生きている世界です。
※桐壺の更衣、臨終間際に詠んだ歌。
宮城野の 露吹きむすぶ 風の音に 小萩がもとを 思ひこそやれ
桐壺帝 ⇒ 桐壺の更衣の母 (贈歌)
【現代語訳】
宮中の萩に、露を結ばせたり散らそうとしたりする風の音を聞くにつけ、
我が子の身の上が思いやられる
※宮城野は歌枕。萩の名所である。
ここでは宮中を指す。
父帝が光源氏を心配する歌。
鈴虫の 声の限りを 尽くしても 長き夜あかず ふる涙かな
靫負命婦 ⇒ 桐壺の更衣の母 (贈歌)
【現代語訳】
鈴虫が声をこれ以上ないくらい鳴き振るわせても、
長い秋の夜をとめどなく流れる涙であることよ
※靫負命婦、弔問の歌。
いとどしく 虫の音しげき 浅茅生に 露置き添ふる 雲の上人
桐壺の更衣の母 ⇒ 靫負命婦 (返歌)
【現代語訳】
虫の音のように泣き暮らしておりました荒れ宿に
よりいっそう涙をもたらします内裏からの使者(靫負命婦)ですこと
荒き風 ふせぎし 蔭の枯れしより 小萩がうへぞ 静心なき
桐壺の更衣の母 ⇒ 桐壺帝 (返歌)
【現代語訳】
荒い風を防いでいた木が枯れてからは
小萩の身の上が心配です
※蔭は桐壺更衣、小萩は、若宮(光源氏)を指す。
「母の更衣が亡くなったから、幼い子が心配だ」の意。
尋ねゆく 幻もがな つてにても 魂のありかを そこと知るべく
桐壺帝 (独詠歌)
【現代語訳】
亡き桐壺の更衣を探しに行く幻術士がいればいいのに。人づてにでも
魂のありかを知ることができるように
※桐壺の更衣の死を悼む歌。
雲の上も 涙にくるる 秋の月 いかですむらむ 浅茅生の宿
桐壺帝 (独詠歌)
【現代語訳】
雲の上の宮中までも涙に曇って見える秋の月だ
ましてや草深い里がどうして澄んでいようか
※「浅茅生の宿」は、若宮(光源氏)がいる里邸を指す。
いときなき 初元結ひに 長き世を 契る心は 結びこめつや
桐壺帝 ⇒ 左大臣 (贈歌)
【現代語訳】
幼子の元服の際に、末永い仲を
あなたの姫との間に結ぶ約束はしましたか
※桐壺帝、左大臣に、光源氏と葵の上の結婚を提案する。
結びつる 心も深き 元結ひに 濃き紫の 色し褪せずは
左大臣 ⇒ 桐壺帝 (返歌)
【現代語訳】
元服の際に、約束した心も深いものになりましょう
濃い紫の色さえ変わらなければ
※「濃き紫」に元服の紐の色と、源氏の愛情をかけている。
「源氏の愛情が変わらなければ、約束した心は
深いものとなりましょう」の意。
帚木(14首)
手を折りて あひ見しことを 数ふれば これひとつやは 君が憂きふし
左馬頭 ⇒ 女<恋人>(贈歌)
【現代語訳】
あなたと結婚していた日々を指折り数えてみると
この一つだけがあなたの嫌なところなものでしょうか
※「やは」は反語で、「この一つではない」という意味。
憂きふしを 心ひとつに 数へきて こや君が手を 別るべきをり
女<恋人> ⇒ 左馬頭 (返歌)
【現代語訳】
あなたの辛い態度を心の中で我慢してきましたが
今は別れる時なのでしょうか
※相手の詠んだ歌の語句を引用しているのは、
女に未練がある証である。
琴の音も 月もえならぬ 宿ながら つれなき人を ひきやとめける
男<殿上人> ⇒ 女<恋人> (贈歌)
【現代語訳】
琴の音色も月も美しいお宅ですが
薄情な人を引き止められなかったのですね
木枯に 吹きあはすめる 笛の音を ひきとどむべき 言の葉ぞなき
女<恋人> ⇒ 男<殿上人> (返歌)
【現代語訳】
冷たい木枯らしに合うあなたの笛の音を
引きとどめる言葉を私は持ち合わせていません
※「私はあなたを引き止めようとはしません」の意
山がつの 垣ほ荒るとも 折々に あはれはかけよ 撫子の露
夕顔 ⇒ 頭中将 (贈歌)
【現代語訳】
山荘の垣根は荒れていても時々は
愛情をかけてやってください撫子の花を
※「撫子」は幼い子どもを指す。
「時々は私の子どもに会いにきてください」の意。
咲きまじる 色はいづれと 分かねども なほ常夏に しくものぞなき
頭中将 ⇒ 夕顔 (返歌)
【現代語訳】
庭に咲いている様々な花はいずれも美しいが
やはり常夏の花の美しさにかなうものはいない
※「常夏」は「撫子」の異名。
「常夏」の「とこ」は「床」(男女の寝所)
を連想させる。
子どもを指す「撫子」から、
母親の夕顔を指す「常夏」にすり替えている。
「子どもよりもあなた(夕顔)が一番です」と
夕顔のご機嫌をとっている。
うち払ふ 袖も露けき 常夏に あらし吹きそふ 秋も来にけり
夕顔 ⇒ 頭中将 (返歌)
【現代語訳】
床の塵を払う袖も涙に濡れている常夏に
激しい風の吹きつける秋が来ました
※「あらし」は頭中将の北の方からの
脅迫を指す。「秋」には「飽き」がかかっており、
「愛が冷めたのですね」という恨みを含む。
ささがにの ふるまひしるき 夕暮れに ひるま過ぐせと いふがあやなさ
式部丞 ⇒ 女<恋人>(贈歌)
【現代語訳】
蜘蛛が活発に動いて私が来ることがわかっている夕暮に
蒜が臭っている昼間が過ぎるまでまで待てと言うのは意味がわからない
※蜘蛛がよく動くのは男が訪問する前兆という俗信があった。
「蒜(にんにく)」と「昼」をかけている。
逢ふことの 夜をし隔てぬ 仲ならば ひる間も何か まばゆからまし
女<恋人> ⇒ 式部丞 (返歌)
【現代語訳】
一夜も間を空けずに逢っている夫婦仲ならば
蒜(にんにく)が臭っている昼間逢ったとしても恥ずかしいことがありましょうか
※男が長く通わなかったのを恨む歌
つれなきを 恨みも果てぬ しののめに とりあへぬまで おどろかすらむ
光源氏 ⇒ 空蝉 (贈歌)
【現代語訳】
あなたの冷たい態度に恨み言を全て言わないうちに夜も明けようとして
鶏までが取るものも取りあえぬまで騒がしく鳴いて私を起こそうとするのでしょうか
※「取りあえぬ」に「鶏」をかけている。
身の憂さを 嘆くにあかで 明くる夜は とり重ねてぞ 音もなかれける
空蝉 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
わが身の辛さを嘆いても嘆き足りないうちに
明ける夜は鶏の鳴く声に取り重ねて
私も涙があふれてきます
※「取り重ね」に「鶏」をかけている。
見し夢を 逢ふ夜ありやと 嘆くまに 目さへあはでぞ ころも経にける
光源氏 ⇒ 空蝉 (贈歌)
【現代語訳】
夢のようだったあの夜以来、再び逢える夜があるだろうか嘆いているうちに
眠れない夜を幾日も送っていました
※「逢う」には「夢が合う」(正夢になる)
をかけている。
「目が合わない」(眠れない)と
「あなたに逢わない」をかけている。
帚木の 心を知らで 園原の 道にあやなく 惑ひぬるかな
光源氏 ⇒ 空蝉 (贈歌)
【現代語訳】
近づけば消えるという帚木のような
あなたの心も知らず
園原への道に空しく迷ってしまいました
※帚木とは信濃の園原に生えていた伝説上の木。
遠くからだと見えるのに近づいたら消える。
空蝉を帚木に喩えている。
数ならぬ 伏屋に生ふる 名の憂さに あるにもあらず 消ゆる帚木
空蝉 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
数にも入らない身分として生きる私は情けないので
存在しても触れられない帚木のようにあなたの前から姿を消します
※帚木は、信濃の園原の伏屋という場所に生えていたので
空蝉は「伏屋」という語句を使っている。
空蝉の教養の高さがうかがえる。
空蝉(2首)
空蝉の 身をかへてける 木のもとに なほ人がらの なつかしきかな
光源氏 ⇒ 空蝉 (贈歌)
【現代語訳】
蝉が抜け殻となるように、衣を脱いで逃げていったあなたですが
やはり人柄が恋しく感じられます
※「人がら」に蝉の「殻」をかけている。
空蝉の 羽に置く露の 木隠れて 忍び忍びに 濡るる袖かな
空蝉 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
蝉の抜け殻の羽に置く露が
木に隠れて見えないように
私もひっそりと涙で袖を濡らしております
※「伊勢集」にあるとされている和歌
夕顔(19首)
心あてに それかとぞ見る 白露の 光そへたる 夕顔の花
夕顔 ⇒ 光源氏<もしくは頭中将>(贈歌)
【現代語訳】
当て推量にあなたではないかと思います
白露の光を添えて美しい夕顔の花は
※「光りそへたる」は光源氏を暗示する。
花は女性の暗喩であることから、
「夕顔の花」で夕顔自身が名乗っていると見る説もある。
相手が元恋人の頭中将だと
勘違いして詠んだ歌という解釈もある。
寄りてこそ それかとも見め たそかれに ほのぼの見つる 花の夕顔
光源氏 ⇒ 夕顔 (返歌)
【現代語訳】
もっと近寄って
誰なのかはっきり見てはいかがでしょう
黄昏時にぼんやりと見えた花の夕顔を
咲く花に 移るてふ名は つつめども 折らで過ぎ憂き 今朝の朝顔
光源氏 ⇒ 中将の君<六条御息所の女房>(贈歌)
【現代語訳】
咲いている花に心を移したという
噂には気がねしますが
手折らずに素通りできないくらい
美しい今朝の朝顔の花です
※主人の六条御息所から女房の中将の君に
「心を移す」のは遠慮される。
「咲く花」「朝顔」は中将の君のこと。
社交辞令的な恋の歌。
朝霧の 晴れ間も待たぬ 気色にて 花に心を 止めぬとぞ見る
中将の君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
朝霧が晴れるまで待たずに
お帰りになるご様子なので
朝顔の花(六条御息所)に心を止めていないと
思われます
※源氏が詠んだ和歌の「咲く花」「朝顔」を
自分ではなく主人・六条御息所のことにすり替えている。
優婆塞が 行ふ道を しるべにて 来む世も深き 契り違ふな
光源氏 ⇒ 夕顔 (贈歌)
【現代語訳】
優婆塞が勤行しているのを道しるべにして
来世の深い約束に背かないで下さい
※優婆塞は在俗のまま仏道の修行をする人。
源氏が夕顔に深い愛を誓った歌。
前の世の 契り知らるる 身の憂さに 行く末かねて 頼みがたさよ
夕顔 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
前世の宿縁の薄さがこの身に悲しく感じられるので
来世までは信頼できません
いにしへも かくやは人の 惑ひけむ 我がまだ知らぬ しののめの道
光源氏 ⇒ 夕顔 (贈歌)
【現代語訳】
昔の人もこのように恋の道に迷いこんだだろうか
私が今まで経験したことのない明け方の道だ
山の端の 心も知らで 行く月は うはの空にて 影や絶えなむ
夕顔 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
山の端の心も知らないで付き従っていく月は
光が消えてしまうのではないでしょうか
※「山の端の心」は光源氏、
「月」は夕顔を暗示している。
光源氏に従っていく私はどうなってしまうのか
不安に思う気持ちを詠んでいる。
夕露に 紐とく花は 玉鉾の たよりに見えし 縁にこそありけれ
光源氏 ⇒ 夕顔 (贈歌)
【現代語訳】
夕方の露を待って花開いて顔をあなたに見せるのは
五条大路の道で出逢った縁からなのですよ
※「紐とく」は男女の契りを交わす意とも、
顔を見せる意とも捉えられる。
「玉鉾の」は「道」の枕詞だが、ここでは
「道」の意味で使われている。
光ありと 見し夕顔の うは露は たそかれ時の そら目なりけり
夕顔 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
光り輝いていると思った夕顔の上露は
夕暮れ時の見間違いでした
※「夕顔のうは露」は光源氏の顔のこと。
源氏を美しいと思ったけれど、
黄昏の見間違いであり、
さほど美しくないですねと冗談を言っている。
見し人の 煙を雲と 眺むれば 夕べの空も むつましきかな
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
愛した人の火葬の煙が雲となってなびいているのを眺めると
この夕方の空も親しく感じられることよ
※夕顔の死を悼む歌。
問はぬをも などかと問はで ほどふるに いかばかりかは 思ひ乱るる
空蝉 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
お見舞いもしないことを、何故かとお尋ね下さらずに月日が経ち、
私もたいへん思い乱れています
※夕顔の死のショックで病気になった光源氏を
案ずる和歌。
空蝉の 世は憂きものと 知りにしを また言の葉に かかる命よ
光源氏 ⇒ 空蝉 (返歌)
【現代語訳】
あなたとの関係はつらいものと知ってしまったのに
あなたの言葉に望みをかけて、この命を生きていこうと思います
ほのかにも 軒端の荻を 結ばずは 露のかことを 何にかけまし
光源氏 ⇒ 軒端の荻 (贈歌)
【現代語訳】
一夜の関係であろうと、軒端の荻を結ぶ逢瀬を遂げなかったら
少しの恨み言を言う理由もなかったでしょう
※「軒端の荻を結ぶ」は男女の契りを暗喩している。
ほのめかす 風につけても 下荻の 半ばは霜に むすぼほれつつ
軒端の荻 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
ほのめかされる手紙を見るにつけても、下荻のような
身分の低い私は、嬉しい反面、思い悩んでいます
泣く泣くも 今日は我が結ふ 下紐を いづれの世にか とけて見るべき
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
泣きながら今日は私が結ぶ袴の下紐を
いつの世にかまた夕顔と再会して心打ち解けて下紐を解いて契ることができるだろうか
※「とけて」には「下紐をとく」(男女の契りをかわす)
と「心を打ちとける」の2つの意味がかかっている。
夕顔の死を悼む歌。
逢ふまでの 形見ばかりと 見しほどに ひたすら袖の 朽ちにけるかな
光源氏 ⇒ 空蝉(贈歌)
【現代語訳】
再会する日までの形見の品と思っていましたが
すっかり袖が涙で朽ちるまでになってしまいました
※地方に下る空蝉に対して
形見の小袿を返却した際の和歌。
蝉の羽も たちかへてける 夏衣 かへすを見ても ねは泣かれけり
空蝉 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
蝉の羽の衣替えが終わった後の夏衣は
返却してもらっても涙があふれてくるばかりです
過ぎにしも 今日別るるも 二道に 行く方知らぬ 秋の暮かな
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
亡くなった人も今日別れて去っていく人もそれぞれの道へ
どこへ行くのか知れない秋の暮れであることよ
※「過ぎにしも」は亡くなった夕顔、
「今日別るるも」は伊予国に下る空蝉を指す。
若紫(25首)
生ひ立たむ ありかも知らぬ 若草を おくらす露ぞ 消えむそらなき
尼君 ⇒ 女房 (贈歌)
【現代語訳】
今後どこでどう育って行くのかも分からない若草のような少女を
残して消えてゆく露のように儚い私は死ぬに死ねないのです
※若草は少女、露は尼君を指す。
露には短い寿命というイメージがある。
初草の 生ひ行く末も 知らぬまに いかでか露の 消えむとすらむ
女房 ⇒ 尼君 (返歌)
【現代語訳】
初草のように幼い姫君のご成長も見ないうちに
どうして尼君様は先立たれることをお考えになるのでしょう
初草の 若葉の上を 見つるより 旅寝の袖も 露ぞ乾かぬ
光源氏 ⇒ 尼君 (贈歌)
【現代語訳】
初草のようにうら若い少女を見てからは
私の旅寝の袖は恋の涙で濡れてまったく乾きません
※「初草の若葉」は若紫(のちの紫の上)を指す。
枕結ふ 今宵ばかりの 露けさを 深山の苔に 比べざらなむ
尼君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
今夜だけの旅の宿の寂しさで涙に濡れているからといて
深山の苔のような私たちのわびしさと比べないで下さい
吹きまよふ 深山おろしに 夢さめて 涙もよほす 滝の音かな
光源氏 ⇒ 僧都 (贈歌)
【現代語訳】
山おろしの風に乗って聞こえてくる懺法の声に煩悩から覚めて
涙を催させる滝の音であることよ
※明け方の僧都の懺法の声を聞いて、
若紫への執着が浄化される気持ちを詠んだ歌。
さしぐみに 袖ぬらしける 山水に 澄める心は 騒ぎやはする
僧都 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
不意に訪問されてお袖を濡らされたという山の水に
心を澄まして住んでいるわたしは驚きません
※「さしぐみ」は「突然」の意と
涙が「さし汲み」をかけている。
「すめる」は「澄める」と「住める」をかけている。
宮人に 行きて語らむ 山桜 風よりさきに 来ても見るべく
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
宮中の人たちに帰って話しましょう。山桜の美しさを
風で散ってしまう前に来て見るようにと
優曇華の 花待ち得たる 心地して 深山桜に 目こそ移らね
僧都(唱和歌)
【現代語訳】
三千年に一度咲くという優曇華の花が咲く瞬間に
立ち会ったような気がして深山桜には目も移りません
※源氏は山桜ではなくて優曇華の花のように
美しいですという挨拶の和歌。
奥山の 松のとぼそを まれに開けて まだ見ぬ花の 顔を見るかな
聖(唱和歌)
【現代語訳】
奥山の松の扉を珍しく開けると
まだ見たことのない花のように美しいお顔を拝見しました
※源氏の美しさを賛美する挨拶の和歌。
夕まぐれ ほのかに花の 色を見て 今朝は霞の 立ちぞわづらふ
光源氏 ⇒ 尼君 (贈歌)
【現代語訳】
昨日の夕暮にわずかに美しい花を見ましたので
今朝は霞の空に立ち去りたくない気分です
※「花の色」は若紫の比喩。
まことにや 花のあたりは 立ち憂きと 霞むる空の 気色をも見む
尼君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
本当に花のそばを立ち去りにくいのでしょうか
そのようにおっしゃる真意を確かめたいものです
※「霞むる」には「掠むる」がかけられており
源氏が若紫を奪おうとする真意を確認したい
という意味がこめられている。
面影は 身をも離れず 山桜 心の限り とめて来しかど
光源氏 ⇒ 若紫 (贈歌)
【現代語訳】
山桜のように美しいあなたの面影が私の身から離れません
心のすべてをそちらに留め置いて来たのです
※光源氏から若紫にあてた恋の和歌。
嵐吹く 尾の上の桜 散らぬ間を 心とめける ほどのはかなさ
尼君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
嵐が吹いて散ってしまう峰の桜に
その花が散る前にお心を寄せられたように頼りなく感じられます
※幼い若紫の代わりに祖母の尼君が詠んだ返歌。
一時的な恋ではないかと疑っている。
あさか山 浅くも人を 思はぬに など山の井の かけ離るらむ
光源氏 ⇒ 尼君 (贈歌)
【現代語訳】
浅香山のように浅い気持ちで思っているわけではないのに
なぜ私から影が離れていらっしゃるのでしょうか
※「かけ離る」は「影離る」とかけている。
汲み初めて くやしと聞きし 山の井の 浅きながらや 影を見るべき
尼君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
薄情な人と契りを結んで後悔したと聞きました山の井のような
浅いお心のまま孫を見せられましょうか
※古今六帖の「くやしくぞ汲みそめてける浅ければ袖のみ濡るる山の井の水(悔しいなあ、汲み始めた後で、あなたの気持ちが浅いのを知り、体は濡れず、袖のみ涙で濡らす夜になるとは、水量の少ない山の井のように)」を下にひいた歌。
見てもまた 逢ふ夜まれなる 夢のうちに やがて紛るる 我が身ともがな
光源氏 ⇒ 藤壺 (贈歌)
【現代語訳】
お逢いしても、また再び逢うことの難しい夢のようなこの世なので
夢の中にそのまま紛れて消えてしまいたい我が身です
※光源氏と藤壺、逢瀬後の恋の和歌
世語りに 人や伝へむ たぐひなく 憂き身を覚めぬ 夢になしても
藤壺 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
世の中の語り草として人が伝えるのではないでしょうか、
この上ないくらい辛い身を、覚めることのない夢の中のこととしても
いはけなき 鶴の一声 聞きしより 葦間になづむ 舟ぞえならぬ
光源氏 ⇒ 若紫 (贈歌)
【現代語訳】
おさない鶴の一声を聞いてから
葦の間を行き悩む舟は何とも言えない思いをしています
※「鶴の一声」は若紫の声、
「舟」は源氏を指す。
手に摘みて いつしかも見む 紫の 根にかよひける 野辺の若草
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
手で摘んで早く見たいなあ
紫草に縁のある野辺の若草を
※「紫」は「紫草」のことで藤壺の宮を指す。
「根にかよふ」は若紫が藤壺の姪であることを言う。
「若草」は若紫を指す。
あしわかの 浦にみるめは かたくとも こは立ちながら かへる波かは
光源氏 ⇒ 少納言 (贈歌)
【現代語訳】
姫君に会うことは難しいだろうが
和歌の浦の波のようにこのまま帰ることはできません
※「わか」は「葦若」と「和歌の浦」をかけている。
若紫を指す。
「見る目」と「海松布」をかけている。
「波」は源氏自身を指している。
寄る波の 心も知らで わかの浦に 玉藻なびかむ ほどぞ浮きたる
少納言 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
和歌の浦に寄る波に浮かびなびく玉藻のように
相手の心をよく知りもせずに従うことは不安なことです
※「寄る波」は源氏、
「玉藻」は若紫を指す。
朝ぼらけ 霧立つ空の まよひにも 行き過ぎがたき 妹が門かな
光源氏 ⇒ 忍びて通ひたまふ所<女>(贈歌)
【現代語訳】
朝霧が立ちこめた空を見るにつけても
素通りしがたい貴女の家の門であることよ
※「あなたの家の前は素通りしがたいから、
ちょっと寄らせてください」という意味。
立ちとまり 霧のまがきの 過ぎうくは 草のとざしに さはりしもせじ
忍びて通ひたまふ所<女>⇒光源氏 (返歌)
【現代語訳】
霧の立ちこめた門の前を通り過ぎがたいと言うならば
草が生い茂り門を閉ざしたことぐらい何の障害でもないでしょう
※「草が門に生い茂っていようとも、
家に入りたいなら入ればいいではないか。
入る気もないくせに」という恨みの歌。
ねは見ねど あはれとぞ思ふ 武蔵野の 露分けわぶる 草のゆかりを
光源氏 ⇒ 若紫 (贈歌)
【現代語訳】
まだ一緒に寝てはいませんが愛しく思います
武蔵野の露に苦労する紫に縁のあるあなたを
※「露分けわぶる草」は藤壺の宮を意識している。
かこつべき ゆゑを知らねば おぼつかな いかなる草の ゆかりなるらむ
若紫 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
恨み言をいわれる理由が分かりません
私はどのような方の縁者なのでしょう
※若紫は、藤壺と光源氏の不倫関係を知らない。
「ゆかり」と言われて、誰のゆかりなのか
疑問に思っている。
末摘花(14首)
もろともに 大内山は 出でつれど 入る方見せぬ いさよひの月
頭中将 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
一緒に内裏を出ましたのに
行方を誤魔化してしまわれる十六夜の月ですね
※「大内山」は内裏を指す。
「月」を光源氏に喩えている。
里わかぬ かげをば見れど ゆく月の いるさの山を 誰れか尋ぬる
光源氏 ⇒ 頭中将 (返歌)
【現代語訳】
どの里もひとしく照らす月を空に見ても
その月が沈む山まで尋ねる人はいませんよ
※自分(源氏)を月に、女を山に喩えている。
「里わかぬかげ」はどの女にも等しく愛情を
かける源氏の好色さを言う。
いくそたび 君がしじまに まけぬらむ ものな言ひそと 言はぬ頼みに
光源氏 ⇒ 末摘花 (贈歌)
【現代語訳】
何度あなたの沈黙に負けたことでしょう
何も言うなとおっしゃらないことを頼みにして
※無口な性格の末摘花に対して
光源氏が詠んだ和歌。
鐘つきて とぢめむことは さすがにて 答へまうきぞ かつはあやなき
侍従 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
鐘をついて法華八講の論議を終わるように
何も言うなとはさすがに言えません、わけがわからなくて
※末摘花が返歌できないので、
侍従が代作した歌。
源氏の和歌「しじま(沈黙)」は
法華八講の論議の際に鐘を合図にして沈黙
することを「しじま」というのが語源。
その連想から、「鐘つきて」と詠んだ。
言はぬをも 言ふにまさると 知りながら おしこめたるは 苦しかりけり
光源氏 ⇒ 末摘花 (贈歌)
【現代語訳】
何も言わないのは言う以上に深い思いだと知っていますが、
ずっと黙っているのは悲しいものです
※古今六条の
「心には下行く水の湧き返り言はで思ふぞ言ふにまされる」
(私の心では、地下水がわき返っているように、口には出さないけれど、あなたを思っています。その思いは口に出して言うより優っています)
を引歌としている。
夕霧の 晴るるけしきも まだ見ぬに いぶせさそふる 宵の雨かな
光源氏 ⇒ 末摘花 (贈歌)
【現代語訳】
夕霧が晴れる気配をまだ見ないうちに
うっとうしさを添える夜の雨が降ることよ
※末摘花との逢瀬の翌日に贈った歌。
「夕霧の晴るるけしき」は末摘花の心を喩える。
宵の雨が降っているから今夜はそちらへ行けないと言い訳している。
晴れぬ夜の 月待つ里を 思ひやれ 同じ心に 眺めせずとも
末摘花(侍従)⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
雲の晴れない夜の月を待っている私を思いやってください
あなたが私と同じ気持ちで眺めているのでなくとも
※侍従が考えて、末摘花が書いた和歌。
「月」は源氏を、「里」は末摘花を指す。
「ながめ」は「眺め」と「長雨」をかけている。
朝日さす 軒の垂氷は 解けながら などかつららの 結ぼほるらむ
光源氏 ⇒ 末摘花 (贈歌)
【現代語訳】
朝日がさしている軒のつららは解けたのにに
どうしてあなたの心の氷は固まったままなのでしょう
※初めて源氏が末摘花の容貌を見た
冬の朝に詠んだ和歌。
「垂氷(つらら)」が解ける=心が解ける
にかけている。
降りにける 頭の雪を 見る人も 劣らず濡らす 朝の袖かな
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
白髪頭の老人の頭に積もった雪を見ると
その人に劣らず、涙で袖を濡らす朝だなあ
※末摘花邸の門の鍵を管理する番人が
白髪頭の老人であった。
その老人を見て源氏が詠んだ独詠歌。
唐衣 君が心の つらければ 袂はかくぞ そぼちつつのみ
末摘花 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
あなたの冷たい心がつらいので
私の袖の袂は涙でこんなに濡れるばかりです
※末摘花が衣装箱と一緒に贈った和歌。
「唐衣」は「着」にかかる枕詞。
なつかしき 色ともなしに 何にこの すゑつむ花を 袖に触れけむ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
親しみを感じる花でもないのに
どうしてこの末摘花と結ばれてしまったのだろう
※「すゑつむ花」は紅花のこと。
「花」に「鼻」をかけている。
末摘花は、鼻の赤い姫君である。
紅の ひと花衣 うすくとも ひたすら朽す 名をし立てずは
大輔の命婦(唱和歌)
【現代語訳】
紅色に一度染めた衣は色が薄くても
悪い評判をどうか立てないで下さい
※源氏に末摘花を紹介した命婦の和歌。
親戚である末摘花を擁護している。
逢はぬ夜を へだつるなかの 衣手に 重ねていとど 見もし見よとや
光源氏 ⇒ 末摘花 (返歌)
【現代語訳】
逢わない夜が多いのに間を隔てる衣とは
さらに逢わない夜を重ねて見なさいということですか
紅の 花ぞあやなく うとまるる 梅の立ち枝は なつかしけれど
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
紅の花は理由もなく嫌に感じる
梅の立ち枝に咲いた花には親近感をかんじるが
※「紅の花」は末摘花の赤い鼻を指す。
「梅の立ち枝」は末摘花の長い鼻を想像させる。
末摘花のことは嫌いではないが、
末摘花の赤い鼻は嫌だという意味。
紅葉賀(17首)
もの思ふに 立ち舞ふべくも あらぬ身の 袖うち振りし 心知りきや
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
つらい気持ちのまま立派に舞うことなどはできそうもない私が
袖を振って舞った気持ちを分かっていただけましたか
※「立ち舞ふ」は「青海波を舞う」意と
「立派に立ち振る舞う」意がかけられている。
「袖うち振り」は袖を振って踊る意と
袖を振って相手の魂を招くという古代信仰
に基づく愛情表現をかけている。
唐人の 袖振ることは 遠けれど 立ち居につけて あはれとは見き
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
中国の人が袖を振って舞ったことは昔のことですが
あなたの舞はしみじみと拝見いたしました
※源氏が舞った青海波は、唐の舞なので
「唐人の」と詠んだ。
いかさまに 昔結べる 契りにて この世にかかる なかの隔てぞ
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
どのような前世の因縁によって
この世にこのような、二人の仲に隔てがあるのだろうか
※「この世」に「子の世」をかけており、
藤壺とも我が子とも会えないつらさを詠んでいる。
見ても思ふ 見ぬはたいかに 嘆くらむ こや世の人の まどふてふ闇
王命婦 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
子を見ている方も物思をしています。見ていないあなたはまたどんなに悲しんでいることでしょう。
これが世の人が言う親の心の闇でしょうか
※「(子を)見ても思ふ」の主語は藤壺、
「(子を)見ぬ」のは光源氏。
藤壺も光源氏も親心の闇で苦しんでいる。
藤壺の代わりに返歌した。
よそへつつ 見るに心は なぐさまで 露けさまさる 撫子の花
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
思いをよそえて見ても気持ちは慰められず
涙を催させる撫子の花だなあ
※「よそへつつ見る」は
「桐壺帝の子として見ている」の意。
実は自分の子なので、涙が出てくる。
袖濡るる 露のゆかりと 思ふにも なほ疎まれぬ 大和撫子
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
袖を濡らしている方(源氏)の子と思うにつけても
やはり疎ましく感じられる大和撫子です
(疎ましいとは思えない大和撫子です)
※「疎まれぬ」の「ぬ」を
完了の助動詞ととるか
打消の助動詞ととるかで意味が変わる。
藤壺の複雑な心境として
両方の意味を含ませているか。
「大和撫子」は若宮のこと。
君し来ば 手なれの駒に 刈り飼はむ 盛り過ぎたる 下葉なりとも
源典侍 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
あなたがいらっしゃったなら人馴れした馬にわらを刈って与えましょう
盛りの過ぎた下草であっても
※「君」は源氏を指し、「下葉」は源典侍自身を指す。
「私は源氏を女として歓迎します」と
色気たっぷりに誘っている。
下葉を駒に食べさせようというこの表現は、
性愛の露骨な表現を思わせる。
次の先行歌を引歌としている。
「わが門の ひとむら薄 刈り飼はん 君が手なれの 駒も来ぬかな」
(『後撰集』恋二・六十六 小町が姉)
笹分けば 人やとがめむ いつとなく 駒なつくめる 森の木隠れ
光源氏 ⇒ 源典侍 (返歌)
【現代語訳】
笹を分けて入ったら人が注意するでしょう
いつでも馬を懐かせている森の木蔭だから
※「駒」は他の男、「森の木」は源典侍を指す。
「私が誘いに乗ったら、あなたの恋人が邪魔するでしょう」
という意味の歌。
次の先行歌を引歌としている。
「笹分けば 荒れこそ増さめ 草枯れの 駒なつくべき 森の下かは」
(蜻蛉日記)
立ち濡るる 人しもあらじ 東屋に うたてもかかる 雨そそきかな
源典侍 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
訪れて濡れる人が誰もいない東屋に
嫌な雨が落ちて来ることよ
※誰も来てくれないことを嘆く和歌。
催馬楽「東屋」の歌詞を踏まえている。
性的な意味を含む「東屋」を
引用することで源氏を不快にさせている。
人妻は あなわづらはし 東屋の 真屋のあまりも 馴れじとぞ思ふ
光源氏 ⇒ 源典侍(返歌)
【現代語訳】
人妻は、ああ面倒くさい
あまり親密にならないようにしようと思います
※「他に男のいる源典侍は面倒なので
親しくなる気はありません」の意。
つつむめる 名や漏り出でむ 引きかはし かくほころぶる 中の衣に
頭中将 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
隠している浮名も世間にばれてしまうでしょう
引っ張り合って破れてしまった二人の衣の中から
※「中」は「衣と衣の中間」という意味と
源氏と源典侍の「仲」という意味をかけている。
隠れなき ものと知る知る 夏衣 着たるを薄き 心とぞ見る
光源氏 ⇒ 頭中将 (返歌)
【現代語訳】
この女との仲は、薄い夏衣では隠せない分かった上で
やってくるとは、薄情なお心ですね
恨みても いふかひぞなき たちかさね 引きてかへりし 波のなごりに
源典侍 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
恨んでも何の意味もありません
立て続けに訪れて帰っていったお二人の波の後には
※二人の若者が源典侍を置き去りにしたことを
波に喩えている。
荒らだちし 波に心は 騒がねど 寄せけむ磯を いかが恨みぬ
光源氏 ⇒ 源典侍 (返歌)
【現代語訳】
頭中将の荒々しい振る舞いには驚かないが
彼を寄せつけたあなたを恨まずにはいられない
なか絶えば かことや負ふと 危ふさに はなだの帯を 取りてだに見ず
光源氏 ⇒ 頭中将 (贈歌)
【現代語訳】
頭中将と源典侍の関係が切れたら私のせいだと非難されると案じています
薄青色の帯は私には関係ありません
※源氏は頭中将の帯をこの和歌とともに
返却した。「帯」は源典侍を指す。
君にかく 引き取られぬる 帯なれば かくて絶えぬる なかとかこたむ
頭中将 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
あなたにこのように取られてしまった帯なので
このように源典侍との仲も絶えてしまったとしましょう
※「帯」は源典侍を指す。
「源典侍をあなたにとられてしまったので、
頭中将と源典侍の仲は切れてしまった」の意。
尽きもせぬ 心の闇に 暮るるかな 雲居に人を 見るにつけても
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
尽きない恋の闇に何も見えません
雲のように高い地位(中宮)についた人を見るにつけても
※「心の闇」は若宮への親心の闇と、
藤壺への恋の闇と両方の意味を持つ。
中宮になった藤壺の宮への叶わない恋心を嘆く和歌。
花宴(8首)
おほかたに 花の姿を 見ましかば つゆも心の おかれましやは
藤壺の宮(独詠歌)
【現代語訳】
普通の気持ちで花のように美しいお姿を拝見するのなら
少しも気を遣わなかったものを
※光源氏の美しさを賛美したい気持ちを抑える藤壺の歌
深き夜の あはれを知るも 入る月の おぼろけならぬ 契りとぞ思ふ
光源氏 ⇒ 朧月夜(贈歌)
【現代語訳】
春の夜の風情をご存知なのも
前世からの御縁が浅くなかったのだと思います
※朧月夜と出会った宿縁の深さを詠んだ和歌。
憂き身世に やがて消えなば 尋ねても 草の原をば 問はじとや思ふ
朧月夜 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
つらい身のまま名のらないままこの世から消えてしまったら
草の原まで尋ねて来て下さらないのではと思います
※「草の原」は死後の世界。
光源氏の歌の返歌ではなく、新たに詠んだ贈歌。
相手の和歌を引用していない。
いづれぞと 露のやどりを 分かむまに 小笹が原に 風もこそ吹け
光源氏 ⇒ 朧月夜(返歌)
【現代語訳】
誰だろうかと家を探しているうちに
世間に噂が立ったら大変です
世に知らぬ 心地こそすれ 有明の 月のゆくへを 空にまがへて
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
これまで経験したことのない気持ちだ
有明の月の行方を見失ってしまって
※「有明の月」は朧月夜を指す。
朧月夜を素性を知りたいと思う源氏の歌。
わが宿の 花しなべての 色ならば 何かはさらに 君を待たまし
右大臣 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
私の家の藤の花が普通の色であるならば
どうしてあなたをお待ちしましょうか
※「我が家の藤の花は美しいから、
ぜひお越しください」の意。
「花」は暗に娘のことを指すか。
梓弓 いるさの山に 惑ふかな ほの見し月の 影や見ゆると
光源氏 ⇒ 朧月夜(贈歌)
【現代語訳】
月が沈むいるさの山の周辺で迷っています
ほのかに見た月をまた見ることができるかと
※この日、右大臣家で「弓の結(競射)」が
あったため、「弓」を詠みこんだ。
「月」は朧月夜を指す。
心いる 方ならませば 弓張の 月なき空に 迷はましやは
朧月夜 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
本当に深い心で思っていらっしゃるならば
月が出ていなくても迷うことがありましょうか
※「あなたの気持ちが薄いから、迷っているのでしょう」
と切り返した歌。
葵(24首)
影をのみ 御手洗川の つれなきに 身の憂きほどぞ いとど知らるる
六条御息所(独詠歌)
【現代語訳】
御禊であなたのお姿をちらっと見て
その冷たい態度に我が身のつらさがますます思い知らされます
※「御手洗川」の「み」は「見」をかける。
御禊の日、車争いの直後に詠んだ歌。
行列に供奉した光源氏は六条御息所の車に
気づかず、通り過ぎてしまう。
はかりなき 千尋の底の 海松ぶさの 生ひゆくすゑは 我のみぞ見む
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
限りなく深い海底に生えている海松のように
豊かに成長してゆくあなたの黒髪は私だけが見届けよう
※「あなたの将来は、私だけが見届けよう」の意。
千尋とも いかでか知らむ 定めなく 満ち干る潮の のどけからぬに
紫の上 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
深い愛情を約束されてもどうして分りましょう
落ち着きなく満ちたり干いたりする潮のようなあなたですから
はかなしや 人のかざせる 葵ゆゑ 神の許しの 今日を待ちける
源典侍 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
ああむなしい、他の女と一緒にいるとは
神の許す今日(賀茂祭)を待っていましたのに
※「あふひ」は「葵」と「逢ふ日」をかける。
この時代よく用いられた用法である。
「かざす」は葵祭で葵を頭にかざしたことにちなむ。
「人のかざす」は源氏が他の女(紫の上)
のものになってしまったことを言う。
かざしける 心ぞあだに おもほゆる 八十氏人に なべて逢ふ日を
光源氏 ⇒ 源典侍(返歌)
【現代語訳】
好色者のあなたの心の方こそ信用ならないですね
たくさんの男に見境なくなびくのですから
※「かざしける心」は源氏との逢瀬を願った源典侍の心。
「八十氏人になべて逢ふ日」は、
多くの人に会える葵祭の日を意味している。
悔しくも かざしけるかな 名のみして 人だのめなる 草葉ばかりを
源典侍 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
ああ悔しい、葵祭の日が「逢う日」なんて名ばかりですね
期待だけさせておいて、私はただの草葉に過ぎないのですか
※「期待外れでした」の意
袖濡るる 恋路とかつは 知りながら おりたつ田子の みづからぞ憂き
六条御息所 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
袖を濡らす恋だと知っていながら
その恋の泥沼に落ちてしまうわが身の辛いことよ
※「こひじ」は「恋路」と「泥(ひじ)」をかけている。
泥沼のように抜けられない辛い恋を想像させる歌。
浅みにや 人はおりたつ わが方は 身もそぼつまで 深き恋路を
光源氏 ⇒ 六条御息所(返歌)
【現代語訳】
袖が濡れるとは、あなたが浅い所に立っていらっしゃるからでしょう
私は全身が濡れるほど深い恋に落ちております
嘆きわび 空に乱るる わが魂を 結びとどめよ したがへのつま
六条御息所(生霊)⇒光源氏(贈歌)
【現代語訳】
悲しみに耐えられず宙に抜け出した私の魂を
結び留めてください、着物の下前の褄(つま)を結んで
※褄(つま)とは着物の裾の端のこと。
「着物の裾をしっかり結んで、
私の魂が抜け出ないようにしてください」の意。
生霊となった六条御息所が
葵の上にとり憑いて言わせた和歌。
のぼりぬる 煙はそれと わかねども なべて雲居の あはれなるかな
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
空に上った火葬の煙は雲と区別がつかないが
どの雲もしみじみと心を打つものだ
限りあれば 薄墨衣 浅けれど 涙ぞ袖を 淵となしける
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
決まりがあるために、私の喪服は薄く浅い墨色ですが
涙で袖は川の深みのように濡れ、深い悲しみに暮れている
※妻の喪に際しては、薄鈍色の喪服を着る決まりであった。
「服の色は薄いが、心は深く悲しんでいます」の意。
人の世を あはれと聞くも 露けきに 後るる袖を 思ひこそやれ
六条御息所 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
人の世の無常を聞くと涙がこぼれます
奥様に先立たれて、涙でお袖を濡らしていらっしゃるだろうとお察しいたします
とまる身も 消えしもおなじ 露の世に 心置くらむ ほどぞはかなき
光源氏⇒六条御息所(返歌)
【現代語訳】
生き残った人も亡くなった人も同じ、露のようにはかない世に
執着を残しているのはつまらないことです
※生き残った自分(源氏)と亡くなった葵の上、
ともに無常の身として、この世のはかなさを嘆く和歌。
「心置く」(執着する)には
六条御息所が生霊となったことを
暗示する意図があるか。
雨となり しぐるる空の 浮雲を いづれの方と わきて眺めむ
三位中将<頭中将> ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
妹が雨となって降る空に浮かぶ雲を
どちらの方向の雲として眺めようか
※「浮雲」は「憂き」をかける。
亡くなった妹(葵の上)の死を悼む歌。
見し人の 雨となりにし 雲居さへ いとど時雨に かき暮らすころ
光源氏⇒三位中将<頭中将>(返歌)
【現代語訳】
妻が雲となり雨となった空までが
ますます雨で暗く泣き暮らしている今日この頃です
草枯れの まがきに残る 撫子を 別れし秋の かたみとぞ見る
光源氏⇒ 大宮(贈歌)
【現代語訳】
草の枯れた垣根に咲き残っている撫子(夕霧)を
秋に死別した葵の上の形見と思います
※「撫子」は葵の上との間に生まれた若君(夕霧)を指す。
「秋」は葵の上を暗示する。
「葵の上の形見として若君を愛していきます」の意。
今も見て なかなか袖を 朽たすかな 垣ほ荒れにし 大和撫子
大宮⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
今もこの子を見てかえって涙で袖を濡らしております
垣根も荒れはてて母親に先立たれてしまった撫子なので
わきてこの 暮こそ袖は 露けけれ もの思ふ秋は あまた経ぬれど
光源氏⇒ 朝顔の君(贈歌)
【現代語訳】
今日の夕暮れはとりわけ涙に袖を濡らしております
物思いのする秋は今までもたくさん経験してきましたが
秋霧に 立ちおくれぬと 聞きしより しぐるる空も いかがとぞ思ふ
朝顔の君⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
秋霧の立つ頃に、奥様に先立たれなさったとお聞きしましたが
昨今の時雨の季節にどんなにお悲しみかとお察し申し上げます
なき魂ぞ いとど悲しき 寝し床の あくがれがたき 心ならひに
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
亡くなった人の魂もますます悲しんでいることだろう
一緒に寝た床を私も離れがたく思うのだから
君なくて 塵つもりぬる 常夏の 露うち払ひ いく夜寝ぬらむ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
あなたが亡くなってから塵の積もった床に
涙を払いながら何度ひとりで寝たことだろう
※「常夏」は「床」とかけている。
あやなくも 隔てけるかな 夜をかさね さすがに馴れし 夜の衣を
光源氏⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
どうしてこれまで何でもない関係でいたのでしょう
何度も夜を一緒に過ごし馴れ親しんで来た仲なのに
あまた年 今日改めし 色衣 着ては涙ぞ ふる心地する
光源氏⇒ 大宮(贈歌)
【現代語訳】
何年も元日には、こちらに参上して着替えをしてきた晴着ですが
今日はこれを着ると涙がこぼれる心地がする
新しき 年ともいはず ふるものは ふりぬる人の 涙なりけり
大宮⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
新年になったとはいえ降りそそぐものは
老いた私の涙です
※「ふる」に「降る」と「古る」をかけている。
賢木(33首)
神垣は しるしの杉も なきものを いかにまがへて 折れる榊ぞ
六条御息所 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
こちらの野の宮には目印となる杉もないのに
どう間違えて折って持って来た榊なのでしょう
※榊の枝を持って、
野の宮を訪問した光源氏に贈った歌。
少女子が あたりと思へば 榊葉の 香をなつかしみ とめてこそ折れ
光源氏 ⇒ 六条御息所(返歌)
【現代語訳】
神に仕える少女がいる辺りだと思うと
榊葉の香りが恋しくなり、探し求めて折ったのです
暁の 別れはいつも 露けきを こは世に知らぬ 秋の空かな
光源氏 ⇒ 六条御息所(贈歌)
【現代語訳】
あなたとの明け方の別れではいつも涙に濡れたが
今朝の別れは今までにないくらい涙に曇る秋の空です
※伊勢に下向する六条御息所との
別れを悲しむ和歌。
おほかたの 秋の別れも 悲しきに 鳴く音な添へそ 野辺の松虫
六条御息所 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
ただでさえ秋の別れは悲しいものなのに
さらに鳴いて悲しませないで野辺の松虫よ
八洲もる 国つ御神も 心あらば 飽かぬ別れの 仲をことわれ
光源氏 ⇒ 伊勢の斎宮(贈歌)
【現代語訳】
我が国をお守りされている国つ神も心を持っているのなら
悲しみの尽きない別れを遂げなければならない理由を教えてください
※六条御息所の娘に贈った歌。
国つ神 空にことわる 仲ならば なほざりごとを まづや糾さむ
斎宮の女別当 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
国つ神がお二人の仲を裁かれることになったなら
あなたの誠意のないお言葉をまず問い詰められることでしょう
※斎宮が、女別当に代作させた歌。
そのかみを 今日はかけじと 忍ぶれど 心のうちに ものぞ悲しき
六条御息所(独詠歌)
【現代語訳】
昔のことを今日は思い出すまいと耐えていたが
心の中では悲しく思われます
※斎宮の娘に付きそって伊勢を下る六条御息所の和歌。
16歳で故東宮に入内して20歳で先立たれた
思い出が心に浮かんで悲しんでいる。
振り捨てて 今日は行くとも 鈴鹿川 八十瀬の波に 袖は濡れじや
光源氏 ⇒ 六条御息所(贈歌)
【現代語訳】
あたなは私を捨てて今日、旅立って行かれるが、鈴鹿川を
渡る時に袖を濡らして涙に濡れるのではないでしょうか
鈴鹿川 八十瀬の波に 濡れ濡れず 伊勢まで誰れか 思ひおこせむ
六条御息所 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
鈴鹿川の数多い瀬の波に袖が濡れるか濡れないか
伊勢に行った私のことを誰が思い起こしてくださるでしょうか
行く方を 眺めもやらむ この秋は 逢坂山を 霧な隔てそ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
あの方が旅立った方角を眺めていよう、今年の秋は
「逢う」という逢坂山を霧よ隠さないでくれ
蔭ひろみ 頼みし松や 枯れにけむ 下葉散りゆく 年の暮かな
兵部卿宮(唱和歌)
【現代語訳】
木陰が広いと頼りにしていた松の木は枯れてしまったのか
下のほうの葉が散って行く年の暮れですね
※「松」は桐壺院を、
「下葉」は後宮の女性たちを喩える。
桐壺院が崩御し、女御・更衣たちが
内裏を退出していくさまを詠んだ和歌。
さえわたる 池の鏡の さやけきに 見なれし影を 見ぬぞ悲しき
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
氷の張った池が鏡のように明るく光っているが
長年見慣れた人影を見られないのが悲しい
年暮れて 岩井の水も こほりとぢ 見し人影の あせもゆくかな
王命婦(唱和歌)
【現代語訳】
年が暮れて岩から湧く水も凍りつき
見慣れた人影も見えなくなっていきますね
心から かたがた袖を 濡らすかな 明くと教ふる 声につけても
朧月夜 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
自分からあれこれと考えると涙で袖が濡れてしまいます
夜が明けると教えてくれる声につけましても
嘆きつつ わが世はかくて 過ぐせとや 胸のあくべき 時ぞともなく
光源氏 ⇒ 朧月夜(返歌)
【現代語訳】
嘆きながら生涯このように過ごせというのですか
胸の思いが晴れる瞬間もないのに
逢ふことの かたきを今日に 限らずは 今幾世をか 嘆きつつ経む
光源氏 ⇒ 藤壺(贈歌)
【現代語訳】
お逢いすることの難しさがこれからも続くのならば
何度転生しても嘆きながら過すことでしょう
※「今幾世」は今後生まれ変わる
いくつもの世のことを言う。
長き世の 恨みを人に 残しても かつは心を あだと知らなむ
藤壺 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
幾世もの永い怨みを私に残したとしても
あなたのお心はまた一方ですぐに変わるものとご承知ください
※「あだ」は源氏の贈歌の「かたき」からの連想。
かたき ⇒ 敵 ⇒ あだ(仇)
浅茅生の 露のやどりに 君をおきて 四方の嵐ぞ 静心なき
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
浅茅生に置く露のようにはかない俗世にあなたを置いてきたので
まわりから吹き寄せる嵐のような世間の噂を聞くにつけ、心配になります
※雲林院に参詣した源氏が
紫の上に宛てた文に書いた和歌。
風吹けば まづぞ乱るる 色変はる 浅茅が露に かかるささがに
紫の上 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
風が吹くとすぐ乱れて心変わりするはかない浅茅生の露の上に
巣をはってそれを頼みに生きている蜘蛛のような私ですからね
※「色変はる」は源氏が心変わりすることの比喩。
「ささがに(蜘蛛)」は紫の上自身を喩える。
かけまくは かしこけれども そのかみの 秋思ほゆる 木綿欅かな
光源氏 ⇒ 朝顔の君(贈歌)
【現代語訳】
口にして言うのは畏れ多いことですが
その昔の秋の出来事が思い出されます
※「そのかみの秋」は物語中には出てこない。
「帚木」巻に源氏がかつて朝顔の君に
和歌を贈ったという記述があり、その時のことを指すか。
そのかみや いかがはありし 木綿欅 心にかけて しのぶらむゆゑ
朝顔の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
その昔どうだったとおっしゃるのですか
心の底から思い慕うとおっしゃるわけは
九重に 霧や隔つる 雲の上の 月をはるかに 思ひやるかな
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
内裏には霧が何重にもかかってかかっているのでしょうか
雲の上の月が見えなくて、はるか遠くに思い申し上げています
※「霧」は朱雀帝の周辺の悪意ある人々(右大臣など)
「月」は宮中を指す。
藤壺の宮はこの日、宮中を退出した。
「帝の周辺の悪意ある人に隔てられて、
宮中のとの間に距離ができてしまいました」の意。
月影は 見し世の秋に 変はらぬを 隔つる霧の つらくもあるかな
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(返歌)
【現代語訳】
月の光はあの頃の秋と変わらないのに
隔てる霧のあるのが辛いと感じられます
※「月」は宮中を指すが、
藤壺の宮の意味も込めて、
源氏に冷淡な態度をとっている藤壺の宮を
責めている。
木枯の 吹くにつけつつ 待ちし間に おぼつかなさの ころも経にけり
朧月夜 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
木枯が吹くごとにあなたの訪問を待っているうちに
長い月日が経過してしまいました
※源氏の訪れがないことを恨む和歌。
あひ見ずて しのぶるころの 涙をも なべての空の 時雨とや見る
光源氏 ⇒ 朧月夜(返歌)
【現代語訳】
お逢いできず恋心を忍んで泣いている涙の雨までを
よくある秋の時雨とお思いなのでしょうか
別れにし 今日は来れども 見し人に 行き逢ふほどを いつと頼まむ
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
故院にお別れ申し上げた命日が巡って来ましたが
亡き人にまためぐり逢える時はいつと期待できようか
※雪が多く積もった日だったので
「行き」には「雪」をかけて冬の情景を喚起している。
亡き桐壺院に逢えない悲しみを詠んだ和歌。
ながらふる ほどは憂けれど 行きめぐり 今日はその世に 逢ふ心地して
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
生き長らえておりますのは辛いことですが
命日の今日は、亡き院が生きていた頃ような思いがして
※「ながらふる」に「(雪が)降る」をかけている。
「行き」に「雪」をかけるのは
源氏の和歌から引用している。
月のすむ 雲居をかけて 慕ふとも この世の闇に なほや惑はむ
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
月のように心のすんだ出家後の有様をお慕い申しあげても
なおも子どもを思うこの世の苦しみに迷い続けるのだろうか
※「月のすむ雲居」は藤壺の宮の喩え。
「すむ」には「住む」と「澄む」を
かけて清らかな出家の境地を暗示する。
「後を追って出家したいけれど、
2人の間の子(東宮)を思う煩悩ゆえに
出家できない」の意。
おほかたの 憂きにつけては 厭へども いつかこの世を 背き果つべき
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
世間でよくある嫌なことからは離れられたが、
いつになったら子どもへの煩悩を捨て去ることができるだろうか
※「私も東宮のことが心配でなりません」の意。
ながめかる 海人のすみかと 見るからに まづしほたるる 松が浦島
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
物思いに沈んでいらっしゃる方の住み家と思うと
まず先に涙に濡れてしまいます
※年が明け、桐壺院の喪が明けた
藤壺の宮を見舞う和歌。
ありし世の なごりだになき 浦島に 立ち寄る波の めづらしきかな
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
昔の名残さえないこのような場所に
立ち寄ってくださるとはありがたいことです
※浦島太郎伝説を踏まえた和歌。
それもがと 今朝開けたる 初花に 劣らぬ君が 匂ひをぞ見る
三位中将<頭中将> ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
それが見たいと思っていた今朝咲いた花に
負けないくらいのお美しさの我が君を見ています
※その日の朝、薔薇が咲きかけていた。
源氏の美しさは薔薇にも劣らないと称賛する。
時ならで 今朝咲く花は 夏の雨に しをれにけらし 匂ふほどなく
光源氏 ⇒ 三位中将<頭中将>(返歌)
【現代語訳】
時季に合わず今朝咲いた花は夏の雨に
しおれてしまったらしい、美しさを見せる間もなく
花散里(4首)
をちかへり えぞ忍ばれぬ ほととぎす ほの語らひし 宿の垣根に
光源氏 ⇒ 中川の女(贈歌)
【現代語訳】
昔の気持ちに戻って懐かしく思わずにはいられない、ほととぎすの声
わずかに契りを交わした家なので
※源氏が昔の恋人に詠んだ和歌。
ほととぎす 言問ふ声は それなれど あなおぼつかな 五月雨の空
中川の女 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
ほととぎすの声ははっきりと聴き分けますが
どのようなご用件かわかりません、五月雨の空のように
※「源氏の声だと分かるが、
今さら何のご用?」とすっとぼけた和歌。
橘の 香をなつかしみ ほととぎす 花散る里を たづねてぞとふ
光源氏 ⇒ 麗景殿女御(贈歌)
【現代語訳】
橘の香りを懐かしく思って
ほととぎすが花の散ったこのお邸にやって参りました
※「五月待つ 花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする」
(古今和歌集 夏、一三九、読人知らず)と
「橘の 花散里の 郭公 片恋しつつ 鳴く日しぞ多き」
(万葉集八、一四七七、大伴旅人)
の2首を踏まえた和歌。
平安時代において、橘の香りは、
昔を懐かしむ意味を持っていた。
父桐壺帝の御代を懐かしむ気持ちの籠った和歌。
ほととぎすを源氏に見立てる。
人目なく 荒れたる宿は 橘の 花こそ軒の つまとなりけれ
麗景殿女御 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
訪ねる人もおらず荒れてしまった邸には
軒端に咲く橘だけがあなたをお誘いするきっかけになったのでした
※「つま」は「端」の意と「きっかけ」の意をかける。
須磨(48首)
鳥辺山 燃えし煙も まがふやと 海人の塩焼く 浦見にぞ行く
光源氏 ⇒ 大宮(贈歌)
【現代語訳】
かつて鳥辺山で焼いた煙に似ているのではないかと
海人が塩を焼く煙を見に、須磨の浦へ行きます
※須磨へ下向することが決まった源氏。
「浦見」には「恨み」がかかっている。
以前、葵の上を鳥辺野で火葬した時の
悲しみを回想しつつ、
須磨をあの世に近い場所として捉えている。
亡き人の 別れやいとど 隔たらむ 煙となりし 雲居ならでは
大宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
亡き娘との仲もますます離れていくのでしょう
煙となった都の空ではないのでは
※源氏が須磨へ下向してしまうと、
亡き葵の上との仲がますます離れてしまうと
嘆いた和歌。
身はかくて さすらへぬとも 君があたり 去らぬ鏡の 影は離れじ
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
わが身はこのように須磨へ流離しようとも
鏡に映った面影はあなたの元を離れずに残ることでしょう
※紫の上との別離の歌。
別れても 影だにとまる ものならば 鏡を見ても 慰めてまし
紫の上 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
お別れしてもあなたの影だけでもとどまってくれるものなら
その影が映った鏡を見て慰めることもできましょうに
月影の 宿れる袖は せばくとも とめても見ばや あかぬ光を
花散里 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
月の光が映っている私の袖は狭いですが
このままとどめて見ておきたいと思います、見飽きることのない光を
※「袖」は花散里自身を指し、
「月影」「あかぬ光」は源氏を指す。
源氏の須磨流離を悲しむ花散里の和歌。
行きめぐり つひにすむべき 月影の しばし雲らむ 空な眺めそ
光源氏 ⇒ 花散里(返歌)
【現代語訳】
空を渡っていき、ついには澄むはずの月の光ですから
しばらくの間曇っていても空を見て悲しんだりしないでください
※「すむ」には「住む」と「澄む」をかける。
「いつかは澄んだ潔白の身が証明されて、
都に帰還して花散里と一緒に住めるから、
悲しまないで」の意。
逢ふ瀬なき 涙の河に 沈みしや 流るる澪の 初めなりけむ
光源氏 ⇒ 朧月夜(贈歌)
【現代語訳】
あなたに逢えず泣き暮れて涙の川に沈んだことが
須磨へ流浪する身の上となるきっかけだったのでしょうか
※「流るる澪」に
「泣かるる身を」をかける。
実際には逢瀬があったのに、
「逢ふ瀬なき」と他人の目を気にしている。
涙河 浮かぶ水泡も 消えぬべし 流れて後の 瀬をも待たずて
朧月夜 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
涙の川に浮かんでいる泡も消えてしまうでしょう
生き長らえて再会できる日を待たずに
※「あなたに再会するより前に
私の命が尽きてしまうでしょう」の意。
見しはなく あるは悲しき 世の果てを 背きしかひも なくなくぞ経る
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
桐壺院は崩御され、存命の方は悲しい身の上の世の末を…
私は出家した甲斐もなく泣き暮らしています
※「見し」は故桐壺院、
「ある」は源氏を指す。
源氏の須磨流離を悲しむ和歌。
別れしに 悲しきことは 尽きにしを またぞこの世の 憂さはまされる
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(返歌)
【現代語訳】
亡き桐壺院にお別れした際に悲しいことは経験し尽くしたと思ったのに
またもこの世のいっそう辛いことに遭ってしまいました
※「この世」の「こ」に「子」を連想させ
東宮を案じる気持ちを表している。
ひき連れて 葵かざしし そのかみを 思へばつらし 賀茂の瑞垣
右近将監 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
あなたにお供をして葵を頭に挿した御禊の日のことを思うと
御利益がなかったのかと辛い気持ちです、賀茂の神様よ
※「そのかみ」には「神」をかける。
憂き世をば 今ぞ別るる とどまらむ 名をば糺の 神にまかせて
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
辛い世の中である都を今離れて旅立つ
後に残る噂の裁きは、糺の神に委ねて
※「糺の神」は地名に基づいて
偽りを糺(ただ)す神とされていた。
亡き影や いかが見るらむ よそへつつ 眺むる月も 雲隠れぬる
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
亡き父桐壺院はどのように御覧になっておられるだろうか
父上だと思って見上げていた月の光も雲に隠れてしまった
※「月」は故桐壺院の比喩。
「月」が「雲隠れ」は
桐壺院があの世で泣いている姿を喩える。
いつかまた 春の都の 花を見む 時失へる 山賤にして
光源氏 ⇒ 東宮(贈歌)
【現代語訳】
いつか再び春の都の花を見ることができるだろうか
時流を失った山賤のようなこの身ですが
※「春の都の花」は東宮が即位する未来を言う。
「山賊」は須磨へ下向する自分を卑下している。
咲きてとく 散るは憂けれど ゆく春は 花の都を 立ち帰り見よ
王命婦 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
咲いたかと思うとすぐ散ってしまう桜の花は悲しいけれど
また都に帰ってきて春の都を御覧になってください
※女房の王命婦が幼い東宮の代わりに返歌をした。
生ける世の 別れを知らで 契りつつ 命を人に 限りけるかな
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
生きている間に生き別れというものがあるとは知らず
命のある限りはあなたとずっと一緒だと思っていたよ
惜しからぬ 命に代へて 目の前の 別れをしばし とどめてしがな
紫の上 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
勿体なくもない私の命に代えて、今のこの
別れの瞬間を少しの間でも引きとどめたいものです
唐国に 名を残しける 人よりも 行方知られぬ 家居をやせむ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
中国で名を残した人以上に
行方も知らない寂しい暮らしをするのだろうか
※中国の屈原の故事が念頭にある歌。
屈原は讒言により都を追われ、
汨羅江(べきらこう)に身を投げた。
故郷を 峰の霞は 隔つれど 眺むる空は 同じ雲居か
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
なつかしい都を山の霞は遠く隔てるが
眺めている空は同じ空なのか
松島の 海人の苫屋も いかならむ 須磨の浦人 しほたるるころ
光源氏 ⇒ 藤壺の宮(贈歌)
【現代語訳】
出家して尼となられたあなたはいかがお過ごしですか
私は須磨の浦で泣き暮らしています
※「松島」に「待つ」をかけ、
「海人(あま)」に「尼」をかけている。
こりずまの 浦のみるめの ゆかしきを 塩焼く海人や いかが思はむ
光源氏 ⇒ 朧月夜(贈歌)
【現代語訳】
性懲りもなくあなたに逢いたいのですが
あなたはどう思っていらっしゃいますか
※「懲りずま」に「須磨」をかけ、
「海松布(みるめ)」に「見る目」をかけている。
塩垂るる ことをやくにて 松島に 年ふる海人も 嘆きをぞつむ
藤壺の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
泣き暮れることを仕事として
出家した私も悲しみを積み重ねています
※「松島」と「待つ」、
「海人」と「尼」、
「嘆き」と「投げ木」をかけている。
「投げ木」は、「積む」の縁語。
浦にたく 海人だにつつむ 恋なれば くゆる煙よ 行く方ぞなき
朧月夜 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
須磨の浦の海人でさえ人目を忍ぶ恋なのですから
都にいる私の恋の火の煙はゆく宛もなく、くすぶっています
※「恋(こひ)」の「ひ」に「火」をかけている。
「燻ゆる(くゆる)」に「悔ゆる」をかけている。
浦人の 潮くむ袖に 比べ見よ 波路へだつる 夜の衣を
紫の上 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
あなたのお袖とお比べてご覧ください
遠く海の道を隔てた都で、寂しく袖を濡らしている夜の衣と
※源氏の文に対する返事
うきめかる 伊勢をの海人を 思ひやれ 藻塩垂るてふ 須磨の浦にて
六条御息所 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
つらい思いをしている伊勢の私を思いやってください
泣き暮らしていらっしゃるという須磨の浦から
※「浮き布(うきめ)」に「憂き目」をかける。
源氏の文に対する返事。
伊勢島や 潮干の潟に 漁りても いふかひなきは 我が身なりけり
六条御息所 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
伊勢の海の干潟で貝を漁っても
何の甲斐もないのは私です
※「貝」と「甲斐」をかけている。
伊勢人の 波の上漕ぐ 小舟にも うきめは刈らで 乗らましものを
光源氏 ⇒ 六条御息所(返歌)
【現代語訳】
波の上を漕ぐ舟に一緒に乗って伊勢までお供すればよかったな
須磨で浮き海布などを刈って辛い思いをしないで
※「うきめ」は「浮き海布」と「憂き目」をかける。
「浮き海布」は海面に浮いている海藻のこと。
海人がつむ なげきのなかに 塩垂れて いつまで須磨の 浦に眺めむ
光源氏 ⇒ 六条御息所(返歌)
【現代語訳】
海人が積み重ねる投げ木の中に泣き暮らし
いつまで須磨の浦にいることでしょう
※「投げ木」に「嘆き」をかける。
荒れまさる 軒のしのぶを 眺めつつ しげくも露の かかる袖かな
花散里 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
いっそう荒れていく軒の忍ぶ草を眺めていると
ひどく涙の露に濡れる袖だこと
※「しのぶ」は「偲ぶ」と「忍ぶ草」、
「眺め」には「長雨」がかかっている。
恋ひわびて 泣く音にまがふ 浦波は 思ふ方より 風や吹くらむ
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
恋しさに耐えきれず泣く私の泣き声に交じって波音が聞こえる
恋しい人のいる都の方から風が吹くからだろうか
初雁は 恋しき人の 列なれや 旅の空飛ぶ 声の悲しき
光源氏 (唱和歌)
【現代語訳】
初雁は都に残してきた恋しい人の仲間なのだろうか
旅の空を飛ぶ声が悲しく聞こえる
※「初雁」とは南下してきた雁。
かきつらね 昔のことぞ 思ほゆる 雁はその世の 友ならねども
良清 (唱和歌)
【現代語訳】
次から次へと昔の出来事が懐かしく思い出されます
雁は昔から友達であったわけではないのですが
心から 常世を捨てて 鳴く雁を 雲のよそにも 思ひけるかな
民部大輔 (唱和歌)
【現代語訳】
自分の意志で常世を捨てて鳴いて空を旅する雁を
他人事のように思っていたなあ
※源氏が都で栄えていた時代を、
「常世」に喩えている。
常世とは永久に不変の神域。
常世出でて 旅の空なる 雁がねも 列に遅れぬ ほどぞ慰む
前右近将監(唱和歌)
【現代語訳】
常世を出て旅の空にいる雁も
仲間の隊列に遅れないでいる間は心も慰みましょう
※「源氏を含め仲間と一緒にいることで
流浪の悲しみが慰められます」の意。
見るほどぞ しばし慰む めぐりあはむ 月の都は 遥かなれども
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
月を見ている間は少しの間だが心慰められる
また逢えるであろう月の都は遥か遠くであるが
※「月の都」は京の都のこと。
憂しとのみ ひとへにものは 思ほえで 左右にも 濡るる袖かな
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
辛いとばかり一途に思うこともできず
須磨流離の辛さと朱雀帝への愛しさとの両方で涙に濡れるわが袖だ
※「ひとへ」は「偏に」と「単衣」をかける。
琴の音に 弾きとめらるる 綱手縄 たゆたふ心 君知るらめや
筑紫の五節 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
琴の音に引き止められてしまいました。綱手縄のように
ゆらゆら揺れている私の心をお分かりでしょうか
※「ひき」に「引き」と「弾き」をかける。
心ありて 引き手の綱の たゆたはば うち過ぎましや 須磨の浦波
光源氏 ⇒ 筑紫の五節(返歌)
【現代語訳】
私を思う気持ちがあって引手綱のように揺れるのならば
あなたは通り過ぎて行かないでしょう、この須磨の浦を
山賤の 庵に焚ける しばしばも 言問ひ来なむ 恋ふる里人
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
山賊が貧しい家で焼いている柴のように
しばしば訪ねて来てほしい恋しい都の人よ
※「しばしば」は「柴々」と「屡々」をかける。
いづ方の 雲路に我も 迷ひなむ 月の見るらむ ことも恥づかし
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
どの方向の雲に私は迷いさすらって行くのだろうか
月が見ているだろうことも恥ずかしい
友千鳥 諸声に鳴く 暁は ひとり寝覚の 床も頼もし
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
友千鳥が一斉に鳴いている明け方は
一人の床に寝覚めて泣く私も心強い気がする
※「友千鳥」は群れをなしている千鳥。
いつとなく 大宮人の 恋しきに 桜かざしし 今日も来にけり
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
いつということもなく都の人が恋しく思われるのに
昔、桜をかざして遊んだ花の宴の日がまたやって来た
※源氏は須磨で春を迎えた。都を懐かしむ和歌。
故郷を いづれの春か 行きて見む うらやましきは 帰る雁がね
光源氏 ⇒ 宰相中将<頭中将>(贈歌)
【現代語訳】
ふるさとの春をいつになったら、帰って見ることができるだろう
うらやましいのは今帰って行く雁だ
※「雁」は須磨を訪れている頭中将を指す。
あかなくに 雁の常世を 立ち別れ 花の都に 道や惑はむ
宰相中将<頭中将> ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
まだ心残りなうちに雁は常世を立ち去りますが
花の都への道にも迷いそうです
※「雁」に「仮」をかけている。
雲近く 飛び交ふ鶴も 空に見よ 我は春日の 曇りなき身ぞ
光源氏 ⇒ 宰相中将<頭中将>(贈歌)
【現代語訳】
雲の近くを飛びかう鶴よ、はっきりとご覧ください
私は春の日のように少しもやましいところのない身なのです
※「雲近く飛び交う鶴」は宮中に仕えている人を暗示する。
たづかなき 雲居にひとり 音をぞ鳴く 翼並べし 友を恋ひつつ
宰相中将<頭中将> ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
頼りない雲居に私は一人で泣いています
かつて翼を並べた友であるあなたを恋い慕いながら
知らざりし 大海の原に 流れ来て ひとかたにやは ものは悲しき
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
今まで見たこともなかった大海原に流れされてきて
ひとかたならず悲しく思われることよ
※禊の際に詠んだ和歌。
人形に穢れや罪を託し、舟に乗せて流すことで厄払いをする。
「ひとかた」には「人形」と「一方」をかけている。
八百よろづ 神もあはれと 思ふらむ 犯せる罪の それとなければ
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
八百万の神々も私に同情してくださるでしょう
これといって犯した罪はないのだから
※八百万の神に身の潔白を訴える。
明石(30首)
浦風や いかに吹くらむ 思ひやる 袖うち濡らし 波間なきころ
紫の上 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
須磨の浦ではどんなに激しい嵐が吹いていることでしょう
あなたのことが心配で袖を涙で濡らしているこの頃です
※紫の上が都から源氏のことを心配して詠んだ歌。
海にます 神の助けに かからずは 潮の八百会に さすらへなまし
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
海に鎮座されている神の御加護がなかったならば
多くの潮流が渦巻く沖合に流され行方知らずとなっただろう
※住吉の神に感謝を述べる和歌。
「ます」「潮の八百会」は祝詞の用語。
遥かにも 思ひやるかな 知らざりし 浦よりをちに 浦伝ひして
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
遥か遠くからあなたを心配しております
知らない浦(須磨)からさらに遠くの浦(明石)に流れ着いても
※源氏はこのとき、須磨から明石へ移動していた。
あはと見る 淡路の島の あはれさへ 残るくまなく 澄める夜の月
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
ああと、しみじみ眺める淡路島の情趣まで
すっかり照らしだす今夜の月であることよ
一人寝は 君も知りぬや つれづれと 思ひ明かしの 浦さびしさを
明石の入道 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
独り寝の辛さはあなたもお分かりになりましたか
所在なく物思いに夜を明かす明石の浦の寂しさを
※「も」は同類の意味を持ち、
「源氏だけでなく明石の君も独り寝が寂しい」の意。
旅衣 うら悲しさに 明かしかね 草の枕は 夢も結ばず
光源氏 ⇒ 明石の入道(返歌)
【現代語訳】
旅の日々の寂しさに夜を明かしかねて
穏やかな夢を見ることもありません
をちこちも 知らぬ雲居に 眺めわび かすめし宿の 梢をぞ訪ふ
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
地理のわからない土地にわびしい生活を送っていますが
お噂を聞いて文を差し上げます
※「かすめし」は入道が源氏に娘のことを話したという意味。
眺むらむ 同じ雲居を 眺むるは 思ひも同じ 思ひなるらむ
明石の入道 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
あなたが眺めていらっしゃる空を同じく私も眺めているのは
きっと同じ気持ちで物思いにふけっているからなのでしょう
※娘の代わりに明石の入道が詠んだ返歌。
「眺む」「同じ」「思ひ」を2度ずつ使用し、
娘と源氏が同じ気持ちであると強調。
いぶせくも 心にものを 悩むかな やよやいかにと 問ふ人もなみ
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
気分が晴れなくて、心の中で悩んでおります
いかがですかと訪問してくれる人もいないので
思ふらむ 心のほどや やよいかに まだ見ぬ人の 聞きか悩まむ
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
私を思うとおっしゃいますが、真意はいかがなものでしょうか
まだ見たこともない方が噂だけ聞いて悩むということがありましょうか
秋の夜の 月毛の駒よ 我が恋ふる 雲居を翔れ 時の間も見む
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
秋の夜の月毛の馬よ、私が恋しく思う都へ天翔けてくれ
少しの間でもあの人に会いたいので
※紫の上を恋うる和歌。
「月毛」の馬に、「月」という名を持つなら
夜空をかけて都に連れていってくれと願う。
むつごとを 語りあはせむ 人もがな 憂き世の夢も なかば覚むやと
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
男女の語らいをできる相手がほしいのです
この辛い世の夢がいくらかでも覚めやしないかと
※須磨流離を「憂き世の夢」ととらえ、
明石の君と結ばれることで悪い夢から
覚めると言い寄っている。
明けぬ夜に やがて惑へる 心には いづれを夢と わきて語らむ
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
明けない夜の闇にそのまま迷っている私の心には
どちらが夢か現実か判別してお話しすればよいのでしょうか
しほしほと まづぞ泣かるる かりそめの みるめは海人の すさびなれども
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
あなたのことを思うと、さめざめと泣けてしまいます
一時的な恋は海人の私の遊びですけれども
※「しほしほ(擬態語)」と「塩」、
「海松布(海草)」と「見る目」
をかけている。
明石の君との浮気を後ろめたく思っている。
うらなくも 思ひけるかな 契りしを 松より波は 越えじものぞと
紫の上 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
約束をしましたので、何の疑いもなく信じていました
末の松山を波は越えることがないように、心変わりはないものだと
※「君をおきてあだし心をわが持たば末の松山波も越えなむ」
(古今集、一〇九三、陸奥歌)などを引歌としている。
末の松山は高さ10mほどの小山で宮城県にある。
大津波がきても波が末の松山を越えることは
ないとされていた。
「絶対に起きないこと」の比喩として、
男女の不変の愛を誓う時に用いられる表現。
このたびは 立ち別るとも 藻塩焼く 煙は同じ 方になびかむ
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
いったんはお別れしますが、藻塩焼く煙が
同じ方向になびくように上京したら一緒に暮らしましょう
※「たび」は「旅」と「度」を書ける。
かきつめて 海人のたく藻の 思ひにも 今はかひなき 恨みだにせじ
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
海人が藻をかき集めて、
その藻を燃やしながら物思いしていますが
今は言っても甲斐のないことなので、お恨みはいたしません
※「ものおもひ」に
「物思い」と「藻」と「火」、
「かひなき」に「貝」と「甲斐」、
「うらみ」に「浦」と「恨み」をかけている。
「源氏が私を置いて都に帰還することを
恨みません」の意。
なほざりに 頼め置くめる 一ことを 尽きせぬ音にや かけて偲ばむ
明石の君 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
あなたがいい加減な気持ちでおっしゃるお言葉を
声をあげて泣きながら心にかけて、お偲び申しあげます
※「ひとこと」には「一琴」と「一言」をかける。
明石の君は源氏から形見の琴をもらった。
逢ふまでの かたみに契る 中の緒の 調べはことに 変はらざらなむ
光源氏 ⇒ 明石の君(返歌)
【現代語訳】
再会する時までの形見に残した琴の中の緒の調子のように
二人の仲の愛情も、大きくは変わらないでいてほしいです
※「かたみ」に「形見」と「互いに」、
「中のを」に琴の「中の緒」と二人の「仲」、
「ことに」に「異に」と「琴に」をかける。
うち捨てて 立つも悲しき 浦波の 名残いかにと 思ひやるかな
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
あなたを置き去りに明石の浦を旅立つ私も悲しい気持ちですが
後に残されたあなたはどのような気持ちになるかと心配です
年経つる 苫屋も荒れて 憂き波の 返る方にや 身をたぐへまし
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
長年住んだ粗末な家も、あなたが去った後は荒れはてて
辛い思いをするだろうから、いっそのこと打ち返す波に身を投げてしまいたい
※「かえる」の主語は、源氏と波の両方。
「都に帰る源氏についていきたい」という意と
「打ち返す波に投身してしまいたい」という意
両方の意味を含んでいる。
寄る波に 立ちかさねたる 旅衣 しほどけしとや 人の厭はむ
明石の君 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
ご用意しました旅のご装束は
私の涙に濡れていますので、あなたは嫌だとお思いになるかしら
※「たち」は「立ち」と「裁ち」をかけている。
「旅衣」までは下の句にかかる序詞であり、
「しほどけしとや 人の厭はむ」を導き出す
ための前置きとして機能している。
かたみにぞ 換ふべかりける 逢ふことの 日数隔てむ 中の衣を
光源氏 ⇒ 明石の君(返歌)
【現代語訳】
お互いに形見として着物を交換しよう
再会できる日まで、かなりの日数を隔てるでしょうから
※「隔てむ」は、「日数隔てむ」と
「隔てむ中の衣」を兼ねる掛詞。
世をうみに ここらしほじむ 身となりて なほこの岸を えこそ離れね
明石の入道 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
世の中が嫌になり、長年ここ明石の潮風に吹かれてきたが
依然として娘を理由としてこの世を離れることができません
※「うみ」は「海」と「憂み」、
「この岸」には「子」と「此」をかけている。
「此岸」はこの世、現世のこと。
都出でし 春の嘆きに 劣らめや 年経る浦を 別れぬる秋
光源氏 ⇒ 明石の入道(返歌)
【現代語訳】
都を去ったあの春の悲しさに劣っていようか
長い年月を過ごしたこの浦と別れる悲しい秋は
※源氏は一昨年の春3月20日頃に京を離れた。
その時の悲しみにも劣らないくらい、
明石の一族との別れが悲しい。
わたつ海に しなえうらぶれ 蛭の児の 脚立たざりし 年は経にけり
光源氏 ⇒ 朱雀帝(贈歌)
【現代語訳】
海辺でしおれて落ちぶれながら蛭子のように
立つこともできず三年を過ごして来ました
※蛭子(ヒルコ)とは日本神話に登場する神。
不具の子であったため、葦舟に乗せて流された。
「かぞいろはあはれと見ずや蛭の子は三歳になりぬ脚立たずして」
(日本紀竟宴和歌、大江朝綱)を踏まえた和歌である。
源氏は須磨・明石にいた期間の自分を
蛭子神に喩えている。
宮柱 めぐりあひける 時しあれば 別れし春の 恨み残すな
朱雀帝 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
このようにめぐり会えたのだから
昔別れた春の恨みは忘れてください
※「宮柱」は日本神話に基づく。
イザナギとイザナミはオノゴロ島に
柱を建て、その周りをまわって出逢った。
源氏と朱雀帝の再会のシーンで詠まれた和歌。
嘆きつつ 明石の浦に 朝霧の 立つやと人を 思ひやるかな
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
あなたが嘆きながら夜を明かしていらっしゃる明石の浦に
悲しみの吐息が朝霧となって立ちこめているのではないかと心配しています
※「明石」と「明かし」をかけている。
須磨の浦に 心を寄せし 舟人の やがて朽たせる 袖を見せばや
筑紫の五節 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
須磨の浦であなたに心を寄せていた舟人が
そのまま涙で朽ちてしまった袖をお見せしたいものです
※舟人に自分を喩えている。
帰りては かことやせまし 寄せたりし 名残に袖の 干がたかりしを
光源氏 ⇒ 筑紫の五節 (返歌)
【現代語訳】
かえって私が愚痴を言いたいくらいです、
あなたに気持ちを寄せていただいてから、
袖が涙に濡れて乾かないものですから
澪標(17首)
かねてより 隔てぬ仲と ならはねど 別れは惜しき ものにぞありける
光源氏 ⇒ 宣旨の君 (贈歌)
【現代語訳】
以前から特別に親しい間柄だったわけではないが
あなたとの別れは悲しい気持ちになるものだな
※「宣旨の君との別れが辛い」という意味の和歌。
宣旨の君は明石の姫君の乳母となる。
うちつけの 別れを惜しむ かことにて 思はむ方に 慕ひやはせぬ
宣旨の君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
お会いしたばかりで別れを惜しむ言葉は口実で
本当は愛しい人がいらっしゃる場所に行きたいのではないですか
※「思はむ方」は明石の君がいる場所。
いつしかも 袖うちかけむ をとめ子が 世を経て撫づる 岩の生ひ先
光源氏 ⇒ 明石の君 (贈歌)
【現代語訳】
天女が羽衣で岩を撫でるように、
早く姫君を手元に引き取って育てたい
岩のように生い先の長い姫の将来を祝って
※明石の姫君の長寿を祝い、
早く自分が引き取って世話をしたいと望んでいる。
ひとりして 撫づるは袖の ほどなきに 覆ふばかりの 蔭をしぞ待つ
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
私一人で姫君をお世話するのは不十分ですので
あなた様の大きな庇護を期待しております
※源氏の和歌の「袖」「撫づる」を引いて返している。
「袖のほどなき」は明石の君一人では
世話が行き届かないことを表す。
「覆ふばかりの蔭」は源氏の支援の喩え。
思ふどち なびく方には あらずとも われぞ煙に 先立ちなまし
紫の上 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
愛しあっている者同士が同じ方向になびいているのとは違って
私は煙となって先に亡くなってしまいたい
※この和歌の直前に、源氏は紫の上に
「あはれなりし夕べの煙」について語っている。
源氏の贈歌
「このたびは立ち別るとも藻塩焼く煙は同じ方になびかむ」
も紫の上に語って聞かせたと推測される。
紫の上の和歌は、源氏が明石で詠んだ和歌
を踏まえて詠んだもの。
誰れにより 世を海山に 行きめぐり 絶えぬ涙に 浮き沈む身ぞ
光源氏 ⇒ 紫の上 (返歌)
【現代語訳】
私はいったい誰のために憂き世を海へ山へとさすらい
涙を流し続けてて浮き沈みしてきたのでしょうか
※「海」と「憂み」をかけている。
「あなたのために辛いことを我慢してきたんですよ」の意。
海松や 時ぞともなき 蔭にゐて 何のあやめも いかにわくらむ
光源氏 ⇒ 明石の君 (贈歌)
【現代語訳】
姫君は、いつも同じ田舎にいたのでは
今日が五月五日の節句であり、五十日の祝であるとどうしてお分りになりましょうか
※「海松」は明石の姫君を指す。
「松」は長寿を予祝するもの。
「あやめ」は「菖蒲」と「文目」をかけ、
「いか」は「五十日」と「如何」をかける。
数ならぬ み島隠れに 鳴く鶴を 今日もいかにと 問ふ人ぞなき
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
人数にも入らない私のもとで育つ姫君を
今日の五十日の祝いはどうですかと訪ねてきてくれる人は他にいません
※姫君を「鶴」に喩え、
「み」に「身」をかけ、
「いか」に「五十」をかけている。
水鶏だに おどろかさずは いかにして 荒れたる宿に月を入れまし
花散里 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
水鶏が戸を叩いて教えてくれなかったら
この荒れた邸に月の光を迎え入れることができたでしょうか
※「だに」は「せめて~だけでも」の意。
「月」は光源氏の比喩。
「水鶏が鳴いて教えてくれたから、
あなたを迎え入れることができたのです」の意。
光源氏と花散里の再会。
おしなべて たたく水鶏に おどろかば うはの空なる 月もこそ入れ
光源氏 ⇒ 花散里 (返歌)
【現代語訳】
すべての家の戸を叩く水鶏の音にこたえて戸を開けたら
私以外の月の光が入ってくるのではないですか
住吉の 松こそものは かなしけれ 神代のことを かけて思へば
惟光 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
住吉の松を見るにつけ感無量です
昔の流浪の旅が思い出されますので
※「松」は「まづ」をかけている。
「住吉の松を見ると、まず真っ先に
須磨明石の流浪の日々が思い出されて感無量です」の意。
源氏がお供を連れて住吉詣を行った際の和歌。
荒かりし 波のまよひに 住吉の 神をばかけて 忘れやはする
光源氏 ⇒ 惟光 (返歌)
【現代語訳】
須磨で大嵐に遭った時に
祈った住吉の神の霊験をどうして忘られようか
みをつくし 恋ふるしるしに ここまでも めぐり逢ひける えには深しな
光源氏 ⇒ 明石の君 (贈歌)
【現代語訳】
身を尽くして恋いこがれていた印として、
ここで巡り合うことができるとは、
私たちの縁は深いのですね
※「澪標=水脈つ串」と「身を尽くし」をかけている。
「縁(えに)」と「江に」をかけている。
同じく住吉詣に来た明石の君と鉢合わせ、
源氏は和歌を贈った。
数ならで 難波のことも かひなきに などみをつくし 思ひそめけむ
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
人数にも入らない身の上で、全て諦めておりましたのに
どうして身を尽くしてまでお慕いすることになったのでしょう
露けさの 昔に似たる 旅衣 田蓑の島の 名には隠れず
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
涙に濡れる旅衣は、昔、須磨を流浪した時に似ているな
田蓑の島という名の蓑の名には身は隠れないので
※「雨により田蓑の島を今日行けど名には隠れぬものにぞありける」
(雨が降ったから、田蓑の島を今日歩いてみたが、
「蓑」というのは名ばかりで雨を防いでくれなかった)
(古今集雑上、九一八、貫之)を引歌としている。
降り乱れ ひまなき空に 亡き人の 天翔るらむ 宿ぞ悲しき
光源氏 ⇒ 斎宮<六条御息所の娘> (贈歌)
【現代語訳】
雪や霙が降り乱れている空を、亡き母宮の魂が
まだ家を離れられず天翔けっているだろうと悲しく思われます
※六条御息所の死去を悼む和歌。
六条御息所の執着心を心配している。
ほとんど技巧がないシンプルな和歌。
消えがてに ふるぞ悲しき かきくらし わが身それとも 思ほえぬ世に
斎宮<六条御息所の娘> ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
消えそうになく生きていますのが悲しいです
毎日涙に暮れてわ我が身が我が身とも思われない世の中に
※「ふる」は「降る」と「経る」をかけている。
「わが身それとも」には霙をおりこむ。
蓬生(6首)
絶ゆまじき 筋を頼みし 玉かづら 思ひのほかに かけ離れぬる
末摘花 ⇒ 侍従 (贈歌)
【現代語訳】
あなたとは絶えるはずのない間柄だと信頼していましたが
思いのほか遠くへ離れて行ってしまうのですね
※末摘花の叔母について九州へ行ってしまう女房との別れの歌。
別れの悲しみと、自分を捨てていく恨みとを表している。
玉かづら 絶えてもやまじ 行く道の 手向の神も かけて誓はむ
侍従 ⇒ 末摘花(返歌)
【現代語訳】
お別れしましてもあなたをお見捨て申しません
九州へ下っていく道中の道祖神に固くお誓いしましょう
亡き人を 恋ふる袂の ひまなきに 荒れたる軒の しづくさへ添ふ
末摘花(独詠歌)
【現代語訳】
亡き父を恋い慕って泣く涙で袂の乾く間もないのに
荒れた軒から雨水までが落ちて降りかかる
尋ねても 我こそ訪はめ 道もなく 深き蓬の もとの心を
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
自分から探してでも、私こそがあなたを訪問しましょう
道もないくらい深く生い茂った蓬の邸に住む姫君の変わらないお心を
藤波の うち過ぎがたく 見えつるは 松こそ宿の しるしなりけれ
光源氏 ⇒ 末摘花 (贈歌)
【現代語訳】
松にかかった藤の花を見過ごしがたく思ったのは
その松が私をずっと待っているあなたの家の目じるしだったからですね
※「松」に「待つ」がかかっている。
末摘花の貞淑な心を称える。
年を経て 待つしるしなき わが宿を 花のたよりに 過ぎぬばかりか
末摘花 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
長年待っていても甲斐のなかった私の邸を
あなたは藤の花を御覧になるついでに訪問しただけなのですね
関屋(3首)
行くと来と せき止めがたき 涙をや 絶えぬ清水と 人は見るらむ
空蝉(独詠歌)
【現代語訳】
行く人と来る人が入り混じる逢坂の関で、
せきとめがたく流れる私の涙を
絶えず流れる清水と人は見るでしょう
※「せき止めがたき」に「(逢坂の)関」をかけている。
空蝉と光源氏は逢坂の関で再会。
わくらばに 行き逢ふ道を 頼みしも なほかひなしや 潮ならぬ海
光源氏 ⇒ 空蝉 (贈歌)
【現代語訳】
偶然に逢坂の関で再会したことに期待を持っていましたが
それも甲斐がありませんね、やはり潮水でない淡水の海だから
※「逢ふ道」に「近江路」、
「甲斐」に「貝」をかける。
琵琶湖は海水ではなく淡水の海だから、
「海布松(見る目)」が生えていなくて
「貝(甲斐)」がないと嘆いている。
逢坂の 関やいかなる 関なれば しげき嘆きの 仲を分くらむ
空蝉 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
逢坂の関は、どのような関なのでしょうか
こんなにも深い嘆きを起こさせ、人と人の仲を引き裂くなんて
絵合(9首)
別れ路に 添へし小櫛を かことにて 遥けき仲と 神やいさめし
朱雀院 ⇒ 前斎宮<六条御息所の娘> (贈歌)
【現代語訳】
別れ際に櫛を差し上げましたが、それを口実に
あなたと離れ離れの関係になると神がお定めになったのでしょうか
※伊勢下向の折、朱雀帝は斎宮の額に小櫛をさし、
「京に帰らぬように」と言ったことを踏まえた和歌。
叶わぬ恋の恨みを含んでいる。
別るとて 遥かに言ひし 一言も かへりてものは 今ぞ悲しき
前斎宮<六条御息所の娘> ⇒ 朱雀院 (返歌)
【現代語訳】
別れの御櫛をいただいた時に院のおっしゃった一言が
帰京した今となっては悲しく思い出されます
※伊勢下向の際、朱雀帝は斎宮に「帰りたまふな」と言った。
斎宮の帰京は、御世交替または斎宮の親族に不幸があった場合。
斎宮は、朱雀帝の退位により帰京した。
一人ゐて 嘆きしよりは 海人の住む かたをかくてぞ 見るべかりける
紫の上 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
一人で都に残って嘆いているよりも、
海人が住んでいる浜辺を見て絵に描いていたほうがよかったわ
※「かた」は「絵」と「潟」の掛詞。
源氏が須磨で描いた美しい絵を見て詠んだ和歌。
憂きめ見し その折よりも 今日はまた 過ぎにしかたに かへる涙か
光源氏 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
辛かったあの頃よりも、今日はまた
再び昔を思い出していっそう涙が流れます
※「憂き目」と「浮海布(うきめ)」
「方」と「潟」、
「なみだ」と「波」をかけている。
伊勢の海の 深き心を たどらずて ふりにし跡と 波や消つべき
平典侍(唱和歌)
【現代語訳】
「伊勢物語」の深い心を訪ねず
古い物語だからといって価値を落としてよいものでしょうか
※平典侍は、
左方=梅壺女御(斎宮女御)の女房
平典侍が絵合の席で詠んだ和歌。
雲の上に 思ひのぼれる 心には 千尋の底も はるかにぞ見る
大弍の典侍(唱和歌)
【現代語訳】
宮中に上った「正三位」の心から見ると
「伊勢物語」の深い心も遥か下の方に見えます
※大弍の典侍は右方=弘徽殿女御の女房
「伊勢物語」を批判している。
「正三位」という物語は現在では散逸
しており、内容は不明。
みるめこそ うらふりぬらめ 年経にし 伊勢をの海人の 名をや沈めむ
藤壺の宮(唱和歌)
【現代語訳】
見た目には古くさく見えるでしょうけれど
昔から有名な「伊勢物語」の名を落とすことができましょうか
※「海松布(みるめ)」と「見る目」、
「浦古り」と「心(うら)古り」をかけている。
「海松布」「浦」「海人」「沈む」は縁語である。
藤壺の宮は、左方の「伊勢物語」を支持した。
身こそかく しめの外なれ そのかみの 心のうちを 忘れしもせず
朱雀院 ⇒ 斎宮女御 (贈歌)
【現代語訳】
我が身はこのように内裏の外におりますが
あの頃のあなたを思う気持ちは今でも忘れていません
※「そのかみ」に「神」をかけている。
「注連(しめ)」は「神」の縁語。
「注連の外」は帝を退位した現在、
内裏を離れて院の御所にいるという意味。
しめのうちは 昔にあらぬ 心地して 神代のことも 今ぞ恋しき
斎宮女御 ⇒ 朱雀院 (返歌)
【現代語訳】
内裏の中は昔と比べて変わってしまった気がして
斎宮として神にお仕えしていた頃が今は恋しく思われます
※朱雀院が「忘れしもせず」と詠んだのに対し
「今ぞ恋しき」と自分もあの頃と同じ気持ちだと
言っている。
松風(16首)
行く先を はるかに祈る 別れ路に 堪へぬは老いの 涙なりけり
明石の入道 (唱和歌)
【現代語訳】
姫君の将来の幸福を祈る別れに際して
堪えられないのは老人の涙だなあ
※明石の姫君と、上京する一行の
無事を祈る和歌。
入道は明石に残る。
もろともに 都は出で来 このたびや ひとり野中の 道に惑はむ
明石の尼君 (唱和歌)
【現代語訳】
あなたと一緒に都を出て来ましたが、今回の旅は
一人で都へ帰る野中の道で迷うことでしょう
※「この度」と「この旅」をかけている。
長年連れ添ってきた夫との別れを惜しむ和歌。
いきてまた あひ見むことを いつとてか 限りも知らぬ 世をば頼まむ
明石の君 (唱和歌)
【現代語訳】
京へ行って生きて再会できるのはいつでしょうか
どれだけ生きるとも分からない寿命を頼りにできましょうか
※「行き」と「生き」の掛詞。
生きて再会できる可能性の低い父との
別れを悲しむ和歌。
かの岸に 心寄りにし 海人舟の 背きし方に 漕ぎ帰るかな
明石の尼君 (唱和歌)
【現代語訳】
彼岸の極楽浄土に心を寄せていた尼の私が
一度は捨てた都に帰って行くことよ
※「かの岸」には「(明石の)岸」と
「彼岸」とをかけ、
「海人」と「尼」も掛詞となっている。
出家した身で都へ帰る感慨を詠んだ和歌。
いくかへり 行きかふ秋を 過ぐしつつ 浮木に乗りて われ帰るらむ
明石の君 (唱和歌)
【現代語訳】
何年もの秋を過ごして来た私は
頼りない舟に乗って都に帰って行くのでしょう
※「浮木」は水に浮かぶ木のことで、
上京した後の不安を表現している。
「浮」は「憂き」を連想させる。
身を変へて 一人帰れる 山里に 聞きしに似たる 松風ぞ吹く
明石の尼君 (唱和歌)
【現代語訳】
尼の姿となって一人で帰ってきた山里に
昔聞いたことがあるような松風が吹いている
故里に 見し世の友を 恋ひわびて さへづることを 誰れか分くらむ
明石の君 (唱和歌)
【現代語訳】
ふるさとである都で昔親しんだ人を慕って弾く
田舎くさい琴の音を誰が分かってくれましょうか
※「さへづる」は意味不明の方言のこと。
「こと」には「言」と「琴」をかけている。
「見し世の友」は幼少時代、都で親しんだ友のこと。
住み馴れし 人は帰りて たどれども 清水は宿の 主人顔なる
明石の尼君 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
かつて住み慣れていた私は帰って来て、昔のことを思い出そうとするが
遣水はこの家の主のように昔と変わらない音を立てています
いさらゐは はやくのことも 忘れじを もとの主人や 面変はりせる
光源氏 ⇒ 明石の尼君(返歌)
【現代語訳】
小さな遣水は昔のことも忘れないだろうが
家の主人のような顔をしているのは
主人であるあなたが出家して姿を変えてしまったからであろうか
契りしに 変はらぬ琴の 調べにて 絶えぬ心の ほどは知りきや
光源氏 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
約束したとおり、音色が変わらない琴の調べのような
心変わりしない私の気持ちをお分かりいただけましたか
※「琴」と「言」は」掛詞。
「琴」「絶えぬ」は縁語。
源氏は自分の誠実さをアピールしている。
変はらじと 契りしことを 頼みにて 松の響きに 音を添へしかな
明石の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
変わらないと約束なさったことを信じて
松風の音に泣き声を添えて待っていました
※「言」と「琴」、
「松」と「待つ」、
「ね」は「琴の音」と「泣く音」の
掛詞となっている。
月のすむ 川のをちなる 里なれば 桂の影は のどけかるらむ
冷泉帝 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
そちらは月が澄んで見える桂川の向こう側の里なので
月の光をゆっくりと眺められるでしょう
※「澄む」と「住む」をかけている。
光源氏の別邸「桂殿」の土地を称賛している。
久方の 光に近き 名のみして 朝夕霧も 晴れぬ山里
光源氏 ⇒ 冷泉帝(返歌)
【現代語訳】
桂の里といえば月に近いように思われますが
それは名ばかりであって、本当は朝霧も夕霧も晴れない山里です
※帝から桂殿を称賛されたのに対して、
「朝夕霧も晴れぬ山里」と謙遜している。
めぐり来て 手に取るばかり さやけきや 淡路の島の あはと見し月
光源氏 (唱和歌)
【現代語訳】
都に帰って来て手に取るくらい近くに見える月は
あの頃、淡路島の向こう遥か遠くに眺めた月と同じ月なのだろうか
浮雲に しばしまがひし 月影の すみはつる夜ぞ のどけかるべき
頭中将(唱和歌)
【現代語訳】
雲に少しの間隠れていた月の光も
今は澄みきっているように
あなた様もいつまでものどかに住むことでしょう
※「浮き」と「憂き」、
「澄み」と「住み」、
「夜」と「世」の掛詞。
源氏を「月影」に喩えている。
ここでの頭中将は、
左大臣家の頭中将とは
別人とするのが一般的な見方。
左大臣家の頭中将は、絵合巻で
中納言に昇進している。
雲の上の すみかを捨てて 夜半の月 いづれの谷に かげ隠しけむ
左大弁(唱和歌)
【現代語訳】
宮中を捨ててしまわれた故桐壺院は
どこの谷間にお姿をお隠してしまわれたのだろう
※左大弁は老人であり、
亡き桐壺院に親しくお仕えしていた。
薄雲(10首)
雪深み 深山の道は 晴れずとも なほ文かよへ 跡絶えずして
明石の君 ⇒ 乳母(贈歌)
【現代語訳】
雪が深いのでこの深い山里への道は通れなくなるでしょうが
どうか都からの手紙は、絶えないようにしてください
※「文」と「踏み」の掛詞。
「雪」と「晴」、
「踏み」と「跡」は縁語。
「乳母と姫君が二条院に移ってしまっても、
手紙だけは遣わしてください」の意。
雪間なき 吉野の山を 訪ねても 心のかよふ 跡絶えめやは
乳母 ⇒ 明石の君(返歌)
【現代語訳】
雪の消えることのない吉野の山奥であっても必ず訪ねて行き
心のこもった手紙を絶やすことは決してしません
末遠き 二葉の松に 引き別れ いつか木高き かげを見るべき
明石の君 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
幼い姫君にお別れして
いつになったら成長した姿を見ることができるのでしょう
※「二葉の松」は姫君を喩えている。
明石の君と幼い明石の姫君との別れ。
生ひそめし 根も深ければ 武隈の 松に小松の 千代をならべむ
光源氏 ⇒ 明石の君(返歌)
【現代語訳】
生まれてきた因縁も深いのだから
いつか一緒に暮らせるようになりましょう
※「武隈の松」は明石の君、
「小松の千代」は姫君を指す。
母子がいつか一緒に暮らせるようになると
慰めている。
舟とむる 遠方人の なくはこそ 明日帰り来む 夫と待ち見め
紫の上 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
あなたをお引き止めするあちらの方がいらっしゃらないのなら
あなたは明日帰ってくるだろうと思ってお待ちしますけれど
※「明日帰ると言っているけど、
明石の君にひきとめられて
きっと帰ってこないでしょう」の意。
行きて見て 明日もさね来む なかなかに 遠方人は 心置くとも
光源氏 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
ちょっと行って様子を見て明日にはすぐ帰ってくるよ
かえってあちらの方が不機嫌になろうとも
※「明石の君が機嫌を損ねようと
明日には紫の上のもとに戻ります」の意。
入り日さす 峰にたなびく 薄雲は もの思ふ袖に 色やまがへる
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
夕日がさしている峰の上にたなびいている薄雲は
悲しむ私の喪服の袖の色に似せたのだろうか
※藤壺の宮の崩御に際して
源氏が詠んだ哀悼の和歌。
君もさは あはれを交はせ 人知れず わが身にしむる 秋の夕風
光源氏 ⇒ 斎宮の女御(贈歌)
【現代語訳】
あなたも私の恋の情緒を分かってください、誰にも知られず
一人で身にしみて感じている秋の夕風ですから
※源氏は斎宮の女御に恋心をほのめかす。
斎宮の女御からは返歌は無い。
漁りせし 影忘られぬ 篝火は 身の浮舟や 慕ひ来にけむ
明石の君 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
明石の浦の漁り火が思い出されるこの篝火は
浮舟のような辛いわが身を追ってここまでついて来たのでしょうか
※「浮き」と「憂き」をかけている。
浅からぬ したの思ひを 知らねばや なほ篝火の 影は騒げる
光源氏 ⇒ 明石の君(返歌)
【現代語訳】
私の深い気持ちをわかっていただけていないから
今でもあなたの心は
篝火のようにゆらゆらと揺れ動いているのでしょう
※「思ひ」に「火」をかける。
朝顔(13首)
人知れず 神の許しを 待ちし間に ここらつれなき 世を過ぐすかな
光源氏 ⇒ 朝顔の君(贈歌)
【現代語訳】
誰にも知られず神の許しを待っていた間に
長年つらい日々を過ごしてきたことよ
※朝顔は父が亡くなったことにより
賀茂の斎院を辞した。
「神の許し」は朝顔が斎院であったことに
ちなんで言う。
なべて世の あはればかりを 問ふからに 誓ひしことと 神やいさめむ
朝顔の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
当たり障りのないご挨拶をするだけでも
誓ったことに反すると神がお咎めになるでしょう
見し折の つゆ忘られぬ 朝顔の 花の盛りは 過ぎやしぬらむ
光源氏 ⇒ 朝顔の君(贈歌)
【現代語訳】
昔拝見したあなたの姿がどうしても忘れられません
朝顔の花のようなあなたの容姿は盛りを過ぎてしまいましたか
※「見し」はかつて逢ったことがあるという意味。
「つゆ」は「露」と
「つゆ」(副詞:少しも)の掛詞。
「朝顔」は女の寝起きの顔を暗示する。
実際は、源氏と朝顔は逢瀬を遂げたことは
ないが、「容貌が衰えたのでは?」とからかって
相手の反応を見ている。
秋果てて 霧の籬に むすぼほれ あるかなきかに 移る朝顔
朝顔の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
秋が終わって霧の立ち込める垣根にしぼんで
今にも枯れてしまいそうな朝顔の花のような私です
※「あなたのおっしゃると通り
女の盛りを過ぎてひっそり生きています」の意。
いつのまに 蓬がもとと むすぼほれ 雪降る里と 荒れし垣根ぞ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
いつの間にこの邸には蓬が生い茂り
雪に埋もれたふる里になってしまったのか
垣根も荒れ果ててしまって…
※「降る」と「古る」をかける。
年経れど この契りこそ 忘られね 親の親とか 言ひし一言
源典侍 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
年月がたってもあなたとのご縁が忘れられません
親の親とかおっしゃった一言がございますもの
※「親の親と思はましかばとひてまし我が子の子にはあらぬなるべし」
(私を親の親と思うならば、当然訪ねただろうに、
ここに立ち寄らないあなたは、
きっと我が子の子ではないのであろう)
(拾遺集雑下、五四五、源重之の母)を踏まえた和歌。
「この契り」に「子の契り」をかけている。
「親の親」とは源典侍自身を指す。
身を変へて 後も待ち見よ この世にて 親を忘るる ためしありやと
光源氏 ⇒ 源典侍(返歌)
【現代語訳】
生まれ変わり来世まで待って見てください
この世で子が親を忘れる例があるかどうか
※「この世」と「子の世」の掛詞。
つれなさを 昔に懲りぬ 心こそ 人のつらきに 添へてつらけれ
光源氏 ⇒ 朝顔の君(贈歌)
【現代語訳】
昔のつれない態度に懲りもしない私の心までもが
あなたが辛いと思う心よりもっと辛く思われるのです
※源氏の執拗な恋心を表した和歌。
あらためて 何かは見えむ 人のうへに かかりと聞きし 心変はりを
朝顔の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
今になってどうして気持ちを変えたりしましょうか
他人ではそのようなことがあると聞いた心変わりを
※朝顔はあくまで源氏の恋を拒否する。
氷閉ぢ 石間の水は 行きなやみ 空澄む月の 影ぞ流るる
紫の上(独詠歌)
【現代語訳】
氷に閉じこめられた石間の遣水は流れが滞っているが
空に澄む月の光は滞りなく西へ流れて行く
※庭を眺めての叙景の和歌。
紫の上自身を石間の水、源氏を月影に喩え
源氏の浮気心に悩む気持を表現しているとの説もあり。
「行き」「生き」、「澄む」「住む」、
「流るる」「泣かるる」、「空」「嘘言」
の掛詞と捉えて、
「私は閉じこめられて、
どう生きていけばよいのか悩んでいます。
嘘ばかりつくあなたのお顔を見ると涙が流れます」
という解釈となる。
かきつめて 昔恋しき 雪もよに あはれを添ふる 鴛鴦の浮寝か
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
昔のさまざまなことが恋しく感じられる雪の夜に
いっそう情緒を添える鴛鴦の鳴き声であることよ
※「むかし恋しき」は藤壺の宮への思慕。
鴛鴦(おし)の浮寝は、
紫の上との夫婦関係のことを指すか。
紫の上も源氏も同じく雪の夜をテーマに
詠んでいるが、紫の上が孤独を歌ったのに対し
源氏は藤壺を追慕している。
2人の感情の齟齬に注目される。
とけて寝ぬ 寝覚さびしき 冬の夜に むすぼほれつる 夢の短さ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
安眠できずふと寝覚めた寂しい冬の夜に
見た夢は短かかったなあ
※源氏は夢の中で藤壺の宮と再会した。
夢から覚めてしまったことを惜しく思う気持ち。
亡き人を 慕ふ心に まかせても 影見ぬ三つの 瀬にや惑はむ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
亡くなった人を恋慕う心のままで訪ねていっても
その姿も見えない三途の川のほとりで迷ってしまうだろうか
※「亡き人」「影」は藤壺の宮を指す。
女は最初に契った男に背負われて
三途の川を渡るとされる。
藤壺の宮は桐壺院に背負われて
川を渡ったであろうから、その姿は見えない。
少女(16首)
かけきやは 川瀬の波も たちかへり 君が禊の 藤のやつれを
光源氏 ⇒ 朝顔の君(贈歌)
【現代語訳】
思いもかけませんでした
今日、禊の日が立ち帰り、あなたの藤色の衣(喪服)を見るとは
※朝顔は父親の喪が明け、禊を行った。
藤衣 着しは昨日と 思ふまに 今日は禊の 瀬にかはる世を
朝顔の君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
喪服を着たのはつい昨日のことと思っていましたのに
今日それを脱ぐ禊をするとは、世の中の移り変わりは早いものですね
さ夜中に 友呼びわたる 雁が音に うたて吹き添ふ 荻の上風
夕霧(独詠歌)
【現代語訳】
真夜中に友を呼びながら飛んでいく雁の鳴き声に
荻の上を吹く風が、さらに悲しく吹き加わることよ
※雲居雁との恋に悩む夕霧の独泳歌。
2人は引き裂かれることになった。
くれなゐの 涙に深き 袖の色を 浅緑にや 言ひしをるべき
夕霧 ⇒ 雲居雁(贈歌)
【現代語訳】
赤い血の涙を流してあなたを恋い慕っている私を
浅緑の袖の色だと言って蔑んでよいものでしょうか
※夕霧はこの時、六位だったので
周りから蔑まれていた。
いろいろに 身の憂きほどの 知らるるは いかに染めける 中の衣ぞ
雲居雁 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
色々と我が身の不幸が思い知らされるのは
どのような前世の因縁なのでしょうか
霜氷 うたてむすべる 明けぐれの 空かきくらし 降る涙かな
夕霧(独詠歌)
【現代語訳】
霜や氷が嫌なふうに張り詰めた明け方の
空を真っ暗にして降る涙の雨だな
天にます 豊岡姫の 宮人も わが心ざす しめを忘るな
夕霧 ⇒ 五節舞姫(贈歌)
【現代語訳】
あなたが天にいらっしゃる豊岡姫に仕える方であっても
私はあなたにしめ縄で「私のもの」と印をつけました
そのことを忘れないでくださいね
※「豊岡姫」は伊勢神宮 外宮の豊受大神のことか。
乙女子も 神さびぬらし 天つ袖 古き世の友 よはひ経ぬれば
光源氏 ⇒ 筑紫の五節(贈歌)
【現代語訳】
少女だったあなたも神さびたことでしょう
天の羽衣を着て舞った昔の友も年をとってしまったので
※源氏は、若い五節の舞姫を見て、
昔関係のあった筑紫の五節のことを思い出し、
懐かしい気持ちで和歌を贈った。
かけて言へば 今日のこととぞ 思ほゆる 日蔭の霜の 袖にとけしも
筑紫の五節 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
五節のことを言いますと、あの頃が今日のことのように思われます
日陰の葛を冠につけて舞い、霜がとけるようにあなたと契りを交わしたことが
日影にも しるかりけめや 少女子が 天の羽袖に かけし心は
夕霧 ⇒ 五節舞姫(贈歌)
【現代語訳】
日の光に照らされてはっきりおわかりになったでしょう
あなたが天の羽衣を着て舞う姿に恋をした私のことが
鴬の さへづる声は 昔にて 睦れし花の 蔭ぞ変はれる
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
鴬の鳴き声は昔のままですが
慣れ親しんだあの頃とは時勢が変わってしまいました
※「花宴」巻の桜花の宴を思い出し
桐壺帝⇒朱雀帝⇒冷泉帝へと
時勢が変わったことを感慨深く詠む。
九重を 霞隔つる すみかにも 春と告げくる 鴬の声
朱雀院(唱和歌)
【現代語訳】
宮中から離れた院の御所にも
春が来たと鴬の声が知らせにきます
いにしへを 吹き伝へたる 笛竹に さへづる鳥の 音さへ変はらぬ
兵部卿宮(唱和歌)
【現代語訳】
昔のままの音色をかなでる笛の音に
さらに鴬の鳴く声まで少しも変わっていません
※昔の徳の高い御代を引き継ぎ、
今もちっとも変っていないと今上帝を称える。
兵部卿宮は後の蛍兵部卿宮。
源氏と朱雀院の異母弟である。
鴬の 昔を恋ひて さへづるは 木伝ふ花の 色やあせたる
冷泉帝(唱和歌)
【現代語訳】
鴬が昔を恋い慕って木から木へ飛び移りながら
鳴いているのは
木の花が色あせているからでしょうか
※退位した朱雀院の寂しい気持ちをくんで、
自分の御代を卑下した和歌。
心から 春まつ園は わが宿の 紅葉を風の つてにだに見よ
秋好中宮 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
あなた様の大好きな春をお待ちのお庭では、
せめて私の庭の
紅葉を風のたよりにでも御覧ください
※春を好む紫の上に対して、
紅葉や秋の花を詰めた箱と一緒に
秋の素晴らしさを詠んだ和歌を贈った。
風に散る 紅葉は軽し 春の色を 岩根の松に かけてこそ見め
紫の上 ⇒ 秋好中宮(返歌)
【現代語訳】
風に散ってしまう紅葉は軽々しいものです
この岩にしっかりと根をはった
松の変わらない緑は春の色ですよ、御覧なさい
※箱の中に苔や岩を入れて文とともに贈り、
「秋よりも春が素晴らしい」と応酬する。
玉鬘(14首)
舟人も たれを恋ふとか 大島の うらがなしげに 声の聞こゆる
乳母の娘(姉)(唱和歌)
【現代語訳】
舟人は誰を恋い慕っているのでしょうか、大島の浦に
悲しい声が聞こえます
※都から筑紫へ下向する玉鬘と乳母の一行。
主人の夕顔を恋い慕った和歌。
来し方も 行方も知らぬ 沖に出でて あはれいづくに 君を恋ふらむ
乳母の娘(妹)(唱和歌)
【現代語訳】
来た方向もこれから進む方向も分からない沖に出て
ああどちらの方を向いてあなたを恋い慕ったらよいのでしょう
※亡き夕顔を恋い慕う和歌。
君にもし 心違はば 松浦なる 鏡の神を かけて誓はむ
大夫監 ⇒ 乳母(贈歌)
【現代語訳】
姫君のお心に違うようなことがあったら、どんな罰も受けると
松浦にまします鏡の神に誓いましょう
※粗野な田舎者の大夫監が玉鬘に求婚。
年を経て 祈る心の 違ひなば 鏡の神を つらしとや見む
乳母 ⇒ 大夫監(返歌)
【現代語訳】
長年祈ってきたことが叶わなかったなら
鏡の神を薄情な神様だとお思い申すことでしょう
※「年を経て祈る心」は
玉鬘と大夫監との結婚ではなく
玉鬘の上京のことを指す。
乳母は玉鬘を上京させ、幸せな結婚を
させたいと思っている。
浮島を 漕ぎ離れても 行く方や いづく泊りと 知らずもあるかな
兵部の君 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
浮き島のように思っていたこの地を舟で離れて行きますが
どこで落ち着けるとも分からない身の上ですこと
※兵部の君は女房の一人。
玉鬘と一緒に上京する。
行く先も 見えぬ波路に 舟出して 風にまかする 身こそ浮きたれ
玉鬘 ⇒ 兵部の君(返歌)
【現代語訳】
行く先もわからない波の道に舟を出して
風まかせの我が身の上こそ頼りないものです
※「浮き」には「憂き」をかけている。
憂きことに 胸のみ騒ぐ 響きには 響の灘も さはらざりけり
乳母(独詠歌)
【現代語訳】
辛い出来事に胸がどきどきしてばかりだったので
それに比べれば響の灘も名ばかりで大したことではなかったわ
※乳母は、求婚者である大夫監が
玉鬘一行の舟を追ってくるのではないかと
ハラハラしていた。
響の灘とは、現在の播磨灘。
二本の 杉のたちどを 尋ねずは 古川野辺に 君を見ましや
右近 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
二本の杉の立っているこの長谷寺に参詣しなかったら
古い川の近くで姫君に再会できたでしょうか
※「初瀬川古川の辺に二本ある杉年を経てまたもあひ見む二本ある杉」
(古今集雑体歌、旋頭歌、一〇〇九、読人しらず)
「初瀬川の古い川の畔にある二本杉。何年か後に逢おう、二本ある杉のところで」
を踏まえた和歌。
玉鬘は長谷寺にて、かつて母・夕顔の
女房をつとめていた右近と再会する。
初瀬川 はやくのことは 知らねども 今日の逢ふ瀬に 身さへ流れぬ
玉鬘 ⇒ 右近(返歌)
【現代語訳】
昔のことは知りませんが
今日あなたとお逢いできたことを嬉しく思う涙で
この体までが流れてしまいそうです
※「早く」に川の流れの速さと
時間の早い時期=「昔」の意味をかける。
「流れ」と「泣かれ」も掛詞。
「瀬」「流れ」は「川」の縁語。
知らずとも 尋ねて知らむ 三島江に 生ふる三稜の 筋は絶えじを
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
今はご存知なくとも聞けばおわかりになるでしょう
三島江に生えている三稜(みくり)のように私とあなたは縁が深いのですから
※「三島江」は歌枕である、
「三島江に生ふる三稜(みくり)の」は
「筋」を導く序詞。
源氏は玉鬘を六条院に迎え入れることを決意。
三稜は、多年草の三稜草のこと。沼沢地に生える。
数ならぬ 三稜や何の 筋なれば 憂きにしもかく 根をとどめけむ
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
数にも入らないこの身はどうして
この世に生まれて来たのでしょう
※源氏の贈歌の「三稜」「筋」の語句を
入れ込んで返している。
「三稜」に「身」、
「憂き」に「泥(うき)」をかける。
「三稜」と「泥」は縁語になっており
玉鬘の教養の高さがうかがえる。
恋ひわたる 身はそれなれど 玉かづら いかなる筋を 尋ね来つらむ
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
ずっと恋い慕っていた私は変わっていないが
姫君はどのような縁でここにたどり着いたのであろうか
※「いづくとて尋ね来つらむ玉かづら我は昔の我ならなくに」
(後撰集雑四、一二五三、源善朝臣)を踏まえる。
源善の和歌では「私は昔の私ではない」だが
源氏はそれと違って「昔も今も変わらず
夕顔を愛している」と主張している。
「玉」「筋」は縁語。
着てみれば 恨みられけり 唐衣 返しやりてむ 袖を濡らして
末摘花 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
着てみると恨めしく思われます、この唐衣は
お返しいたしましょう。涙で袖を濡らして
※着物の御礼として末摘花が詠んだ和歌。
源氏はこの和歌を、
『唐衣』、『袂濡るる』といった恨み言が
定型的で古臭いと酷評している。
返さむと 言ふにつけても 片敷の 夜の衣を 思ひこそやれ
光源氏 ⇒ 末摘花(返歌)
【現代語訳】
着物をお返ししましょうとおっしゃるにつけても
独りで夜を過ごすあなたをお察しいたします
※「いとせめて恋しき時はむばたまの夜の衣を返してぞ着る」
(古今集恋二、五五四、小野小町)を踏まえる。
平安時代には、衣を裏返して着て寝ると
好きな人の夢が見られるという俗信があった。
「着物を返す(返却する)」を
「着物を裏返す」の意味にすり替えた和歌。
初音(6首)
薄氷 解けぬる池の 鏡には 世に曇りなき 影ぞ並べる
光源氏 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
薄い氷の融けた池の鏡のような面には
世にも素晴らしい二人の姿が並んで映っています
※「鏡」に「鏡餅」を想像させる。
この時、鏡餅で新春のお祝いをしていた。
2人の幸福を称える和歌。
曇りなき 池の鏡に よろづ代を すむべき影ぞ しるく見えける
紫の上 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
少しも曇りのない池の鏡にこの先永く
住んで行く私たち2人の姿がはっきりと映っています
※「すむ」は「澄む」と「住む」の掛詞。
「曇り」「澄む」「影」は「鏡」の縁語。
年月を 松にひかれて 経る人に 今日鴬の 初音聞かせよ
明石の君 ⇒ 明石の姫君(贈歌)
【現代語訳】
長い年月、子どもの成長を待ち続けていた私に
今日はその初音を聞かせてください
※「松」と「待つ」
「古」と「経る」
「初音」と「初子」の掛詞となっている。
※この歌を詠んだ元日は、子の日であったので
「初子(はつね)」を詠みこんでいる。
正月にも実の娘に会えない明石の君は、
「せめて声が聞きたい」と和歌を詠んだ。
ひき別れ 年は経れども 鴬の 巣立ちし松の 根を忘れめや
明石の姫君 ⇒ 明石の君(返歌)
【現代語訳】
別れて何年もたちましたが
鶯が巣立った松を忘れないように
私も生みの母君を忘れましょうか
※「松」と「待つ」は掛詞。
実母に初めて返歌をした明石の姫君。
めづらしや 花のねぐらに 木づたひて 谷の古巣を 訪へる鴬
明石の君(独詠歌)
【現代語訳】
珍しいことだなあ、花の御殿から木を飛び移って
谷の古巣を訪れた鶯のように
我が娘が返歌をくれました
※「花のねぐら」は紫の上と姫君が住む春の御殿、
「谷の古巣」は明石の君が住む冬の御殿、
「鴬」は姫君を喩える。
実の娘から返歌が来たことを喜ぶ和歌。
ふるさとの 春の梢に 訪ね来て 世の常ならぬ 花を見るかな
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
二条東院の春 その木の枝を訪ねてみたら
世にも珍しい紅梅の花が咲いていたことよ
※「花」には「鼻」がかけてあり、
末摘花の赤い鼻を暗示している。
源氏は久々に二条東院の末摘花を訪問して、
昔と変わらず無風流な様子に懐かしさと嫌悪感を覚えた。
胡蝶(14首)
風吹けば 波の花さへ 色見えて こや名に立てる 山吹の崎
女房(唱和歌)
【現代語訳】
風が吹くと波の泡まで色を映して見えますが
これが有名な山吹の崎でしょうか
※「山吹の崎」は近江国にある歌枕。
春の町の船楽に参加した女房が
池の水に姿を映している山吹を称えて詠んだ和歌。
春の池や 井手の川瀬に かよふらむ 岸の山吹 そこも匂へり
女房(唱和歌)
【現代語訳】
春の御殿の池は井手の川瀬に通じているのでしょうか
岸の山吹が池の底にまで咲いていますね
※「井出」は山城国の山吹の名所。
亀の上の 山も尋ねじ 舟のうちに 老いせぬ名をば ここに残さむ
女房(唱和歌)
【現代語訳】
蓬莱山まで訪ねて行かなくても
この舟の中で不老の名を残しましょう
※「亀の上の山」は蓬莱山のこと。
不老不死の神薬を持つ仙人が住むと信じられていた。
春の町の中島を称える和歌。
春の日の うららにさして ゆく舟は 棹のしづくも 花ぞ散りける
女房(唱和歌)
【現代語訳】
春の日のうららかな光の中を漕いで行く舟は
棹から落ちるしずくも花となって散ります
※「さし」は「日が射し」と
「棹をさし」の掛詞。
紫の ゆゑに心を しめたれば 淵に身投げむ 名やは惜しけき
兵部卿宮 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
縁のある方に恋をしていますので
淵に身を投げても名誉は惜しくもありません
※酒宴の場で詠んだ和歌。
「紫のゆゑ」とは血縁があるという意味。
兵部卿宮は玉鬘が源氏の娘であり、
自分の姪だと思っている。
(実際は頭中将の娘)
淵に身を 投げつべしやと この春は 花のあたりを 立ち去らで見よ
光源氏 ⇒ 兵部卿宮(返歌)
【現代語訳】
淵に身を投げるだけの価値があるかどうか
この春の花の周辺を立ち去らずによく御覧ください
※酒宴の場で、源氏は兵部卿宮をひきとめる。
兵部卿宮は、のちの蛍兵部卿宮。
花園の 胡蝶をさへや 下草に 秋待つ虫は うとく見るらむ
紫の上 ⇒ 秋好中宮(贈歌)
【現代語訳】
花園の胡蝶までが下草に隠れて
秋を待っている松虫(秋好中宮)はつまらないと思うでしょうか
※「少女」の巻で
「心から春まつ園はわが宿の紅葉を風のつてにだに見よ」
と秋好中宮から贈られた和歌への返歌となっている。
「まつ」に「待つ」と「松虫」の「松」を掛けている。
胡蝶にも 誘はれなまし 心ありて 八重山吹を 隔てざりせば
秋好中宮 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
胡蝶にも誘われたいくらいでした
八重山吹の隔てがありませんでしたら
※「胡蝶」に「来てふ(来いという)」をかけている。
中宮という身分柄、簡単に春の町に行くことができない。
思ふとも 君は知らじな わきかへり 岩漏る水に 色し見えねば
柏木 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
こんなに恋い慕っていてもあなたはご存知ないのでしょうね
岩間から湧き上がる水には色がありませんから
ませのうちに 根深く植ゑし 竹の子の おのが世々にや 生ひわかるべき
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
邸の奥で大切に世話をしていた娘も
それぞれ結婚して邸を出て行ってしまうのか
※「ませ」は六条院、
「竹の子」は玉鬘を指す。
「世(男女の仲)」と「(竹の)節(よ)」の掛詞。
「節」は「竹」の縁語となっている。
今さらに いかならむ世か 若竹の 生ひ始めけむ 根をば尋ねむ
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
今さらどんな場合に私の
本当の父親を探したりするでしょうか
※「若竹」は自分を、「根」は実の父親を喩える。
源氏の和歌の「おのが世々に」を
実の父親のところへ行く意味にうけとって
このように返歌した。
橘の 薫りし袖に よそふれば 変はれる身とも 思ほえぬかな
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
懐かしい母君(夕顔)とあなたを比べてみると
とても別人とは思われません
※「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」
(古今集夏)を踏まえる。
「橘の薫りし袖」で昔の恋人=夕顔を指す。
「母・夕顔と玉鬘はよく似ている」の意。
袖の香を よそふるからに 橘の 身さへはかなく なりもこそすれ
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
懐かしい母君と似ていると思われますと
私の身までが母と同じように短命になってしまうかも知れません
※「身」と「(橘の)実」とをかける。
母・夕顔は「夕顔」巻で若くして亡くなっている。
うちとけて 寝も見ぬものを 若草の ことあり顔に むすぼほるらむ
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
心を開いて一緒に寝たわけでもないのに
どうしてあなたは何かあったような顔をして思い悩んでいるのですか
※「寝」と「根」は掛詞。
「根」は「若草」の縁語。
前夜、源氏は玉鬘の横で添い寝をした。
蛍(8首)
鳴く声も 聞こえぬ虫の 思ひだに 人の消つには 消ゆるものかは
蛍兵部卿宮 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
鳴く声も聞こえない蛍の火のような私の恋は、
人が消そうとして消えるものでしょうか
※蛍の光に照らされた玉鬘の
美しい姿を見てしまった蛍兵部卿宮。
「思ひ」には「火」をかけ、
簡単には消えない恋心を訴える。
声はせで 身をのみ焦がす 蛍こそ 言ふよりまさる 思ひなるらめ
玉鬘 ⇒ 蛍兵部卿宮(返歌)
【現代語訳】
声には出さずひたすら身を焦がしている蛍の方が
あなたのように言葉にするよりもっと深い思いなのでしょう
今日さへや 引く人もなき 水隠れに 生ふる菖蒲の 根のみ泣かれむ
蛍兵部卿宮 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
今日でさえ引く人もない水中に隠れて生えている菖蒲の根のように
あなたに相手にされない私は声を上げて泣くだけでしょうか
※「根」と「音」、「流れ」と「泣かれ」の掛詞。
この日は五月五日。端午の節句にちなんで
菖蒲を詠みこんでいる。
あらはれて いとど浅くも 見ゆるかな 菖蒲もわかず 泣かれける根の
玉鬘 ⇒ 蛍兵部卿宮(返歌)
【現代語訳】
菖蒲の根を引き抜いてきれいに洗ったように
はっきりと見せていただきましてますます浅く見えました
わけもなく涙が出るとおっしゃるあなたのお心が
※「洗はれて」と「現れて」
「文目」と「菖蒲」
「泣かれ」と「流れ」
「音」と「根」の掛詞。
その駒も すさめぬ草と 名に立てる 汀の菖蒲 今日や引きつる
花散里 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
馬も食べない草として有名な水際の菖蒲(あやめ)のような私を
端午の節句である今日、引き立てて下さったのですか
※「駒もすさめぬ」は、源氏に
女として愛されていないことを言う。
この日は夏の町の馬場殿で騎射が行われた。
鳰鳥に 影をならぶる 若駒は いつか菖蒲に 引き別るべき
光源氏 ⇒ 花散里(返歌)
【現代語訳】
鳰鳥(におどり)のようにいつもあなたと一緒にいる若駒の私は
いつ菖蒲のあなたと別れたりしましょうか
※「若駒」は源氏自身、
「菖蒲」は花散里を喩える。
仲のよい鳰鳥に、二人の仲を喩えている。
思ひあまり 昔の跡を 訪ぬれど 親に背ける 子ぞたぐひなき
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
思いあまって昔の本を探してみましたけど
親に背いた子どもの例は見つかりませんでした
古き跡を 訪ぬれどげに なかりけり この世にかかる 親の心は
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
昔の本を読んでみましたが、確かに見つかりませんでした。
この世にこのような親心の人は
※玉鬘は源氏に恋心をほのめかされたことを
うっとうしく感じている。
常夏(4首)
撫子の とこなつかしき 色を見ば もとの垣根を 人や尋ねむ
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
撫子の花のようにいつ見ても美しいあなたを見たら
母親のことを内大臣はたずねられることだろう
※「とこなつかし(常に心が惹かれる」と
「常夏(撫子の別名)」をかけている。
内大臣は、前の頭中将。玉鬘の実父。
山賤の 垣ほに生ひし 撫子の もとの根ざしを 誰れか尋ねむ
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
山の貧しい垣根に生えた撫子のような私の
母親など誰がたずねるでしょうか
※自分を数にも入らない者だと謙遜している。
草若み 常陸の浦の いかが崎 いかであひ見む 田子の浦波
近江の君 ⇒ 弘徽殿女御(贈歌)
【現代語訳】
未熟者ですが、いかがでしょうか
どうにかあなた様にお会いしとうございます
※「草若み」は自分を卑下しているつもりか。
「いかが崎」(河内)、「田子の浦」(駿河)
「常陸の浦」と関係のない3箇所の地名を
詠みこんだ本末あはぬ歌
(上下のつじつまが合わない歌)である。
常陸なる 駿河の海の 須磨の浦に 波立ち出でよ 筥崎の松
弘徽殿女御(代筆:中納言) ⇒ 近江の君(返歌)
【現代語訳】
常陸にある駿河の海の須磨の浦に
お出かけなさい、箱崎の松が待っていますよ
※女房の中納言が女御の代わりに詠んだ和歌。
「松」と「待つ」をかけている。
「待っていますよ」という意味。
篝火(2首)
篝火に たちそふ恋の 煙こそ 世には絶えせぬ 炎なりけれ
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
篝火に沿うように立ち上る恋の煙こそ
永遠に消えることのない私の思いの炎なのです
※「恋」に「火」を連想させる。
行方なき 空に消ちてよ 篝火の たよりにたぐふ 煙とならば
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
果てしない空に消して下さい、あなたの恋が
篝火と一緒に立ち上る煙とおっしゃるならば
野分(4首)
おほかたに 荻の葉過ぐる 風の音も 憂き身ひとつに しむ心地して
明石の君(独詠歌)
【現代語訳】
いつものように荻の葉の上を吹き過ぎて行く風の音も
辛い我が身だけには染み入るような気分がして
※野分の見舞だけを言って
すぐ帰っていく源氏を恨めしく思って詠んだ和歌。
吹き乱る 風のけしきに 女郎花 しをれしぬべき 心地こそすれ
玉鬘 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
吹き乱れる風のせいで女郎花は
しおれてしまいそうな気持ちがいたします
※「吹き乱る風」とは源氏の玉鬘に対する執着のこと。
「女郎花」は玉鬘の比喩。
下露に なびかましかば 女郎花 荒き風には しをれざらまし
光源氏 ⇒ 玉鬘(返歌)
【現代語訳】
下葉の露になびいたならば
女郎花は強い風にはしおれないでしょう
※「私の気持ちに応えていれば、
あなたは結婚問題で辛い思いをせずにすむのに」の意。
風騒ぎ むら雲まがふ 夕べにも 忘るる間なく 忘られぬ君
夕霧 ⇒ 雲居雁(贈歌)
【現代語訳】
風が騒いで羊雲が乱れる夕方にも
少しの間も忘れることのできないあなたよ
行幸(9首)
雪深き 小塩山に たつ雉の 古き跡をも 今日は尋ねよ
冷泉帝 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
雪深い小塩山に降り立つ雉のように
昔の例に従って今日の行幸にいらっしゃればよかったのに
※帝は、源氏が物忌みで行幸に
参加しなかったことを残念がっている。
昔の例とは、仁和二年(886年)12月14日
光孝天皇の芹川行幸に太政大臣藤原基経が供奉した例をいうか。
小塩山 深雪積もれる 松原に 今日ばかりなる 跡やなからむ
光源氏 ⇒ 冷泉帝(返歌)
【現代語訳】
小塩山に深雪が積もった松原に
行幸の先例は多くありますが
今日ほどの盛儀はかつてなかったことでしょう
※「みゆき」に「深雪」と「行幸」をかけている。
うちきらし 朝ぐもりせし 行幸には さやかに空の 光やは見し
玉鬘 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
雪が散らついて曇った朝の行幸では
はっきりと日の光(帝)は見えませんでした
※「空の光」は冷泉帝の比喩。
宮仕えを勧める源氏への和歌。
あかねさす 光は空に 曇らぬを などて行幸に 目をきらしけむ
光源氏 ⇒ 玉鬘(返歌)
【現代語訳】
日の光は曇りなく輝いていましたのに
どうして行幸の日に、ちらつく雪で目を曇らせていたのですか
※「あかねさす」は「光」の枕詞。
「みゆき」に「行幸」と「み雪」を掛けている。
ふたかたに 言ひもてゆけば 玉櫛笥 わが身はなれぬ 懸子なりけり
大宮 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
源氏の君と内大臣、どちらの方から言っても
あなたは私にとって離れられない孫に当たる方なのですね
※「玉櫛笥」は歌語。
「懸子」に「子」を、「二方」に「蓋」を掛ける。
「身」「懸子」は「玉櫛笥」の縁語。
大宮にとって内大臣は実子、源氏は娘婿。
玉鬘は内大臣の実の娘であり、源氏の養女である。
わが身こそ 恨みられけれ 唐衣 君が袂に 馴れずと思へば
末摘花 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
私自身こそが恨めしく思われます
あなたのおそばにいることができないと思いますと
※玉鬘の裳着のお祝いに詠んだ和歌だが、
恋人を恨む内容となっており、場違いである。
唐衣 また唐衣 唐衣 かへすがへすも 唐衣なる
光源氏 ⇒ 末摘花(返歌)
【現代語訳】
唐衣、また唐衣、唐衣
あなたはいつもいつも唐衣とおっしゃる
※「唐衣」と「返す」は縁語。
末摘花がよく「唐衣」を詠みこんだ
古臭い和歌を詠むことをからかっている。
恨めしや 沖つ玉藻を かづくまで 磯がくれける 海人の心よ
内大臣 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
恨めしいことです、玉裳を着る今日まで
隠れていた人の心が
※「浦」「恨」、「藻」「裳」、
「潜く」「被く」の掛詞。
玉鬘を「海人」に見たてて、
今まで娘であることを名乗り出なかった
不満を表明する和歌。
よるべなみ かかる渚に うち寄せて 海人も尋ねぬ 藻屑とぞ見し
光源氏 ⇒ 内大臣(返歌)
【現代語訳】
頼る人がいないから、このような私の所に身を寄せて
誰にも訪ねてきてもらえない子だと思っていました
※「寄る辺無み」「寄るべ波」の掛詞。
「藻屑」に「裳」を連想させる。
内大臣を「海人」に、玉鬘を「藻屑」に
源氏は「渚」に喩えている。
藤袴(8首)
同じ野の 露にやつるる 藤袴 あはれはかけよ かことばかりも
夕霧 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
あなたと同じ野の露に濡れて
しおれている藤袴のような私に
優しい言葉をかけて下さい、ほんの少しでも
※夕霧は玉鬘に恋心をほのめかす。
「藤袴」は喪服(大宮の喪)を指すと同時に
藤-薄紫(ゆかりの色)を指し、
いとこ同士の交流をしましょうと訴えている。
尋ぬるに はるけき野辺の 露ならば 薄紫や かことならまし
玉鬘 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
たずねてみて遥か遠い野辺の露だったならば
薄紫のご縁があるとは言い訳でしょう
※「実際には2人は無関係です」と
突っぱねている。
妹背山 深き道をば 尋ねずて 緒絶の橋に 踏み迷ひける
柏木 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
実の姉弟であるとは知らずに
叶わない恋の道に迷い文を贈ったことです
※「妹背山」は大和の歌枕であり、
2人が「姉弟」である意を含ませる。
「緒絶の橋」は陸奥の歌枕であり、
「絶」に叶えがたい恋の意をこめた。
「踏み」に「文」を掛ける。
惑ひける 道をば知らず 妹背山 たどたどしくぞ 誰も踏み見し
玉鬘 ⇒ 柏木(返歌)
【現代語訳】
あなたが私を思っていたとは知りませんでした
どうしてよいか分からず手紙を拝見していました
数ならば 厭ひもせまし 長月に 命をかくる ほどぞはかなき
髭黒大将 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
人並みの者であったら嫌ってしまうだろうに、九月に
望みをかけているとは、何とはかない身の上であろう
※9月は帝への出仕や結婚を忌む月なので、
玉鬘の宮仕えは10月からだと髭黒は知っている。
9月が最後のチャンスだと期待している。
朝日さす 光を見ても 玉笹の 葉分けの霜を 消たずもあらなむ
蛍兵部卿宮 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
帝の御寵愛を受けたとしても
霜のようにはかない私のことを忘れないでください
※「朝日さす光」を帝の寵愛に、
「玉笹」を玉鬘に、「霜」を自分自身に喩える。
情熱的な髭黒とは対照的に、諦めモードである。
忘れなむと 思ふもものの 悲しきを いかさまにして いかさまにせむ
左兵衛督 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
忘れようと思うけれどそれがまた悲しいのを
どのようにしてどのようにしたらよいでしょうか
※左兵衛督は紫の上の異母兄弟。
求婚者の一人。
心もて 光に向かふ 葵だに 朝おく霜を おのれやは消つ
玉鬘 ⇒ 蛍兵部卿宮(返歌)
【現代語訳】
自分から光に向かう葵でさえ
朝おいた霜を自分から消すでしょうか
※自分を「葵」に、蛍兵部卿宮を「霜」に喩えている。
真木柱(21首)
おりたちて 汲みは見ねども 渡り川 人の瀬とはた 契らざりしを
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
あなたと深い関係はありませんでしたが、三途の川を渡る時
他の男に背負われて渡るようには約束しなかったのに
※「汲み」「瀬」は「川」の縁語。
「せ」は「瀬」と「背」との掛詞である。
女は死後に初めて契った男に背負われて
三途の川を渡るという俗信に基づいた和歌。
玉鬘は髭黒大将と結婚した。
みつせ川 渡らぬさきに いかでなほ 涙の澪の 泡と消えなむ
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
三途の川を渡る前に何とかしてやはり
涙の川に浮かぶ泡のように消えてしまいたい
心さへ 空に乱れし 雪もよに ひとり冴えつる 片敷の袖
髭黒大将 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
心までが空に思い乱れましたこの雪に
一人で冷たい片袖を敷いて寝ました
※昨夜、玉鬘のもとに通えなかったことを
弁解する和歌。
ひとりゐて 焦がるる胸の 苦しきに 思ひあまれる 炎とぞ見し
木工の君 ⇒ 髭黒大将(贈歌)
【現代語訳】
北の方が一人でとり残されて、思い焦がれる胸の苦しさが
思い余って炎となったのを拝見しました
※木工の君は女房。
「ひとり」に「独り」と「火取り」を掛ける。
憂きことを 思ひ騒げば さまざまに くゆる煙ぞ いとど立ちそふ
髭黒大将 ⇒ 木工の君(返歌)
【現代語訳】
嫌なことを思って心が騒ぐので、あれこれと
後悔の炎がますます燃え立つのだ
※「思ひ」の「ひ」に「火」をかけ、
「くゆる」に「燻る」と「悔ゆる」をかけている。
「燻る煙」は「火」の縁語。
今はとて 宿かれぬとも 馴れ来つる 真木の柱は われを忘るな
真木柱 ⇒ 北の方(贈歌)
【現代語訳】
今はもうこの家を出て行きますが、私が慣れ親しんだ
この真木の柱は私を忘れないでください
※この和歌が姫君の呼称となり、
巻名にもなっている。
馴れきとは 思ひ出づとも 何により 立ちとまるべき 真木の柱ぞ
北の方 ⇒ 真木柱(返歌)
【現代語訳】
馴れ親しんで来た真木柱だと思い出しても
どうしてこの邸にとどまっていられましょうか
浅けれど 石間の水は 澄み果てて 宿もる君や かけ離るべき
中将の君 ⇒ 木工の君(贈歌)
【現代語訳】
浅い関係のあなたが残って、
邸を守るはずの北の方様が邸を離れて行くことが
あってよいものでしょうか
※「石間の水」に木工の君を喩え、
「宿守る君」は北の方を指している。
「すみ」に「住み」と「澄み」をかけている。
「かけ」に「かけ離る」と水に映る「影」とを響かせる。
中将の君(女房)は北の方とともに出て行き、
木工の君(女房)は髭黒について邸に残る。
ともかくも 岩間の水の 結ぼほれ かけとむべくも 思ほえぬ世を
木工の君 ⇒ 中将の君(返歌)
【現代語訳】
何を言われても、私の心は悲しみに閉ざされて
いつまでここに居られるかもわかりません
※「言はま」に「岩間」を掛ける。
「結ぼほれ」は、水の流れが滞る意と
気持ちが鬱々として塞いでいる意をこめる。
深山木に 羽うち交はし ゐる鳥の またなくねたき 春にもあるかな
蛍兵部卿宮 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
深山木と親しくしている鳥が
これ以上なく妬ましく思われる春だなあ
※鬚黒を「深山木」(無風流な木の譬え)
に見立て、玉鬘を「鳥」に見立てる。
「またなくねたき」には
「またなく妬き」に「また鳴く音」「また泣く声」を掛ける。
「髭黒と玉鬘が夫婦になったことが妬ましい」の意。
などてかく 灰あひがたき 紫を 心に深く 思ひそめけむ
冷泉帝 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
どうしてこのように一緒になりがたいあなたを
深く思ってしまったのでしょう
※「紫」は三位の服の色。
帝は玉鬘を三位に叙したので、紫を詠みこんだ。
紫は椿の灰を混ぜて染料を作るため、
「灰」が詠みこまれている。
「灰合ひ」に「逢ひ」を掛ける。
「深く」「染め」は「紫」の縁語。
いかならむ 色とも知らぬ 紫を 心してこそ 人は染めけれ
玉鬘 ⇒ 冷泉帝(返歌)
【現代語訳】
どのようなお気持ちでいらっしゃるのか存じませんでした
この紫の色(三位)は深い御心から下さったものなのですね
九重に 霞隔てば 梅の花 ただ香ばかりも 匂ひ来じとや
冷泉帝 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
幾重にも霞に隔てられてしまったなら、
梅の花の香りは
宮中まで匂って来ないのだろうか
※「霞」は髭黒の比喩。
「梅の花」は玉鬘を喩える。
「九重」は宮中の意と幾重にもの意を掛ける。
源氏、内大臣の世話役の者や
大将たちが玉鬘の監視をしていることを嘆く。
香ばかりは 風にもつてよ 花の枝に 立ち並ぶべき 匂ひなくとも
玉鬘 ⇒ 冷泉帝(返歌)
【現代語訳】
香りだけは風にご伝言をください
美しい花の枝に並べるような私ではありませんが
※「花の枝」は後宮の妃たちの比喩。
かきたれて のどけきころの 春雨に ふるさと人を いかに偲ぶや
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
穏やかな雨が降る春雨のころ
昔慣れ親しんだ私をどう思っていらっしゃいますか
※「ふる」は「春雨に降る」と
「古る里人」との掛詞。
眺めする 軒の雫に 袖ぬれて うたかた人を 偲ばざらめや
玉鬘 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
物思いに耽りながら
軒からしたたる雨の雫に袖を濡らして
どうしてあなたのことを思わないでいられましょうか
※「うたかた人」は源氏のこと。
「ながめ」は「長雨」と「眺め」をかけている。
「うたかた」は「泡沫(うたかた)」の意と
かりそめの意をかける。
「雫」「濡れ」「泡沫」は縁語。
思はずに 井手の中道 隔つとも 言はでぞ恋ふる 山吹の花
光源氏(独詠歌)
【現代語訳】
思いがけずに二人の仲は隔てられてしまいましたが
心の中では恋い慕っていますよ
※玉鬘への諦めきれない恋心を訴えた和歌。
六条院の庭には、山吹が美しく咲いていた。
「井手の中道」は山吹の名所の井手へ通じる道のこと。
同じ巣に かへりしかひの 見えぬかな いかなる人か 手ににぎるらむ
光源氏 ⇒ 玉鬘(贈歌)
【現代語訳】
せっかく私の所でかえった雛が見えませんね
どんな人が手に握っていますか
※「かひ」には「卵(かひ)」と「甲斐」をかける。
鬚黒が玉鬘と結婚したことを恨む和歌。
巣隠れて 数にもあらぬ かりの子を いづ方にかは 取り隠すべき
髭黒大将 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
私の巣に隠れて、
あなたにとては子どもの数にも入らない雁の子を
どちらの方に隠すとおっしゃるのでしょうか
※「かりの子」に「雁の子」と「仮の子」、
「とり」に「鳥」と「取り」を掛ける。
玉鬘の代わりに髭黒が返歌をした。
沖つ舟 よるべ波路に 漂はば 棹さし寄らむ 泊り教へよ
近江の君 ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
沖の舟よ、寄る岸がなくて波に漂っているなら
私が棹さして近づいていきますので、行き先を教えてください
※「沖つ舟」に夕霧を喩える。
「なみ」は「寄る辺なみ」(寄る辺がないので)と
「波路」をかけている。
「漂はば」は夕霧と雲居雁との結婚が決まらないことを言う。
「棹さし寄らむ」は「私の方から近寄って行こう」の意。
夕霧に不躾なたわむれを仕掛けた和歌。
よるべなみ 風の騒がす 舟人も 思はぬ方に 磯伝ひせず
夕霧 ⇒ 近江の君(贈歌)
【現代語訳】
寄る所がなく風にもてあそばれている舟人でも
思ってもいない海岸を沿ったりはしません。
※「舟人」は夕霧自身を指す。
「思はぬ方」は近江の君の比喩。
梅枝(11首)
花の香は 散りにし枝に とまらねど うつらむ袖に 浅くしまめや
朝顔の君 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
花の香りは散ってしまった枝には残りませんが、
香を焚きしめた袖には深く香ることでしょう
※「散りにし枝」は朝顔自身を、
「うつらむ袖」は明石の姫君を喩える。
自分を卑下して、明石の姫君の若さを称賛する和歌。
薫物合わせにて、お香と一緒に贈られた。
花の枝に いとど心を しむるかな 人のとがめむ 香をばつつめど
光源氏 ⇒ 朝顔の君(返歌)
【現代語訳】
花の枝にますます心を惹かれることだなあ
他人に批判されるだろうと隠しているけれど
※「花の枝」は朝顔を喩えている。
「気持ちを隠しているけれど、あなたに
ますます魅力を感じます」の意。
鴬の 声にやいとど あくがれむ 心しめつる 花のあたりに
蛍兵部卿宮(唱和歌)
【現代語訳】
鴬のさえずりにますます魂が抜け出しそうです
心が惹かれた梅の花の咲く場所では
※薫物合わせ後の饗宴で詠まれた和歌。
色も香も うつるばかりに この春は 花咲く宿を かれずもあらなむ
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
色も香りも染みついてしまうほどに、今年の春は
梅の花の咲く私の邸を絶えず訪れて下さいよ
鴬の ねぐらの枝も なびくまで なほ吹きとほせ 夜半の笛竹
柏木(唱和歌)
【現代語訳】
鴬の巣のある枝もたわむほど
夜通し笛の音を吹き続けて下さい
※夕霧の横笛の技量を称賛する和歌。
心ありて 風の避くめる 花の木に とりあへぬまで 吹きや寄るべき
夕霧(唱和歌)
【現代語訳】
気をづかって風が避けて吹くらしい梅の花の木に
考えなしに近づいて笛を吹いていいものでしょうか
※「取りあへぬ」に「鳥」(鴬)を掛ける。
「吹き」に「風が吹く」と「笛を吹く」の意を掛ける。
霞だに 月と花とを 隔てずは ねぐらの鳥も ほころびなまし
弁少将(唱和歌)
【現代語訳】
霞さえ月と花とを隔てなければ
ねぐらに帰る鳥も、月の光を昼間と勘違いして、鳴き出すでしょう
花の香を えならぬ袖に うつしもて ことあやまりと 妹やとがめむ
蛍兵部卿宮 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
この梅の花の香りを、
いただいた衣装の素晴らしい袖に移して帰ったら
浮気をしたのではないかと妻が咎めるでしょう
※「妹」とは妻のこと。
めづらしと 故里人も 待ちぞ見む 花の錦を 着て帰る君
光源氏 ⇒ 蛍兵部卿宮(返歌)
【現代語訳】
家で待っているあなたの奥様も
珍しいことだと思って見るでしょう
この花の錦を着て帰るあなたを
つれなさは 憂き世の常に なりゆくを 忘れぬ人や 人にことなる
夕霧 ⇒ 雲居雁(贈歌)
【現代語訳】
あなたの冷たい態度は、
つらいこの世で当然のこととなって行きますが
それでもあなたのことを忘れない私は普通の人と違っているのでしょうか
限りとて 忘れがたきを 忘るるも こや世になびく 心なるらむ
雲居雁 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
もうこれが最後だと、忘れられないという私のことを忘れるのは
あなたの心もこの世の普通の人の心なのでしょう
※「世になびく」は夕霧に別の人との
縁談がきていることを言う。
藤裏葉(20首)
わが宿の 藤の色濃き たそかれに 尋ねやは来ぬ 春の名残を
内大臣<頭中将> ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
私の邸の藤の花の色が濃い夕暮れ時に
訪ねていらっしゃいませんか、いく春の名残を惜しみましょう
※内大臣は夕霧を自邸に招待し、
雲居雁との結婚を許可しようと思っている。
なかなかに 折りやまどはむ 藤の花 たそかれ時の たどたどしくは
夕霧 ⇒ 内大臣<頭中将>(返歌)
【現代語訳】
かえって藤の花を折るのに戸惑うのではないでしょうか
夕暮れ時の視界がはっきりしない時刻では
※「花を折る」は「結婚する」の意味を暗示している。
「本当にお伺いしてよろしいですか」という意味の和歌。
紫に かことはかけむ 藤の花 まつより過ぎて うれたけれども
内大臣<頭中将> (唱和歌)
【現代語訳】
紫色のせいにしましょう、藤の花が
松の木を越えるほど長く待つことになるとは恨めしいけれど
※「紫」は雲居雁を指す。
「夕霧を婿にすることを
長く待たされたことが恨めしいが雲居雁のせいにしよう」
という意味。
いく返り 露けき春を 過ぐし来て 花の紐解く 折にあふらむ
夕霧 (唱和歌)
【現代語訳】
何度も涙に濡れる春を過ごして来ましたが
今日になって花の開くお許しをいただくことができました
※長年望んできた結婚が許された喜びを表す和歌。
たをやめの 袖にまがへる 藤の花 見る人からや 色もまさらむ
柏木 (唱和歌)
【現代語訳】
若い女性の袖に見間違えるような藤の花は
見る人が立派なためかより一層美しさが増すことでしょう
※「藤の花」は雲居雁、
「見る人」は夕霧を喩える。
浅き名を 言ひ流しける 河口は いかが漏らしし 関の荒垣
雲居雁 ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
軽々しい浮名を流したあなたの口は
どうして他人にお漏らしになったのですか
※この直前に夕霧は「河口の」と発言している。
元歌は催馬楽。
「河口の 関の荒垣や 関の荒垣や 守れども はれ 守れども 出でて我寝ぬや 出でて我寝ぬや 関の荒垣」
親に厳しく監視されていた女が、
抜け出して男と共寝をしてしまったという歌。
弁の少将が催馬楽の「葦垣」を歌い、
「姫を盗み出そうとしている」と言ったので
夕霧は「河口の」と口ずさむことで
「私と雲居雁はとっくの昔に自らの意志で寝た」
と反論しようとしたのだ。
雲居雁は催馬楽の「河口」を引歌として
この和歌を詠んだ。
漏りにける 岫田の関を 河口の 浅きにのみは おほせざらなむ
夕霧 ⇒ 雲居雁(返歌)
【現代語訳】
浮名が漏れたのはあなたの父親のせいでもあるのに
私のせいばかりになさらないで下さい
※「守り」と「漏り」をかけている。
とがむなよ 忍びにしぼる 手もたゆみ 今日あらはるる 袖のしづくを
夕霧 ⇒ 雲居雁(贈歌)
【現代語訳】
批判しないでください、人目を避けて絞る手の力もなく
今日は他人に隠せそうもない袖の涙のしずくを
※後朝の文に書かれていた和歌。
「今日からは誰にも遠慮しません」という意が含まれる。
何とかや 今日のかざしよ かつ見つつ おぼめくまでも なりにけるかな
夕霧 ⇒ 藤典侍(贈歌)
【現代語訳】
何といったでしょうか、今日のこの插頭の名を、
目の前に見ていながら思い出せないくらい
あなたに逢わないでいたことよ
※藤典侍は夕霧の愛人。
かざしても かつたどらるる 草の名は 桂を折りし 人や知るらむ
藤典侍 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
頭にかざしてもはっきりと思い出せない草の名を
試験に合格しているあなたはご存知でしょう
※「桂を折る」は官吏登用試験に合格すること。
夕霧は試験に合格している。
浅緑 若葉の菊を 露にても 濃き紫の 色とかけきや
夕霧 ⇒ 大輔の乳母(贈歌)
【現代語訳】
浅緑色をした若葉の菊が
濃い紫の花が咲こうとは全く思っていなかったでしょう
※「浅緑」は六位の袍の色。
「濃き紫の色」は中納言三位の袍の色。
「私が三位に出世するとは思わなかったでしょう」の意。
大輔の乳母は雲居雁の乳母で、
昔、六位の夕霧との結婚に不満を言っていた。
双葉より 名立たる園の 菊なれば 浅き色わく 露もなかりき
大輔の乳母 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
幼い二葉の頃から名門の園に育つ菊ですから
浅い色をだと差別する者は誰もいませんでした
※「夕霧は名門の家の出だから、
六位でも蔑視する人はいませんでした」の意。
なれこそは 岩守るあるじ 見し人の 行方は知るや 宿の真清水
夕霧(唱和歌)
【現代語訳】
おまえこそはこの邸を守っている主人だよ
昔、お世話になった人の行方は知っているか、邸の真清水よ
※真清水に呼びかけた和歌。
「見し人」は亡き大宮。
亡き人の 影だに見えず つれなくて 心をやれる いさらゐの水
雲居雁(唱和歌)
【現代語訳】
亡き人の姿さえ映さず冷淡な表情で
気持ちよさそうに流れている浅い清水ね
※二人を育ててくれた祖母・大宮を思い、
感傷にひたる和歌。
そのかみの 老木はむべも 朽ちぬらむ 植ゑし小松も 苔生ひにけり
太政大臣<頭中将>(唱和歌)
【現代語訳】
昔の老木はなるほど朽ちてしまって当然だろう
植えた小松に苔が生えたのだから
※「老木」は大宮、「小松」は太政大臣自身を指す。
もしくは、「老木」が太政大臣、
「小松」は夕霧夫妻と見る説もある。
いづれをも 蔭とぞ頼む 双葉より 根ざし交はせる 松の末々
宰相の乳母(唱和歌)
【現代語訳】
どちら様をも頼みにしております、幼い時分から
互いに仲睦まじく成長なさった二本の松でいらっしゃいますから
※宰相の乳母は夕霧の乳母。
夕霧夫妻を祝福する和歌。
色まさる 籬の菊も 折々に 袖うちかけし 秋を恋ふらし
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
色濃くなった籬の菊も折にふれて
袖をうち掛けて舞った昔の秋を思い出すことでしょう
※青海波を舞った昔の秋を思い出して詠んだ和歌。
紫の 雲にまがへる 菊の花 濁りなき世の 星かとぞ見る
太政大臣<頭中将>(唱和歌)
【現代語訳】
紫の雲に似ている菊の花は
濁りのない世の中の星かと思います
※「久方の雲の上にて見る菊は天つ星とぞあやまたれける」
(古今集秋下、二六九、藤原敏行)を踏まえた和歌。
秋をへて 時雨ふりぬる 里人も かかる紅葉の 折をこそ見ね
朱雀院(唱和歌)
【現代語訳】
何度も秋を経て、時雨と共に年老いた里人でも
このように美しい紅葉を見たことはない
※朱雀院は、冷泉帝の今日の六条院行幸を羨ましく思う。
「ふり」は「降り」と「古り」の掛詞。
世の常の 紅葉とや見る いにしへの ためしにひける 庭の錦を
冷泉帝(唱和歌)
【現代語訳】
ありふれた紅葉と思って御覧になるのでしょうか
故桐壺院の先例にならった紅葉の錦ですのに
※今日の紅葉は故桐壺院の先例を模倣したもの
だと謙遜し、朱雀院を慰めている。
若菜上(24首)
さしながら 昔を今に 伝ふれば 玉の小櫛ぞ 神さびにける
秋好中宮 ⇒ 朱雀院(贈歌)
【現代語訳】
挿したまま昔から今になりましたので
玉の小櫛は古くなってしまいました
※朱雀院は、秋好中宮が昔伊勢に下向する際
小櫛を髪にさして送り出した。
昔を懐かしみながら女三の宮の成長を称える和歌。
さしつぎに 見るものにもが 万世を 黄楊の小櫛の 神さぶるまで
朱雀院 ⇒ 秋好中宮(返歌)
【現代語訳】
あなたに引き続いて姫宮の幸福になっていくのを見たいものです
千秋万歳を告げる黄楊の小櫛が古くなるまで
※「秋好中宮の幸福に引き続き、
我が娘・女三の宮に幸福になりますように」の意。
若葉さす 野辺の小松を 引き連れて もとの岩根を 祈る今日かな
玉鬘 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
若葉が芽ばえる野辺の小松を引き連れて
お世話して下さった元の岩根を祝う今日の子の日ですこと
※「小松」は玉鬘の子ども、
「岩根」は源氏を指す。
生い先長い「小松」と固く不滅な「岩根」
にあやかって源氏の健康と長寿を祈る和歌。
小松原 末の齢に 引かれてや 野辺の若菜も 年を摘むべき
光源氏 ⇒ 玉鬘(返歌)
【現代語訳】
小松原の将来のある年齢にあやかって
野辺の若菜である私も長生きするでしょう
※「摘む」「積む」は掛詞。
「小松」「摘む」は縁語。
「小松(玉鬘の子どもたち)の豊かな
生命力にあやかって、
私も長生きできるでしょう」という意味の和歌。
目に近く 移れば変はる 世の中を 行く末遠く 頼みけるかな
紫の上 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
目の前で移り変わっていく二人の仲でしたのに
行く末長くと信頼していたとは
※女三の宮が降嫁したことで、
紫の上は源氏に裏切られたと失望した。
命こそ 絶ゆとも絶えめ 定めなき 世の常ならぬ 仲の契りを
光源氏 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
命が絶えてしまうのは仕方ないことだが
無常のこの世とは違う変わらない二人の仲なのですよ
中道を 隔つるほどは なけれども 心乱るる 今朝のあは雪
光源氏 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
二人の仲を邪魔するほどではありませんが
降り乱れる今朝の淡雪に私の心も乱れています
はかなくて うはの空にぞ 消えぬべき 風にただよふ 春のあは雪
女三の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
頼りなくて空に消えてしまいそうです
風に漂う春の淡雪のように
背きにし この世に残る 心こそ 入る山路の ほだしなりけれ
朱雀院 ⇒ 紫の上(贈歌)
【現代語訳】
捨て去ったこの世に残る子どもを思う心こそが
山に入る私の妨げなのです
※「この世」に「子」をかけている。
「女三の宮を心配に思う気持ちが、
山の御寺で仏道に専念する妨げとなっている」の意。
背く世の うしろめたくは さりがたき ほだしをしひて かけな離れそ
紫の上 ⇒ 朱雀院(返歌)
【現代語訳】
お捨てになったこの世がご心配なら
離れがたい姫君から無理に離れたりしないでください
※朱雀院の出家に対して、
批判的な意味が込められている。
年月を なかに隔てて 逢坂の さも塞きがたく 落つる涙か
光源氏 ⇒ 朧月夜(贈歌)
【現代語訳】
長い年月を隔ててようやくお逢いできたのに
このような障子に隔たれていては堰き止めがたく涙が零れます
※「逢坂」と「逢ふ」、
「関」と「塞」の掛詞。
「逢坂」と「関」は縁語。
朧月夜は源氏と障子を隔てて対面したが、
源氏は障子を無理に動かして逢瀬を遂げる。
涙のみ 塞きとめがたき 清水にて ゆき逢ふ道は はやく絶えにき
朧月夜 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
涙だけは関の清水のように堰き止められず流れますが
お逢いする道はとっくの昔に絶えていました
※「逢ふ道」と「近江路」の掛詞。
(逢坂の関は近江国にあった)
「関」「清水」は「逢坂」の縁語。
沈みしも 忘れぬものを こりずまに 身も投げつべき 宿の藤波
光源氏 ⇒ 朧月夜(贈歌)
【現代語訳】
須磨に沈んで暮らしていた頃のことを忘れないが
また懲りもせずにこの邸の藤の花(淵)に身を投げてしまいたい
※「こりずま」と「須磨」、
「藤」と「淵」の掛詞。
朧月夜を藤の花に喩えている。
朧月夜への執着心を表現した和歌。
身を投げむ 淵もまことの 淵ならで かけじやさらに こりずまの波
朧月夜 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
身を投げようとおっしゃる淵も本当の淵ではないのですから
懲りることなくあなたの偽りの言葉を信用したりしません
※「淵」と「藤」の掛詞、「藤」と「波」は縁語。
源氏の執心を突っぱねる和歌。
身に近く 秋や来ぬらむ 見るままに 青葉の山も 移ろひにけり
紫の上 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
近くに秋が来たのかしら、見ているうちに
青葉の山のあなたの心の色が変わってきましたね
※「秋」と「飽き」をかける。
「私はあなたに飽きられてしまったのですか」の意。
水鳥の 青羽は色も 変はらぬを 萩の下こそ けしきことなれ
光源氏 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
水鳥の青い羽の私の心の色は変わらないのに
萩の下葉のあなたこそ心が変わっていきます
※「水鳥の青羽」は源氏、「萩」は紫の上を喩える。
老の波 かひある浦に 立ち出でて しほたるる海人を 誰れかとがめむ
明石の尼君(唱和歌)
【現代語訳】
長生きした甲斐があると嬉し涙を流している
出家した老人の私を誰が批判したりするでしょうか
※「貝」と「効」、「尼」と「海人」の掛詞。
「波」「貝」「浦」「潮垂る」は「海人」の縁語。
東宮に入内して妊娠した
孫の明石の姫君の立派な姿を見て感慨にひたっている。
しほたるる 海人を波路の しるべにて 尋ねも見ばや 浜の苫屋を
明石の姫君(唱和歌)
【現代語訳】
泣いていらっしゃる尼君に案内していただいて
訪ねてみたいものです、生まれ故郷の明石の浦を
世を捨てて 明石の浦に 住む人も 心の闇は はるけしもせじ
明石の君(唱和歌)
【現代語訳】
出家して明石の浦に住んでいる父の入道も
子を思うがゆえの心の闇は晴れることもないでしょう
光出でむ 暁近く なりにけり 今ぞ見し世の 夢語りする
明石の入道(独詠歌)
【現代語訳】
朝日があがってくる暁が近づいてきたことよ
昔見た夢の話を、今になって初めてします
※明石の入道の辞世の歌。
生まれた男皇子の即位、明石の姫君の立后が近づいたと喜ぶ。
この和歌が書かれた手紙には、
入道が昔見た予言の夢の話も書かれていた。
いかなれば 花に木づたふ 鴬の 桜をわきて ねぐらとはせぬ
柏木 ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
どうして、花から花へと木を飛び移る鴬は
桜を特別なものとして、ねぐらにしないのでしょうか
※花を六条院の他の女たちに、
桜を女三の宮に、鴬を源氏に喩える。
源氏が女三の宮を愛していないことを非難する和歌。
柏木はこの日、女三の宮の美しい姿を見てしまった。
深山木に ねぐら定むる はこ鳥も いかでか花の 色に飽くべき
夕霧 ⇒ 柏木(返歌)
【現代語訳】
深山の木をねぐらと決めているはこ鳥も
どうして美しい花の色に飽きたりしましょうか
※深山木を紫の上に、はこ鳥を源氏に、
花を女三の宮に喩える。
「源氏は紫の上を愛しているが
美しい女三の宮に飽きたりはしない」と反論する和歌。
よそに見て 折らぬ嘆きは しげれども なごり恋しき 花の夕かげ
柏木 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
遠くから見るばかりで
手折ることのできない悲しみは深いですが
あの日の夕方に見た花の美しさは今でも恋しく思われます
※「嘆き」に「投げ木」を連想させ、
「折る」「繁る」「花」は「木」の縁語である。
「花」は女三の宮の美貌を言う。
いまさらに 色にな出でそ 山桜 およばぬ枝に 心かけきと
小侍従 ⇒ 柏木(返歌)
【現代語訳】
今になって表情にお出しなさいますな
手の届かない山桜の枝に恋をしたなどと
※女三の宮が返事をかけそうにないので
女房の小侍従が代返した。
若菜下(18首)
恋ひわぶる 人のかたみと 手ならせば なれよ何とて 鳴く音なるらむ
柏木(独詠歌)
【現代語訳】
恋い慕っている人の形見と思って可愛がっていると
どういうつもりでそんな鳴き声を出すのか
※柏木は女三の宮が飼っていた猫を入手した。
猫が「ねう、ねう(寝よう、寝よう)」と
鳴くのを聞いて詠んだ和歌。
誰れかまた 心を知りて 住吉の 神代を経たる 松にこと問ふ
光源氏 ⇒ 明石の尼君(贈歌)
【現代語訳】
わたし以外に誰が昔の事情を知って
住吉に神代から生える松に話しかけたりしましょうか
※住吉参詣した源氏は、
須磨・明石に流浪していた過去を回想する。
住の江を いけるかひある 渚とは 年経る尼も 今日や知るらむ
明石の尼君 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
住吉の浜を、生きてきた甲斐がある浜だと
年老いた尼も今日知ることでしょう
※「貝」と「効」、「尼」と「海人」をかけている。
昔こそ まづ忘られね 住吉の 神のしるしを 見るにつけても
明石の尼君 (独詠歌)
【現代語訳】
昔のことが何より忘れられない
住吉の神の霊験を目の前で見るにつけても
住の江の 松に夜深く 置く霜は 神の掛けたる 木綿鬘かも
紫の上 (唱和歌)
【現代語訳】
住吉の浜の松に夜が深くなってから置く霜は
神様が掛けた木綿鬘(ゆうかずら)でしょうか
※住吉の神の神意を詠む和歌。
「霜」を「木綿鬘」に見立てる。
木綿鬘は頭にかける木綿で作ったかつらのこと。
神人の 手に取りもたる 榊葉に 木綿かけ添ふる 深き夜の霜
明石の姫君 (唱和歌)
【現代語訳】
神に仕える人が手に持った榊の葉に
木綿を掛け添えたような深い夜の霜ですこと
祝子が 木綿うちまがひ 置く霜は げにいちじるき 神のしるしか
中務の君 (唱和歌)
【現代語訳】
神に仕える人々の木綿鬘と見間違えるような霜は
おっしゃる通り住吉の神の御霊験でございましょう
※中務の君は、紫の上に仕える女房。
起きてゆく 空も知られぬ 明けぐれに いづくの露の かかる袖なり
柏木 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
起きて帰って行く先も分からない暗い夜明けに
どこから露がかかって袖が濡れるのでしょう
※「起き」と「置き」の掛詞。
「置く」と「露」は縁語。
「露」は涙を象徴している。
女三の宮と一夜を過ごした柏木は、
まだ空の暗い明け方に帰っていく。
明けぐれの 空に憂き身は 消えななむ 夢なりけりと 見てもやむべく
女三の宮 ⇒ 柏木(返歌)
【現代語訳】
夜明けの暗い空にこの辛い身は消えてしまいたいです
これは夢であったと思っておしまいにできるように
悔しくぞ 摘み犯しける 葵草 神の許せる かざしならぬに
柏木(独詠歌)
【現代語訳】
悔しいものだ、罪を犯してしまったことよ
あの人と逢ってしまった
神が許した関係ではないのに
※「摘み犯す」と「罪犯す」
「葵」と「逢ふ日」の掛詞。
女三の宮との関係を罪であると自覚している。
もろかづら 落葉を何に 拾ひけむ 名は睦ましき かざしなれども
柏木(独詠歌)
【現代語訳】
落葉のように魅力のない方をどうして妻にしたのだろう
同じ朱雀院の娘である姉妹同士ではあるが
※「もろかづら」は賀茂祭の際に頭にさす
葵と桂の飾りのこと。
「挿頭(かざし)」には
姉妹という意味の「かざし」をかける。
女三の宮と二の宮は姉妹である。
柏木は女二の宮を妻としたが、
女三の宮に比べて見劣りがすると言っている。
わが身こそ あらぬさまなれ それながら そらおぼれする 君は君なり
六条御息所<死霊> ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
私の身はこんなに変わり果ててしまったが
知らないふりをするあなたは昔と変わらないですね
※紫の上を一時絶命させた
六条御息所の死霊が詠んだ和歌。
消え止まる ほどやは経べき たまさかに 蓮の露の かかるばかりを
紫の上 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
露が消えずに残っている間だけでも生きられるでしょうか
たまたま蓮の露がこのように残っているだけの命ですから
※「消え」と「露」と「かかる」、
「玉」と「露」は縁語。
「たまさか」には「魂(たま)」を響かせる。
自身のはかない命を消え残る露に喩えた和歌。
契り置かむ この世ならでも 蓮葉に 玉ゐる露の 心隔つな
光源氏 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
お約束しましょう、この世だけでなく来世でも
蓮の葉の上に玉のように置く露のように
少しも心の隔てを置かないでくださいよ
※この世のみならず、来世までもの愛を誓う和歌。
夕露に 袖濡らせとや ひぐらしの 鳴くを聞く聞く 起きて行くらむ
女三の宮 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
夕露に袖を濡らせというのでしょうか、
ひぐらしが鳴くのを聞きながら
起きて行かれるのですね
※「夕露に袖濡らす」は涙を流すということ。
「起きて」は「露」の縁語「置きて」を響かす。
夕方は本来男が訪ねてくる時刻であるのに、
帰ろうとする源氏を恨む和歌。
待つ里も いかが聞くらむ 方がたに 心騒がす ひぐらしの声
光源氏 ⇒ 女三の宮(返歌)
【現代語訳】
私を待っている人はどのように聞いているでしょうか
それぞれに心を騒がせるひぐらしの声ですね
海人の世を よそに聞かめや 須磨の浦に 藻塩垂れしも 誰れならなくに
光源氏 ⇒ 朧月夜 (贈歌)
【現代語訳】
あなたが出家されたことを他人事として聞き流せません
私が須磨の浦で涙を流していたのは他ならぬあなたのせいなのに
※「海人」に「尼」をかける。
朧月夜が出家したと聞いて、
知らせてくれなかった冷たさを恨む和歌。
海人舟に いかがは思ひ おくれけむ 明石の浦に いさりせし君
朧月夜 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
私は尼になりましたが、
あなたはどうして遅れをおとりになったのでしょう
明石の浦で女性と恋をなさっていたあなたですものね
※「いさり(漁り)」は暗に明石の君との結婚のことを指すか。
「須磨流浪で涙を流していたのではなく、
他の女と恋をしていたのでしょう」と切り返す。
柏木(11首)
今はとて 燃えむ煙も むすぼほれ 絶えぬ思ひの なほや残らむ
柏木 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
これが最期であると燃える私の荼毘の煙も
くすぶって空に上っていけず
あなたへの諦められない思いがなおもこの世に残ることでしょう
※「思ひ」と「火」は掛詞。
「煙」「火」は縁語。
病に倒れた柏木は女三の宮に手紙を書く。
立ち添ひて 消えやしなまし 憂きことを 思ひ乱るる 煙比べに
女三の宮 ⇒ 柏木(返歌)
【現代語訳】
私も一緒に煙になって消えてしまいたいです
辛いことを思い乱れる悩みの重さを競い合って
行方なき 空の煙と なりぬとも 思ふあたりを 立ちは離れじ
柏木 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
行くえのない空の煙になったとしても
愛しているあなたのおそばを離れたくありません
※「煙」と「立ち」は縁語。
柏木の詠んだ最後の和歌。
誰が世にか 種は蒔きしと 人問はば いかが岩根の 松は答へむ
光源氏 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
いったい誰が種を蒔いたのですかと人がきいたら
岩根の松は誰と答えるでしょうか
※「松」は若君(薫)を喩える。
「誰が父親かと問われたら、薫は誰と答えるでしょうか」の意。
時しあれば 変はらぬ色に 匂ひけり 片枝枯れにし 宿の桜も
夕霧 ⇒ 一条御息所(贈歌)
【現代語訳】
季節が巡って来たならまた変わらない色に咲くものです
片方の枝が枯れてしまったこの桜の木も
※「夫(柏木)を亡くした女二の宮も、
時がたてばまた元気になれるでしょう」の意。
一条御息所は、女二の宮(落葉の宮)の母親。
この春は 柳の芽にぞ 玉はぬく 咲き散る花の 行方知らねば
一条御息所 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
今年の春は柳の芽に露の玉が貫いているように泣いています
咲いて散る桜の花の行く方もわからないので
※「娘の将来が不安で、泣いています」の意。
木の下の 雫に濡れて さかさまに 霞の衣 着たる春かな
太政大臣<頭中将>(唱和歌)
【現代語訳】
木の葉からしたたる雫に濡れて
順番が逆ですが
親が子の喪に服している春です
※「さかさまに」は
親が子の喪に服すことを言う。
「木の下の雫」は涙に濡れる意。
「霞の衣」は喪服の喩え。
息子(柏木)の死を悼む太政大臣(頭中将)の和歌。
亡き人も 思はざりけむ うち捨てて 夕べの霞 君着たれとは
夕霧(唱和歌)
【現代語訳】
亡くなった人も思わなかったことでしょう
親に先立って父親が喪服を着ることになろうとは
恨めしや 霞の衣 誰れ着よと 春よりさきに 花の散りけむ
弁の君(唱和歌)
【現代語訳】
恨めしいことだ、喪服を誰かが着るようにと思って
春より先に花は散ってしまったのでしょうか
※弁の君は柏木の弟。
ことならば 馴らしの枝に ならさなむ 葉守の神の 許しありきと
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
同じことならば連理の枝のように親しくして下さい
葉守の神のお許しがあったのですから
※「葉守の神」とは、樹木に宿り、木を護り、
葉を茂らせる神。
柏木に 葉守の神は まさずとも 人ならすべき 宿の梢か
少将の君 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
柏木に葉守の神はいらっしゃらなくても
むやみに人を近づけてよい梢ではないのです
※葉守の神は柏木に宿るとされているので
逆に「柏木に葉守の神はまさずとも」と言っている。
女二の宮の代わりに返歌をした。
横笛(8首)
世を別れ 入りなむ道は おくるとも 同じところを 君も尋ねよ
朱雀院 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
この世を捨てて仏道に入った時期は私より遅くとも
同じ極楽浄土をあなたも求めて下さい
※朱雀院は御寺の近くで採れた
「野老(ところ)=山芋の一種」を
女三の宮に贈ったので、
和歌にも「ところ」を詠みこんでいる。
憂き世には あらぬところの ゆかしくて 背く山路に 思ひこそ入れ
女三の宮 ⇒ 朱雀院(返歌)
【現代語訳】
辛い世の中とは違う所に行きたくて
父上が世を捨てて入った同じ御寺に私も入りたいのです
憂き節も 忘れずながら 呉竹の こは捨て難き ものにぞありける
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
辛いことは忘れられないが
この子は捨て難く思われることだ
※「こは」は「これは」の意と「子は」の掛詞。
「節」と「竹」は縁語。
若君(薫)が竹の子をかじっているのを見て詠んだ和歌。
ことに出でて 言はぬも言ふに まさるとは 人に恥ぢたる けしきをぞ見る
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
言葉に出しておっしゃらないのは、
おっしゃる以上に気持ちが深いのだと
あなたの慎み深い態度から分かりますよ
※「言」と「琴」をかけている。
夕霧は直前に柏木の遺品である琴を演奏し、
女二の宮にも演奏を勧めている。
深き夜の あはればかりは 聞きわけど ことより顔に えやは弾きける
女二の宮<落葉の宮> ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
秋の夜の情趣はわかっていますが
琴を弾くよりも表情に、
あなたの意に添うような様子を見せましたでしょうか
※「ことよりほかに」「いひける」とする本もある。
これだと「琴以外で何か言うことができましたか」
という意味になる。
露しげき むぐらの宿に いにしへの 秋に変はらぬ 虫の声かな
一条御息所 ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
泣き暮らしておりますこの荒れ果てた家で昔の
秋と変わらない笛の音を聞かせて戴きました
横笛の 調べはことに 変はらぬを むなしくなりし 音こそ尽きせね
夕霧 ⇒ 一条御息所(返歌)
【現代語訳】
横笛の音色は昔に比べて特に変わりませんが
亡くなった人を悼む泣き声は絶えることがありません
※「こと」に「琴」をかけている。
笛竹に 吹き寄る風の ことならば 末の世長き ねに伝へなむ
柏木<死霊> ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
この笛に吹き寄る風が同じであるなら
私の子孫に伝えて欲しいものだ
※「世」「節(よ)」、「根」「音」の掛詞。
「竹」「根」「「節(よ)」は縁語。
「根」は子孫を意味する。
「この笛を、私の子孫に伝えてください」の意。
夕霧の夢の中で、柏木の霊が詠んだ和歌。
鈴虫(6首)
蓮葉を 同じ台と 契りおきて 露の分かるる 今日ぞ悲しき
光源氏 ⇒ 女三の宮(贈歌)
【現代語訳】
来世は同じ蓮の花に生まれようと約束しましたが
その葉に置く露のように離れ離れでいる今日が悲しいです
※女三の宮主催の
持仏開眼供養の準備を行っている時に詠んだ和歌。
隔てなく 蓮の宿を 契りても 君が心や 住まじとすらむ
女三の宮 ⇒ 光源氏(返歌)
【現代語訳】
一緒の蓮の花の上で仲睦まじくしようと約束なさっても
あなたの本音はさとり澄ましていて、
私と一緒にとは思っていないでしょう
※「すまじ」は「住まじ」と「清まじ」の掛詞。
おほかたの 秋をば憂しと 知りにしを ふり捨てがたき 鈴虫の声
女三の宮 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
秋という季節は辛いものと分かっていますが
鈴虫の声だけは飽きずに聞き続けていたいものです
※「秋」と「飽き」の掛詞。「鈴」「振り」は縁語。
自分のことを飽きた源氏への恨みを含んだ和歌。
心もて 草の宿りを 厭へども なほ鈴虫の 声ぞふりせぬ
光源氏 ⇒ 女三の宮(返歌)
【現代語訳】
あなたはご自分の意志でこの世をお捨てになったのですが
やはりお声は鈴虫と同じように変わりませんね
※「振り」と「古り」は掛詞、
「鈴」と「振り」は縁語。
「草のやどり」は六条院、
「鈴虫」は女三の宮を喩える。
「出家しても、あなたは昔と同じく美しい」の意。
雲の上を かけ離れたる すみかにも もの忘れせぬ 秋の夜の月
冷泉院 ⇒ 光源氏(贈歌)
【現代語訳】
宮中から遠く離れた住みかである仙洞御所にも
忘れもせず秋の月はかがやいています
※「中秋の名月は照っているのに
あなたはこちらを訪れませんね」の意。
月影は 同じ雲居に 見えながら わが宿からの 秋ぞ変はれる
光源氏 ⇒ 冷泉院(返歌)
【現代語訳】
月の光は昔と同じくかがやいていますが
私の方がすっかり変わってしまいました
※「月影」は冷泉院のことを指す。
夕霧(26首)
山里の あはれを添ふる 夕霧に 立ち出でむ空も なき心地して
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
山里の物悲しい風情を添える夕霧のせいで
帰って行く気持ちにもなれません
※「霧」「立ち」「空」が縁語。
夕霧は落葉の宮が住む山荘を訪問した。
山賤の 籬をこめて 立つ霧も 心そらなる 人はとどめず
女二の宮<落葉の宮> ⇒ 夕霧 (返歌)
【現代語訳】
山里の垣根に立ちこめた霧も
軽薄な心の人は引き止めません
※「霧」は落葉の宮自身、「心そらなる人」は夕霧を指す。
自分に好意を持つ夕霧を突っぱねる。
我のみや 憂き世を知れる ためしにて 濡れそふ袖の 名を朽たすべき
女二の宮<落葉の宮> ⇒ 夕霧 (贈歌)
【現代語訳】
私だけが不幸な結婚をした女の例として
さらに良くない評判を受けて涙を流さなければいけないのですか
※「柏木との結婚で苦しんだのに、
さらに夕霧と結婚して苦しまなければならないのか」の意。
夕霧は落葉の宮をかき抱き、迫った。
おほかたは 我濡衣を 着せずとも 朽ちにし袖の 名やは隠るる
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(返歌)
【現代語訳】
私があなたに悲しい思いをさせなくても
既に悪い評判が立ってしまって、もう隠せるものではありません
※「既に柏木とのことで悪評が広まっているから
自分との間に悪評を立ててもいいではないですか」の意。
荻原や 軒端の露に そぼちつつ 八重立つ霧を 分けぞ行くべき
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
荻原の軒端の荻の露に濡れながら
何重にも立ち籠めた霧の中を
帰って行かねばならないのでしょう
※「露と霧の中、涙に濡れて
帰っていかねばならない」と、
落葉の宮の同情をひこうとする和歌。
分け行かむ 草葉の露を かことにて なほ濡衣を かけむとや思ふ
女二の宮<落葉の宮> ⇒ 夕霧 (返歌)
【現代語訳】
帰って行く途中で草葉の露に濡れるのを言いがかりに
私に濡れ衣を着せようと思っていらっしゃいますか
※「私にあらぬ浮き名を負わせないでください」の意。
魂を つれなき袖に 留めおきて わが心から 惑はるるかな
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
魂を冷たいあなたの所に置いてきて
自分のことながらどうしてよいか分からず困惑しています
※後朝の文。
せくからに 浅さぞ見えむ 山川の 流れての名を つつみ果てずは
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
私の気持ちを拒むゆえに浅いお心が見えるでしょう
山川の流れのように浮き名は包み隠せませんから
※「塞く」「浅さ」「流れ」は「山川」の縁語。
女郎花 萎るる野辺を いづことて 一夜ばかりの 宿を借りけむ
一条御息所 ⇒ 夕霧 (返歌)
【現代語訳】
女郎花が萎れている野辺をどういうお心から
一夜だけの宿をお借りになったのですか
※夕霧と落葉の宮が結婚したと思い、
今宵、夕霧の訪問がないのを責める和歌。
秋の野の 草の茂みは 分けしかど 仮寝の枕 結びやはせし
夕霧 ⇒ 一条御息所(贈歌)
【現代語訳】
秋の野の草の茂みを踏み分けてうかがいましたが
仮寝の枕に男女の契りを結ぶようなことはしていません
あはれをも いかに知りてか 慰めむ あるや恋しき 亡きや悲しき
雲居雁 ⇒ 夕霧 (贈歌)
【現代語訳】
あなたが悲しんでいるのを
何が原因と思って慰めしたらいいですか
生きている方が恋しいのか、亡くなった方が悲しいのか
※「ある」は落葉宮を、「亡き」は一条御息所を指す。
いづれとか 分きて眺めむ 消えかへる 露も草葉の うへと見ぬ世を
夕霧 ⇒ 雲居雁(返歌)
【現代語訳】
特に何が悲しいというわけではありません
消えてしまう露も草葉の上だけでないこの世ですから
※落葉の宮とのことをはぐらかした和歌。
里遠み 小野の篠原 わけて来て 我も鹿こそ 声も惜しまね
夕霧 ⇒ 少将の君(贈歌)
【現代語訳】
人里が遠いので小野の篠原を踏み分けて来ましたが
私も鹿のように声をあげて泣いています
※「鹿」と「然(しか)」の掛詞。
少将の君は落葉の宮の女房。
藤衣 露けき秋の 山人は 鹿の鳴く音に 音をぞ添へつる
少将の君 ⇒ 夕霧(返歌)
【現代語訳】
喪服も涙に濡れている秋の山人は
鹿の鳴く声に、声を添えて泣いています
見し人の 影澄み果てぬ 池水に ひとり宿守る 秋の夜の月
夕霧(独詠歌)
【現代語訳】
あの人がもう住んでいないこの邸の池の水に
ひとりで宿を守っている秋の夜の月よ
※柏木を偲ぶ和歌。
「見し人」は柏木を指す。
一条宮邸のそばを通った時に
詠んだ和歌。
「人の影」「(月の)影」、
「住み」「澄み」の掛詞。
「影」「澄み」「月」は縁語
いつとかは おどろかすべき 明けぬ夜の 夢覚めてとか 言ひしひとこと
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
いつになったらお訪ねできますでしょうか
明けない夜の夢が覚めたらとおっしゃっていましたが
※落葉の宮が昨夜
「今は、かくあさましき夢の世を、すこしも思ひ覚ます折あらば」
と語ったことを受けた和歌。
朝夕に 泣く音を立つる 小野山は 絶えぬ涙や 音無の滝
女二の宮<落葉の宮>(独詠歌)
【現代語訳】
朝も夕も声を立てて泣いている小野山では
絶え間なく流れる涙は音無の滝になるのでしょうか
※落葉の宮の手習歌。
のぼりにし 峰の煙に たちまじり 思はぬ方に なびかずもがな
女二の宮<落葉の宮>(独詠歌)
【現代語訳】
母君が空へのぼっていった峰の煙にまじって
思ってもいない方角になびかずにいたいものだわ
※「夕霧と結婚するよりは亡くなった母のもとへ行きたい」の意。
恋しさの 慰めがたき 形見にて 涙にくもる 玉の筥かな
女二の宮<落葉の宮>(独詠歌)
【現代語訳】
恋しさを慰められない形見の品として
涙に曇る玉の箱ですこと
※玉の筥は法華経を入れた箱。
母御息所の形見である。
怨みわび 胸あきがたき 冬の夜に また鎖しまさる 関の岩門
夕霧 ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
怨んでも怨みきれません
思いを晴らすことができない冬の夜に
さらに鎖をかけられた関所のような岩の門ですね
※夕霧の思惑で一条宮邸に連れ戻された
落葉の宮は、塗籠にこもって夕霧を拒否し続ける。
落葉の宮の冷たい態度を恨む和歌。
馴るる身を 恨むるよりは 松島の 海人の衣に 裁ちやかへまし
雲居雁 ⇒ 夕霧(贈歌)
【現代語訳】
長年一緒に過ごして古くなった我が身を恨むよりも
いっそのこと尼姿になってしまおうかしら
※着古して柔らかくなった
夕霧の下着を手に取って詠んだ和歌。
夕霧は雲居雁を置いて落葉の宮のもとへ
向かおうとする。
「恨む」「裏」、「尼」「海人」は掛詞。
「馴るる」「裏」「衣」「裁ち」、「浦」「松島」は縁語。
松島の 海人の濡衣 なれぬとて 脱ぎ替へつてふ 名を立ためやは
夕霧 ⇒ 雲居雁(返歌)
【現代語訳】
長年連れ添ったからといって、
私を捨てて尼になったという噂が立ってよいものでしょうか
契りあれや 君を心に とどめおきて あはれと思ふ 恨めしと聞く
太政大臣<頭中将> ⇒ 女二の宮<落葉の宮>(贈歌)
【現代語訳】
前世からの因縁があるのか、あなたのことを
お気の毒だと思う一方で、恨めしい方だと聞いています
※「あはれ」と思うのは
落葉の宮が息子・柏木の妻だったから。
「うらめし」と思うのは
落葉の宮が娘・雲居雁の夫(夕霧)を奪ったから。
何ゆゑか 世に数ならぬ 身ひとつを 憂しとも思ひ かなしとも聞く
女二の宮<落葉の宮> ⇒ 太政大臣<頭中将>(返歌)
【現代語訳】
なぜ世の中で人の数にも入らない私のことを
辛いとも思い愛しいともお思いになるのでしょう
※「身ひとつ」と言うことで
自分は夕霧とは無関係だと主張している。
数ならば 身に知られまし 世の憂さを 人のためにも 濡らす袖かな
藤典侍 ⇒ 雲居雁(贈歌)
【現代語訳】
私が人数に入る存在だったら
夫の浮気の悲しみを思い知るでしょうが
あなたのために涙で袖を濡れております
※藤典侍は惟光の娘で、夕霧の愛人。
「身」は藤典侍自身のこと。
「人」は雲居雁を指す。
「私は身分が低いから夫の浮気は諦められるけど、
あなたはお辛いでしょう」の意。
人の世の 憂きをあはれと 見しかども 身にかへむとは 思はざりしを
雲居雁 ⇒ 藤典侍(返歌)
【現代語訳】
他人の夫婦仲の辛さを
気の毒だと思って見てきましたが
自分のことになるとは思いませんでした
御法(12首)
惜しからぬ この身ながらも かぎりとて 薪尽きなむ ことの悲しさ
紫の上 ⇒ 明石の君(贈歌)
【現代語訳】
惜しくもない我が身ですが、これを最後として
薪が尽きて火が消えるように
命が尽きることを思うと悲しいものです
※「この身」に「菓(このみ)」を掛け、
法華経の経文を想起させる。
「菓(このみ)を採り水を汲み、
薪を拾ひ食(じき)を設け」(法華経、提婆達多品)
法華経の序品には「薪尽て火の滅するが如し」
という一文もある。
二条院の法華経供養の際に詠んだ和歌。
薪こる 思ひは今日を 初めにて この世に願ふ 法ぞはるけき
明石の君 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
仏道へのお思いは今日を最初の日として
この世で願う仏法のために
この先も永く祈り続けられることでしょう
※紫の上が自身の寿命が尽きることを
詠んだのに対し、
明石の君は紫の上の長寿を祝う和歌を
返し、励ましている。
絶えぬべき 御法ながらぞ 頼まるる 世々にと結ぶ 中の契りを
紫の上 ⇒ 花散里(贈歌)
【現代語訳】
私の人生で最後の法会ですが
現世も来世もと結んだあなたとの縁を頼もしく思います
結びおく 契りは絶えじ おほかたの 残りすくなき 御法なりとも
花散里 ⇒ 紫の上(返歌)
【現代語訳】
あなたと法会で結んだ縁は絶えることがないでしょう
私のような普通の人は残り少ない命で、
法会も多くは催せないでしょうけど(あなたは違う)
※「普通の人は法会も多くは催せないけれど、
紫の上は長生きして、法会も多く開催できます」の意。
おくと見る ほどぞはかなき ともすれば 風に乱るる 萩のうは露
紫の上(唱和歌)
【現代語訳】
起きていると見えるのも少しの時間であり
ややもすれば風に吹き乱れる萩の上露のような
はかない私の命です
※「置く」「起く」は掛詞。
「露」「置く」縁語。
ややもせば 消えをあらそふ 露の世に 後れ先だつ ほど経ずもがな
光源氏(唱和歌)
【現代語訳】
ややもすれば先を争って消えてゆく
露のようにはかない人の世に
後れたり先立ったりせずあなたと私、一緒に消えたいものです
秋風に しばしとまらぬ 露の世を 誰れか草葉の うへとのみ見む
明石の中宮(唱和歌)
【現代語訳】
秋風に少しの間もとどまらず散っていく露の命を
誰が草葉の上の露だけと思うでしょうか
※紫の上だけではなく
自分の命もはかないものだと慰める和歌。
いにしへの 秋の夕べの 恋しきに 今はと見えし 明けぐれの夢
夕霧(独詠歌)
【現代語訳】
昔お姿を拝見した秋の夕暮を恋しく思うにつけても
明け方の暗がりの中で見たご臨終のお姿が夢のようだ
※紫の上の死を悼む和歌。
いにしへの 秋さへ今の 心地して 濡れにし袖に 露ぞおきそふ
致仕大臣<頭中将> ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
昔の秋までが今のような心地がして
涙に濡れた袖の上にさらに涙を落としています
※30年前の妹・葵の上の死を
思い出しつつ今回の紫の上の死を悼む弔問の和歌。
露けさは 昔今とも おもほえず おほかた秋の 夜こそつらけれ
光源氏 ⇒ 致仕大臣<頭中将> (返歌)
【現代語訳】
涙に濡れているのは昔も今も同じです
だいたい秋の夜というものは物悲しい気持ちになるのです
枯れ果つる 野辺を憂しとや 亡き人の 秋に心を とどめざりけむ
秋好中宮 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
枯れ果てた野辺を嫌っていたから
亡くなられたお方は
秋をお好きでなかったのでしょうか
※紫の上は生前、春が好きだった。
「秋に亡くなったのは、秋が好きでなかったからか」の意。
「枯れ果つる」は人生の最期を連想させる。
昇りにし 雲居ながらも かへり見よ われ飽きはてぬ 常ならぬ世に
光源氏 ⇒ 秋好中宮 (返歌)
【現代語訳】
煙となって昇っていった雲の上からも
こちらを振り返って見てほしいものです
私は無常の世にすっかり飽きてしまいました
※「飽き」と「秋」をかけている。
幻(26首)
わが宿は 花もてはやす 人もなし 何にか春の たづね来つらむ
光源氏 ⇒ 蛍兵部卿宮 (贈歌)
【現代語訳】
私の家には花を喜ぶ人もいませんのに
どうして春が訪ねて来たのでしょうか
※兵部卿宮が新年の挨拶に訪ねてきて詠んだ和歌。
「春」は兵部卿宮を喩える。
香をとめて 来つるかひなく おほかたの 花のたよりと 言ひやなすべき
蛍兵部卿宮 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
梅の香を求めて来たかいもなく
ありふれた花見のついでに立ち寄ったとおっしゃるのですか
※「香」は光源氏を喩える。
「源氏様に会いにきたのに、
花見のついでに来たというのですか」の意。
憂き世には 雪消えなむと 思ひつつ 思ひの外に なほぞほどふる
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
つらいこの世から消えてしまいたいと思いながらも
心外にもまだ生きていることだ
※「行き消え」と「雪消え」、
「経る」と「降る」の掛詞。
「消え」と「降る」は「雪」の縁語。
植ゑて見し 花のあるじも なき宿に 知らず顔にて 来ゐる鴬
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
植えて眺めた花の主人もいない家に
知らない顔をしてやって来て鳴いている鴬よ
※「花のあるじ」は紫の上を指す。
毎年巡りくる季節と不変の自然に対し、
生命のはかなさを嘆く歌。
今はとて 荒らしや果てむ 亡き人の 心とどめし 春の垣根を
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
とうとう出家するとなると
すっかり荒れ果ててしまうのだろうか
亡き人が愛していた春の庭も
なくなくも 帰りにしかな 仮の世は いづこもつひの 常世ならぬに
光源氏 ⇒ 明石の君 (贈歌)
【現代語訳】
泣きながら帰ってきたことです
このかりそめの世は
どこもかしこも永遠のものはないので
※「鳴く」「泣く」、
「雁」「仮」の掛詞。
「常」に「床」を連想させる。
「雁」と「常世」は縁語。
雁は常世から渡ってくると考えられていた。
常世から帰ってきた「雁」に源氏自身を喩え、
「常世」に「床」をかけて、
永遠にと願った紫の上との共寝も二度とないと
嘆く和歌。
雁がゐし 苗代水の 絶えしより 映りし花の 影をだに見ず
明石の君 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
雁がいた苗代水(なわしろみず)が
なくなってからは
そこに映っていた花の影さえ見ることができません
※「苗代水」は紫の上を、
「花」源氏を喩える。
紫の上が亡くなってから
源氏が意気消沈して明石の君への訪れがないことをいう。
夏衣 裁ち替へてける 今日ばかり 古き思ひも すすみやはせぬ
花散里 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
夏の衣に着替えた今日だけは
昔のことも思い出しませんか
※「紫の上との昔の思い出を追憶しましょう」の意。
羽衣の 薄きに変はる 今日よりは 空蝉の世ぞ いとど悲しき
光源氏 ⇒ 花散里 (返歌)
【現代語訳】
羽衣のように薄い着物に着替える今日からは
はかない世の中をよりいっそう悲しく感じます
※「薄き」「空蝉」は「羽衣」の縁語。
「うつせみの」は「世」に係る枕詞。
さもこそは よるべの水に 水草ゐめ 今日のかざしよ 名さへ忘るる
中将の君 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
いかにも神に供える水も古くなって
水草が生えているでしょう
賀茂祭の葵の名前さえ忘れてしまわれるとは
※「神に供える水に水草が生えるほど
長い間、私のことをお忘れになるのは
仕方ないが、花の名前さえ忘れるとは」の意。
中将の君は源氏に仕える女房。
この日は賀茂祭であった。
おほかたは 思ひ捨ててし 世なれども 葵はなほや 摘みをかすべき
光源氏 ⇒ 中将の君 (返歌)
【現代語訳】
だいたいのものへの執着を捨ててしまったこの世だが
この葵はやはり摘んでしまいたい
※「葵」は中将の君を喩える。
「摘み」「罪」の掛詞。
「葵」「罪」「犯す」は神事に関する縁語。
中将の君への戯れの和歌。
亡き人を 偲ぶる宵の 村雨に 濡れてや来つる 山ほととぎす
光源氏 (唱和歌)
【現代語訳】
亡き紫の上を偲ぶ今宵の村雨に
濡れて来たのか、山時鳥よ
※ホトトギスの鳴き声を聞きつつ、
紫の上をしのぶ和歌。
ほととぎす 君につてなむ ふるさとの 花橘は 今ぞ盛りと
夕霧 (唱和歌)
【現代語訳】
時鳥よ、紫の上に伝えておくれ
故郷の橘の花は今が盛りですよと
つれづれと わが泣き暮らす 夏の日を かことがましき 虫の声かな
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
することもなく泣き暮らしている夏の日に
私のせいで蜩(ひぐらし)も泣いているのだろうか
夜を知る 蛍を見ても 悲しきは 時ぞともなき 思ひなりけり
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
夜がおとずれたことを知って光る螢を見ても悲しいのは
昼夜かまわず燃える亡き人を慕う思いの炎であった
※「思ひ」に「火」をかけている。
七夕の 逢ふ瀬は雲の よそに見て 別れの庭に 露ぞおきそふ
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
七夕の逢瀬は雲の上の他人事として見て
私は紫の上との別れに悲しみの涙を添えることよ
※紫の上との死別を思い、
7月8日未明の、露にびっしょり濡れた庭を悲しく眺める。
君恋ふる 涙は際も なきものを 今日をば何の 果てといふらむ
中将の君 ⇒ 光源氏 (贈歌)
【現代語訳】
ご主人様を慕う涙には際限もないのに
今日の一周忌はいったい何が終わる日だと言うのでしょうか
※「君」は亡き紫の上。「果て」は一周忌をさす。
人恋ふる わが身も末に なりゆけど 残り多かる 涙なりけり
光源氏 ⇒ 中将の君 (返歌)
【現代語訳】
人を恋い慕う私の余命は少なくなったが
残りが多いのはこの涙であることよ
もろともに おきゐし菊の 白露も 一人袂に かかる秋かな
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
一緒に起きて置いた菊のきせ綿の朝露も
今年の秋は私ひとりの袂にかかることだ
※平安時代には9月8日に
菊の花を真綿でおおって菊の香を移し、
翌日の朝に露に湿った真綿で顔にあて、
健康を保とうとする風習があった。
「置き」「起き」は掛詞。
大空を かよふ幻 夢にだに 見えこぬ魂の 行方たづねよ
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
大空を飛んでいく幻術士よ、夢の中にさえ
現れない亡き人の魂の行く方を探してくれ
宮人は 豊明と いそぐ今日 日影も知らで 暮らしつるかな
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
宮人が豊明(とよのあかり)の節会に
夢中になっている今日
私は日の光も見ないで暮らしてしまったことよ
※「日光(ひかげ)」と「日蔭の蔓」の掛詞。
豊明節会では日蔭の蔓を冠の装飾として用いた。
悲しみに暮れ出家を思う源氏は、
華やかな儀式に入り込むことができない。
死出の山 越えにし人を 慕ふとて 跡を見つつも なほ惑ふかな
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
死出の山を越えてしまった人を慕ってついて行こうとして
その筆跡を見ながらも悲しみ思い悩むことだ
※出家前に紫の上の文を破って焼かせる源氏。
紫の上の筆跡を見て湧き上がる悲しみを詠んだ和歌。
かきつめて 見るもかひなし 藻塩草 同じ雲居の 煙とをなれ
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
かき集めて見ても無意味なものだ
この手紙も亡き人と同じように空に昇る煙となりなさい
※「藻塩草」は手紙の譬喩。「煙」の縁語。
春までの 命も知らず 雪のうちに 色づく梅を 今日かざしてむ
光源氏 ⇒ 導師 (贈歌)
【現代語訳】
春まで命があるかどうか分からないから
雪の中に色づいた紅梅を今日は頭に飾ろう
千世の春 見るべき花と 祈りおきて わが身ぞ雪と ともにふりぬる
導師 ⇒ 光源氏 (返歌)
【現代語訳】
多くの春を見るようにと
あなたの長寿をお祈りいたしましたが
私の身は降る雪とともに年ふりました
もの思ふと 過ぐる月日も 知らぬまに 年もわが世も 今日や尽きぬる
光源氏 (独詠歌)
【現代語訳】
物思いしながら過ごし月日がたつのも知らない間に
今年も私の寿命も今日が最後になったか
※源氏、辞世の和歌。
匂宮(1首)
おぼつかな 誰れに問はまし いかにして 初めも果ても 知らぬわが身ぞ
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
はっきりしないことだ、誰にきいたらよいだろう
どうして初めも終わりも分からない我が身の上なのだろう
※自らの出生の秘密に悩む薫の和歌。
紅梅(4首)
心ありて 風の匂はす 園の梅に まづ鴬の 訪はずやあるべき
紅梅大納言 ⇒ 匂宮 (贈歌)
【現代語訳】
思うところがあって風が匂いを吹いて送る園の梅に
真っ先に鴬が来ないということがありましょうか
※「梅」は紅梅大納言の中の君
「鴬」は匂宮を喩える。
二人の結婚を望む和歌。
花の香に 誘はれぬべき 身なりせば 風のたよりを 過ぐさましやは
匂宮 ⇒ 紅梅大納言 (返歌)
【現代語訳】
花の香に誘われてよいような身であったら
風の便りをそのまま見過ごさないでしょう
※「中の君には不釣り合いな自分なので」
と縁談を拒否する和歌。
匂宮は、宮の御方に興味を示す。
本つ香の 匂へる君が 袖触れば 花もえならぬ 名をや散らさむ
紅梅大納言 ⇒ 匂宮 (贈歌)
【現代語訳】
もともとよい香りが漂っていらっしゃる
あなたが袖を振ると
花も素晴らしい評判を得るでしょう
※「花」は中の君を指す。
花の香を 匂はす宿に 訪めゆかば 色にめづとや 人の咎めむ
匂宮 ⇒ 紅梅大納言 (返歌)
【現代語訳】
花の香りを匂わしていらっしゃる
宿に訪ねていったら
色好みな男だと人が批判するのではないでしょうか
※中の君との縁談に気がのらず、ごまかそうとしている。
竹河(24首)
折りて見ば いとど匂ひも まさるやと すこし色めけ 梅の初花
宰相の君 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
折ってみたらよりいっそう良い香りがするのでは
もう少し色づいてみてはどうですか、梅の初花は
※「折りて見る」は男女の関係を持つことを暗示。
「梅の初花」は薫。戯れの歌。
宰相の君は女房。
薫が堅物なので、冗談を言っている。
よそにては もぎ木なりとや 定むらむ 下に匂へる 梅の初花
薫 ⇒ 宰相の君 (返歌)
【現代語訳】
傍目には枯木だと決めつけているのでしょうが
心の中は美しく咲いている梅の初花です
※内面の魅力を主張する和歌。
人はみな 花に心を 移すらむ 一人ぞ惑ふ 春の夜の闇
蔵人の少将 ⇒ 女房 (贈歌)
【現代語訳】
人はみな花に心を寄せているのでしょうが
私は一人で迷っています、春の夜の闇の中で
※蔵人の少将は夕霧の息子。
玉鬘の娘に求婚している。
美しい薫のほうが注目されているのを嘆く和歌。
「花」は薫を指す。
をりからや あはれも知らむ 梅の花 ただ香ばかりに 移りしもせじ
女房 ⇒ 蔵人の少将 (返歌)
【現代語訳】
時と場合によって心を寄せるものです
ただ梅の花の香りが漂っているだけで
こうも心がひかれるのではありませんよ
※玉鬘邸の女房が、蔵人の少将を慰める。
竹河の 橋うちいでし 一節に 深き心の 底は知りきや
薫 ⇒ 玉鬘 (贈歌)
【現代語訳】
竹河を歌った、あの歌の文句の一端から
私の深い心を知っていただけましたか
※「橋」と「端」の掛詞。
「竹」と「節」、「河」と「深き」と「底」は縁語。
直前に薫は催馬楽「竹河」を
歌っている。
「竹河の 橋のつめなるや
橋のつめなるや 花園に はれ
花園に 我をば放てや
我をば放てや少女伴へて」
玉鬘の娘(大君)への気持ちを
アピールしている和歌である。
竹河に 夜を更かさじと いそぎしも いかなる節を 思ひおかまし
藤侍従 ⇒ 薫(返歌)
【現代語訳】
竹河を歌って夜遅くならないようにと
急いでお帰りになったのに
どんな深い心があると思えばよいのでしょうか
※「夜」と「よ(竹の節と節の間)」の掛詞。
「竹」と「節」は縁語。
桜ゆゑ 風に心の 騒ぐかな 思ひぐまなき 花と見る見る
大君(唱和歌)
【現代語訳】
桜のせいで、風が吹くたびに心が騒ぎます
私を思ってくれない花だと思いながら
※大君は玉鬘の娘。
桜が散るのを惜しむ和歌。
咲くと見て かつは散りぬる 花なれば 負くるを深き 恨みともせず
宰相の君(唱和歌)
【現代語訳】
咲いたと見えてすぐ散ってしまう花なので
負けて木を取られたことを深く恨みません
※大君と中君は桜の所有権を巡って碁を打っていた。
中君が勝利した。
宰相の君は大君の方についていた女房。
風に散る ことは世の常 枝ながら 移ろふ花を ただにしも見じ
中君(唱和歌)
【現代語訳】
桜が風に散ることは世の常ですが、枝ごと
こちらの木になった花を平常心で見ていられないでしょう
心ありて 池のみぎはに 落つる花 あわとなりても わが方に寄れ
大輔の君(唱和歌)
【現代語訳】
こちらに味方して池の水際に散る花よ
水の泡となっても私の方に流れ寄っておくれ
※大輔の君は中君側の女房。
大空の 風に散れども 桜花 おのがものとぞ かきつめて見る
童女(唱和歌)
【現代語訳】
大空の風に散ってしまったけれど、桜の花を
私のものと思ってかき集めてみました
※中君側の童女
桜花 匂ひあまたに 散らさじと おほふばかりの 袖はありやは
なれき<童女>(唱和歌)
【現代語訳】
桜の花の美しさを方々に散らすまいとしても
空を覆うほど大きな袖がございましょうか
※なれきは大君側の童女
つれなくて 過ぐる月日を かぞへつつ もの恨めしき 暮の春かな
薫 ⇒ 藤侍従 (贈歌)
【現代語訳】
冷たい態度のままで過ぎてゆく年月を数えていますと
恨めしくも春の終わりになりました
いでやなぞ 数ならぬ身に かなはぬは 人に負けじの 心なりけり
蔵人の少将 ⇒ 中将の御許 (贈歌)
【現代語訳】
何ということか、物の数にも入らない身なのに
負けじ魂も成就させることができないのだ
※中将の御許は玉鬘邸の女房。
蔵人の少将が思いを寄せている大君は、
冷泉院への参院が決まった。
わりなしや 強きによらむ 勝ち負けを 心一つに いかがまかする
中将の御許 ⇒ 蔵人の少将 (返歌)
【現代語訳】
無理なことです、強い方が勝つ勝負を
あなたのお心一つでどうすることもできません
※「強き」「勝ち負け」は碁の縁語。
「強き」は冷泉院を指している。
あはれとて 手を許せかし 生き死にを 君にまかする わが身とならば
蔵人の少将 ⇒ 中将の御許 (贈歌)
【現代語訳】
気の毒だと思って、大君を私にいただけませんか
この先の生死はあなた次第の我が身と思うのならば
※「手をゆるす」は、碁で相手に何目か置き意志を許すこと。
「生き死に」は碁の縁語である。
花を見て 春は暮らしつ 今日よりや しげき嘆きの 下に惑はむ
蔵人の少将 ⇒ 玉鬘 (贈歌)
【現代語訳】
花を見て春を過ごしました
今日からは茂った木の下で悲しみに暮れるでしょう
※「嘆き」に「木」を響かせる。
「木」と「繁き」は縁語。
今日ぞ知る 空を眺むる けしきにて 花に心を 移しけりとも
玉鬘 ⇒ 蔵人の少将 (返歌)
【現代語訳】
今日こそ分かりました、空を眺めているふりをして
花に心を奪われていらっしゃったのだと
あはれてふ 常ならぬ世の 一言も いかなる人に かくるものぞは
大君 ⇒ 蔵人の少将 (贈歌)
【現代語訳】
「可哀想だ」という一言も、この無常の世において
いったい誰に言葉をかけたらよろしいのでしょうか
※蔵人の少将の手紙に
「あはれと思ふ、とばかりだに、
一言のたまはせば、それにかけとどめられて、
しばしもながらへやせむ」と
書いてあったのを踏まえた和歌。
生ける世の 死には心に まかせねば 聞かでややまむ 君が一言
蔵人の少将 ⇒ 大君 (返歌)
【現代語訳】
この世の生死は思い通りにならないので
聞かずに終わってしまうのでしょうか
あなたの「可哀想だ」という一言を
手にかくる ものにしあらば 藤の花 松よりまさる 色を見ましや
薫 ⇒ 藤侍従 (贈歌)
【現代語訳】
手に取ることができるものなら、藤の花の
松の緑より美しい色をむなしく眺めているでしょうか
※大君への失恋を嘆く和歌。
「藤の花」は大君の比喩。
「力の及ぶ相手であれば大君を他人のものにしなかったのに」の意。
紫の 色はかよへど 藤の花 心にえこそ かからざりけれ
藤侍従 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
紫の色は同じですが、藤の花は
私の思い通りにできなかったのです
※「色はかよへど」は
藤侍従と大君が姉弟であることを言う。
竹河の その夜のことは 思ひ出づや しのぶばかりの 節はなけれど
女房 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
竹河を歌ったあの夜のことは覚えていますか
思い出すほどのことではございませんが
※「夜」と「世」の掛詞。
「竹」と「よ(節と節の間)」と「節」は縁語。
流れての 頼めむなしき 竹河に 世は憂きものと 思ひ知りにき
薫 ⇒ 女房 (返歌)
【現代語訳】
これまでの期待も空しいこととわかり
世の中は辛いものだとよく思い知りました
※大君への失恋を引きずる薫の和歌。
橋姫(13首)
うち捨てて つがひ去りにし 水鳥の 仮のこの世に たちおくれけむ
八の宮 (唱和歌)
【現代語訳】
つがいでいた水鳥の雁は
はかないこの世に子を残して見捨てて行ったのだろうか
※母親に先立たれた娘たちの不幸を詠む和歌。
「雁」と「仮」、
「この世」の「こ」には
「雁の子」の「子」をかけている。
いかでかく 巣立ちけるぞと 思ふにも 憂き水鳥の 契りをぞ知る
大君 (唱和歌)
【現代語訳】
どうしてこんなに大きくなったのかと思うにつけても
水鳥のような辛い宿命が思い知られます
※「憂き水鳥」に「憂き身」を詠みこんでいる。
泣く泣くも 羽うち着する 君なくは われぞ巣守に なりは果てまし
中君 (唱和歌)
【現代語訳】
泣きながらも羽を着せかけてくださる
お父様がいらっしゃらなかったら
私は大きくなることはできなかったでしょうに
見し人も 宿も煙に なりにしを 何とてわが身 消え残りけむ
八の宮 (唱和歌)
【現代語訳】
妻も京の邸も煙となってしまったが
どうして我が身だけがこの世に消えずに残っているのだろう
※「見し人」は亡くなった北の方。
「宿」は火災で燃えた京の邸。
八の宮と娘は宇治へ移る。
世を厭ふ 心は山に かよへども 八重立つ雲を 君や隔つる
冷泉院 ⇒ 八の宮 (贈歌)
【現代語訳】
世の中を避ける気持ちは宇治山に通じておりますが
あなたが何重もの雲で山を隔てていらっしゃるのでしょうか
あと絶えて 心澄むとは なけれども 世を宇治山に 宿をこそ借れ
八の宮 ⇒ 冷泉院 (返歌)
【現代語訳】
世を捨てて心が澄みきっているわけではありませんが
世を辛いものと思い宇治山で暮らしております
※「住む」と「澄む」の掛詞。
山おろしに 耐へぬ木の葉の 露よりも あやなくもろき わが涙かな
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
山おろしの風に耐えられない木の葉の露よりも
妙にもろく流れる私の涙よ
あさぼらけ 家路も見えず 尋ね来し 槙の尾山は 霧こめてけり
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
夜が明けて行きますが帰る家路も見えません
訪ねて来た槙の尾山は霧が立ち込めていますので
※「帰りたくありません」という挨拶の和歌。
「槙の尾山」は宇治川右岸にある山。
雲のゐる 峰のかけ路を 秋霧の いとど隔つる ころにもあるかな
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
雲がかかっている峰の険しい山道には秋霧が立ち込め
父上との間をますます隔てている今日この頃です
※父八の宮は山寺にこもっている。
橋姫の 心を汲みて 高瀬さす 棹のしづくに 袖ぞ濡れぬる
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
姫君たちのお寂しい心をお察ししまして
浅瀬を漕ぐ舟の棹の雫で袖が濡れるように
涙で袖を濡らして泣いています
※「袖を濡らす」は涙を流していることを暗示する。
さしかへる 宇治の河長 朝夕の しづくや袖を 朽たし果つらむ
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
棹さして行き来する宇治川の渡し守は
朝夕の雫に濡れて袖を朽ちさせていることでしょう
目の前に この世を背く 君よりも よそに別るる 魂ぞ悲しき
柏木 ⇒ 女三の宮 (贈歌)
【現代語訳】
目の前で出家されるあなたよりも
お会いできずに死んでいく私の魂のほうが悲しいのです
※生前、柏木が女三の宮に宛てた文に
書かれていた和歌。
命あらば それとも見まし 人知れぬ 岩根にとめし 松の生ひ末
柏木 ⇒ 女三の宮 (贈歌)
【現代語訳】
生きていられたら、我が子だと思って見ることでしょう
誰も知らない岩根に残した松が成長していく姿を
※薫を「岩根の松」に喩える。
椎本(21首)
山風に 霞吹きとく 声はあれど 隔てて見ゆる 遠方の白波
八の宮 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
山風に乗って霞を吹き散らす笛の音は聞こえますが
遠くに隔たって見えるそちらの白波です
※前日に聞こえてきた笛の音を
薫のものと思って詠んだ和歌。
「遠方」は宇治に存在した地名。
「をち」(遠方)に掛ける。
薫の来訪をうながしている。
遠方こちの 汀に波は 隔つとも なほ吹きかよへ 宇治の川風
匂宮 ⇒ 八の宮 (返歌)
【現代語訳】
そちらとこちらの水際に波は隔てていても
やはり吹き通いなさい宇治の川風よ
※宇治の姉妹に興味を持っている匂宮は、
薫の代わりに八の宮に返歌をした。
山桜 匂ふあたりに 尋ね来て 同じかざしを 折りてけるかな
匂宮 ⇒ 宇治の姉妹 (贈歌)
【現代語訳】
山桜が美しく咲いているところを訪ねてきて
同じこの地の桜を插頭しに手折ったことよ
私たちは血縁同士なのです
※匂宮は美しい桜の枝を折って、
和歌とともに姉妹に贈った。
「同じかざし」は匂宮と姉妹が
同じ皇族の血をひいていることを言う。
かざし折る 花のたよりに 山賤の 垣根を過ぎぬ 春の旅人
中君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
插頭の花を折るついでに、山里の粗末な家は
通り過ぎてしまう春の旅人なのでしょうね
われなくて 草の庵は 荒れぬとも このひとことは かれじとぞ思ふ
八の宮 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
私が亡くなって邸が荒れてしまっても
この一言の約束だけは守っていただきたいと思っております
※「一言」とは、直前に
「私が亡くなった後、姫君たちを見捨てないでください」
と言ったことを指す。
「一言」と「一琴」、
「枯れ」と「離れ」は掛詞。
「草」と「枯れ」は縁語。
いかならむ 世にかかれせむ 長き世の 契りむすべる 草の庵は
薫 ⇒ 八の宮 (返歌)
【現代語訳】
どのような世の中になっても
こちらを訪れないことはありません
末長く約束を結びましたので
※「草」と「結ぶ」は縁語。
牡鹿鳴く 秋の山里 いかならむ 小萩が露の かかる夕暮
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
牡鹿が鳴く秋の山里ではいかがお過ごしでしょうか
小萩に露のかかるように、
あなたも泣いている夕暮でしょう
※「小萩」は中君を喩える。
「露」は涙を暗示。
「かかる」は「露が懸かる」と
「かかる夕暮」をかけている。
八の宮が亡くなり、弔問の和歌。
涙のみ 霧りふたがれる 山里は 籬に鹿ぞ 諸声に鳴く
大君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
涙ばかりが霧のように塞がっている山里では
垣根に鹿が声をあわせて鳴いております
※大君が妹中君の代わりに詠んだ和歌。
「鹿」は自分たちのことを指す。
「鳴く」には「泣く」をかける。
朝霧に 友まどはせる 鹿の音を おほかたにやは あはれとも聞く
匂宮 ⇒ 中君 (返歌)
【現代語訳】
朝霧のなかで友を見失った鹿の声を
ありふれたものとして
しみじみ悲しく聞いていられますでしょうか
色変はる 浅茅を見ても 墨染に やつるる袖を 思ひこそやれ
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
色の変わった浅茅を見るにつけても
墨染の喪服を着ていらっしゃるお姿をお察しいたします
色変はる 袖をば露の 宿りにて わが身ぞさらに 置き所なき
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
喪服に色の変わった袖に露は置いていますが
我が身はどこにも置き所がありません
※「露」「置く」は縁語。
秋霧の 晴れぬ雲居に いとどしく この世をかりと 言ひ知らすらむ
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
秋霧の晴れない雲の上ではよりいっそう
この世を仮の世だと雁が鳴いて知らせるのだろう
※空に雁が飛んでいくのを見て詠んだ和歌。
「雁」と「仮り」の掛詞。
君なくて 岩のかけ道 絶えしより 松の雪をも なにとかは見る
大君 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
父上がお亡くなりになって
険しい岩の山道も絶えてしまいました
あなたは松に積もった雪をどう御覧になりますか
※「岩のかけ道」は
姉妹の住む山荘と山寺とを結ぶ道のこと。
奥山の 松葉に積もる 雪とだに 消えにし人を 思はましかば
中君 ⇒ 大君 (返歌)
【現代語訳】
奥山の松葉に積もる雪とでも
亡くなった父上を思うことができたらいいのに
※「雪」「消え」縁語。
「雪は再び降り積もることができるから
父を雪と思えたらいいけれど、
人間は雪とは違うから
亡くなった人とは二度と会えない」の意。
雪深き 山のかけはし 君ならで またふみかよふ 跡を見ぬかな
大君 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
雪深い山にかかった橋は
あなた以外に
誰も踏み分けて訪れる人はございません
※薫が「匂宮の文には誰が返事をしているか?」
と聞いたので、
「あなた以外に文を送ったことはありません」
と言い返している。
つららとぢ 駒ふみしだく 山川を しるべしがてら まづや渡らむ
薫 ⇒ 大君 (返歌)
【現代語訳】
氷に閉ざされて馬が踏み砕いて歩く山川を
匂宮に案内するついでに、まずは私が渡りましょうか
※「匂宮より先に私があなたと
男女の契りを結びたい」の意。
立ち寄らむ 蔭と頼みし 椎が本 空しき床に なりにけるかな
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
立ち寄るべき蔭と信頼していた椎の木の根元は
空しい床になってしまったな
※八の宮が生前使っていた部屋を見て詠んだ和歌。
「椎」は八の宮の比喩。
君が折る 峰の蕨と 見ましかば 知られやせまし 春のしるしも
大君 (唱和歌)
【現代語訳】
父上が摘んでくださった峰の蕨でしたら
春が来た印だと思ったでしょうけれど
※阿闍梨から贈られた山菜を見て詠んだ和歌。
雪深き 汀の小芹 誰がために 摘みかはやさむ 親なしにして
中君 (唱和歌)
【現代語訳】
雪深い水際の小芹も誰のために摘んで喜びましょうか
私たちは親がいませんので
※「小芹」の「小」に「子」を響かす。
「親」と「子」は縁語。
つてに見し 宿の桜を この春は 霞隔てず 折りてかざさむ
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
あの時は事のついでに眺めたあなたの家の桜を
今年の春は霞を隔てず手で折ってかざしたいものです
※「花を折る」という表現は
男女の関係になることを暗示している。
心のままに詠んだ積極的な和歌。
いづことか 尋ねて折らむ 墨染に 霞みこめたる 宿の桜を
中君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
どこと思って花を手折るのでしょうか
墨染に霞んでいる私の家の桜を
※宇治の姉妹は父親の服喪中であるので、
「墨染に」と詠んでいる。
総角(31首)
あげまきに 長き契りを 結びこめ 同じ所に 縒りも会はなむ
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
総角に末長い約束を結びこめて
あなたと一緒になりたいものです
※「総角」は催馬楽の曲名。
<総角>
「総角や トウトウ 尋ばかりや
トウトウ 離(さか)りて寝たれども
転(まろ)びあひけり トウトウ
か寄りあひけり トウトウ」
<意味>
男女の子供が、最初は少し離れて
寝ていたけど、転がって最後は
仲睦まじくなった
ぬきもあへず もろき涙の 玉の緒に 長き契りを いかが結ばむ
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
貫いて止めることも出来ない
もろい涙の玉の緒に
末長い約束をどうして結ぶことができるでしょうか
※「もろき涙の玉の緒」は
自らの余命が短いことを言う。
山里の あはれ知らるる 声々に とりあつめたる 朝ぼらけかな
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
山里の情趣が感じられます鳥の声に
さまざまな思でいっぱいになる朝け方ですね
※「とりあつめたる」に「鳥」をかける。
薫は大君の寝所に入ったが、
何事もなく朝を迎えた。
鳥の音も 聞こえぬ山と 思ひしを 世の憂きことは 訪ね来にけり
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
鳥の声も聞こえない山里と思っていましたが
人の世の辛いことはやって来るものなのですね
おなじ枝を 分きて染めける 山姫に いづれか深き 色と問はばや
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
同じ枝を分けて染めた山姫を
どちらが深い色ですかと尋ねましょうか
※反語表現。
「大君と中君どちらへの気持ちが深いと
問うまでもなく、自分の気持ちは
もともと大君にあります」という意味の和歌。
山姫の 染むる心は わかねども 移ろふ方や 深きなるらむ
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
山姫が色を染め分ける理由はわかりませんが
あなたは色変わりして妹の方に
深い思いを寄せているのでしょう
※「中君のほうに心を寄せているのでしょう」の意。
大君は、中君と薫を結婚させたがっている。
女郎花 咲ける大野を ふせぎつつ 心せばくや しめを結ふらむ
匂宮 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
女郎花が咲いている大野に人が入らないように
どうして心狭く縄を張っていらしゃるのか
※「女郎花」は宇治の姉妹を指す。
匂宮を宇治に連れていきたがらない
薫へのたわむれの和歌。
霧深き 朝の原の 女郎花 心を寄せて 見る人ぞ見る
薫 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
霧が深く立ち込める朝の原の女郎花は
深い心を寄せている人だけが見るものです
※「朝の原」は大和国の歌枕。
しるべせし 我やかへりて 惑ふべき 心もゆかぬ 明けぐれの道
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
道案内をした私のほうが迷ってしまいそうです
満足できない気持ちで帰る明け方の薄暗い道を
※薫は大君の寝所に再び近づくが、
思いは遂げられずに朝を迎える。
かたがたに くらす心を 思ひやれ 人やりならぬ 道に惑はば
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
妹のことと自分のことをそれぞれに
思い悩む私の気持ちを思いやって下さい
あなた自身のせいで道にお迷いならば
世の常に 思ひやすらむ 露深き 道の笹原 分けて来つるも
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
世の中でありふれたことと
思っていらっしゃるのでしょうか
露が深く立ち込めた道の笹原を分けて来たのですが
※匂宮は中君と契った。
翌朝の後朝の文に書かれていた和歌。
小夜衣 着て馴れきとは 言はずとも かことばかりは かけずしもあらじ
薫 ⇒ 大君 (贈歌)
【現代語訳】
小夜衣を着て親密になったとは言いませんが
いいがかりくらいはつけないでもありませんよ
※「寝所に近づき、大君の顔まで見たのだから
冷たくあしらってもだめですよ」と脅す和歌。
隔てなき 心ばかりは 通ふとも 馴れし袖とは かけじとぞ思ふ
大君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
隔てるものはなく心だけは通い合うでしょうが
慣れ親しんだ仲とはおっしゃらないでください
中絶えむ ものならなくに 橋姫の 片敷く袖や 夜半に濡らさむ
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
関係が切れようとするものではないのに
あなたが独り敷く袖は夜中に涙で濡れることだろう
※匂宮は母の明石の中宮に外出を制限されている。
絶えせじの わが頼みにや 宇治橋の 遥けきなかを 待ちわたるべき
中君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
あなたとの関係が切れないようにと信じて
古い宇治橋のように
末永い仲をずっとお待ちしております
いつぞやも 花の盛りに 一目見し 木のもとさへや 秋は寂しき
宰相の中将 (唱和歌)
【現代語訳】
いつのことだったか
花の盛りに一目見た木の根元までが
秋はお寂しい感じになっているでしょう
※「木のもと」に「子(姫君たち)」を響かせる。
宰相の中将は夕霧の息子。
以下5首、宇治での紅葉狩りにて
詠まれた和歌。
桜こそ 思ひ知らすれ 咲き匂ふ 花も紅葉も 常ならぬ世を
薫 (唱和歌)
【現代語訳】
桜こそは知っているでしょう
美しく咲く花も紅葉も、みなこの世は常ならぬものだと
いづこより 秋は行きけむ 山里の 紅葉の蔭は 過ぎ憂きものを
衛門督 (唱和歌)
【現代語訳】
どこから秋は去って行くのでしょう
山里の紅葉の蔭は立ち去るのが辛いのに
※衛門督は夕霧の息子。
見し人も なき山里の 岩垣に 心長くも 這へる葛かな
宮の大夫 (唱和歌)
【現代語訳】
お会いしたことのある方も亡くなってしまい
山里の岩垣に心が変わることなく這いかかっている蔦よ
※「見し人」は八の宮を指す。
秋はてて 寂しさまさる 木のもとを 吹きな過ぐしそ 峰の松風
匂宮 (唱和歌)
【現代語訳】
秋が終わって寂しさがつのる木のもとを
あまり強く吹かないでください、峰の松風よ
※「木」に「子」をかける。
若草の ね見むものとは 思はねど むすぼほれたる 心地こそすれ
匂宮 ⇒ 女一の宮 (贈歌)
【現代語訳】
若草のように美しいあなたと
一緒に寝ようとは思いませんが
気分がふさぎこんでおります
※女一の宮は匂宮にとって同母姉。
美しい姉に恋心を抱いて贈った和歌。
眺むるは 同じ雲居を いかなれば おぼつかなさを 添ふる時雨ぞ
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
眺めているのは同じ空なのに
どうしてこんなに会いたい気持ちをつのらせる時雨なのか
※匂宮は母・明石の中宮に禁じられて宇治へ通えない。
霰降る 深山の里は 朝夕に 眺むる空も かきくらしつつ
中君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
霰が降る深山の里は朝も夕も
眺める空が暗く曇っています
霜さゆる 汀の千鳥 うちわびて 鳴く音悲しき 朝ぼらけかな
薫 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
霜が冷たく凍っている水際の千鳥が耐えられずに
寂しく鳴く声が悲しい明け方ですね
暁の 霜うち払ひ 鳴く千鳥 もの思ふ人の 心をや知る
中君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
明け方の霜を払って鳴く千鳥も
悲しんでいる人の気持ちが分かるのでしょうか
かき曇り 日かげも見えぬ 奥山に 心をくらす ころにもあるかな
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
曇って日の光も見えない山奥で
心を暗くなる今日このごろだなあ
※病気になり弱っていく大君を看病しながら
絶望的な気持ちを詠んだ和歌。
くれなゐに 落つる涙も かひなきは 形見の色を 染めぬなりけり
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
紅色の衣に落ちる涙が何の役にも立たないと思うのは
大君の形見の黒色に衣の色を染めないからだ
※大君が亡くなったが、
大君と薫は夫婦ではないので
喪服を着られないことを嘆いた和歌。
この時は薄紅の直衣を着ていた。
おくれじと 空ゆく月を 慕ふかな つひに住むべき この世ならねば
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
大君に後れまいと、空を流れていく月が恋しい
いつまでも住んでいられないこの世なので
※「澄む」に「住む」を掛ける。
「澄む」は「月」の縁語。
亡くなった大君を慕う和歌。
恋ひわびて 死ぬる薬の ゆかしきに 雪の山にや 跡を消なまし
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
恋に思い悩んで死ぬ薬が欲しいがために
雪の山に入って行って跡をくらましてしまいたい
※大君の死を悲しむ絶望の和歌。
来し方を 思ひ出づるも はかなきを 行く末かけて なに頼むらむ
中君 ⇒ 匂宮 (贈歌)
【現代語訳】
過ぎ去ったことを思い出しても頼りないのに
将来のことをどうして信用できましょうか
※匂宮は宇治を訪問し、中君に愛を誓うが
中君は匂宮の口慣れている様子に嫌気を感じた。
行く末を 短きものと 思ひなば 目の前にだに 背かざらなむ
匂宮 ⇒ 中君(返歌)
【現代語訳】
将来が短いものと思うなら
せめて私の前だけでも背かないでください
早蕨(15首)
君にとて あまたの春を 摘みしかば 常を忘れぬ 初蕨なり
阿闍梨 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
わが主人にと思って毎年の春に摘んできましたので
今年も例年どおりの初蕨です
※「君」は亡き八の宮をさす。
「摘み」と「積み」は掛詞。
この春は 誰れにか見せむ 亡き人の かたみに摘める 峰の早蕨
中君 ⇒ 阿闍梨 (返歌)
【現代語訳】
今年の春は誰にお見せしましょうか
亡き人の形見として摘んだ峰の早蕨を
※「亡き人」は亡き父・八の宮をさす。
「姉・大君が亡くなって早蕨を見せる人がいない」
の意。
折る人の 心にかよふ 花なれや 色には出でず 下に匂へる
匂宮 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
この梅の花は
折る人の心に通っている花なのでしょうか
外見には出ないけれど内側に匂いを含んでいますね
※匂宮は、薫が内心では中君を慕っている
のではないかと疑っている。
見る人に かこと寄せける 花の枝を 心してこそ 折るべかりけれ
薫 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
見る人に言いがかりをつけられる花の枝は
注意して折るべきでしたね
はかなしや 霞の衣 裁ちしまに 花のひもとく 折も来にけり
薫 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
早いものですね
喪服を作ったばかりなのに
もう花が咲く季節となりました
※大君の喪が明けて
中君が喪服を脱ぎ禊を行った日に
贈られた和歌。
「霞の衣」は喪服のこと。
見る人も あらしにまよふ 山里に 昔おぼゆる 花の香ぞする
中君 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
花を見る人もいなくなってしまうでしょう
嵐にが吹き乱れる山里に
昔を思い出させる花の香が漂っています
※中君は京へ引っ越す予定なので、
「宇治の山荘の庭の花を見る人がいなくなる」
と感傷にひたっている。
「嵐」と「あらじ」をかけている。
袖ふれし 梅は変はらぬ 匂ひにて 根ごめ移ろふ 宿やことなる
薫 ⇒ 中君 (返歌)
【現代語訳】
昔見た梅は今も変わらぬ匂いですが
すっかり引っ越してしまう邸は
今はもう他人の所なのでしょうか
さきに立つ 涙の川に 身を投げば 人におくれぬ 命ならまし
弁の尼 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
大君様が先立たれた悲しみの
涙の川に身を投げていたならば
死に後れなかったでしょうに
身を投げむ 涙の川に 沈みても 恋しき瀬々に 忘れしもせじ
薫 ⇒ 弁の尼 (返歌)
【現代語訳】
身を投げるという涙の川に沈んでも
恋しい人と過ごした折々を忘れることはできまい
人はみな いそぎたつめる 袖の浦に 一人藻塩を 垂るる海人かな
弁の尼 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
他の人は皆、準備に忙しく繕い物をしていますが
一人涙に暮れる尼の私ですこと
※「発つ」と「裁つ」、「浦」と「裏」、
「海人」と「尼」は掛詞。
「裏」「裁つ」は「袖」の縁語。
「藻塩」「海人」は「浦」の縁語。
塩垂るる 海人の衣に 異なれや 浮きたる波に 濡るるわが袖
中君 ⇒ 弁の尼 (返歌)
【現代語訳】
涙に暮れる尼であるあなたと同じです
頼りないこれからの日々を思って涙を流している私は
ありふれば うれしき瀬にも 逢ひけるを 身を宇治川に 投げてましかば
大輔の君 (唱和歌)
【現代語訳】
長生きしたので嬉しい事に出会うことができました
もし身を宇治川に投げてしまっていたら
今日、一緒に京へ行くことはできなかったでしょう
※大輔の君は中君付きの老女房。
「身を憂」の「う」は
「宇治川」の「う」とかけている。
「ましかば」反実仮想。
過ぎにしが 恋しきことも 忘れねど 今日はたまづも ゆく心かな
女房 (唱和歌)
【現代語訳】
亡くなった方を恋しく思う気持ちは忘れませんが
今日は何をさしおいてもまず嬉しく思います
※「過ぎにし」は亡き大君を指す。
眺むれば 山より出でて 行く月も 世に住みわびて 山にこそ入れ
中君 (独詠歌)
【現代語訳】
考えると山から出て昇って行く月も
この世を住みにくいものと嫌って山に帰って行くのでしょう
※「澄み」に「住み」を掛ける。
京に行っても、また宇治に帰るかも知れないと
自分の将来を案じる和歌。
しなてるや 鳰の湖に 漕ぐ舟の まほならねども あひ見しものを
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
琵琶湖の湖に漕ぐ舟のように
まともではないが一晩会ったこともあるのに
※匂宮が中君を京の二条院に迎え、
愛しているのを見て薫は悔しく思う。
「しなてるや」は「鳰(にお)の海」の枕詞。
「舟の」までの上句は「真帆」を導く序詞。
「鳰(にお)の海」は琵琶湖の呼称。
宿木(24首)
世の常の 垣根に匂ふ 花ならば 心のままに 折りて見ましを
薫 ⇒ 今上帝 (贈歌)
【現代語訳】
どこにでもあるような家の
垣根に咲いている花ならば
思いのままに手で折って鑑賞することができるでしょうに
※今上帝から女二の宮の降嫁をほのめかされ、
高貴さゆえに遠慮する意味の和歌。
霜にあへず 枯れにし園の 菊なれど 残りの色は あせずもあるかな
今上帝 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
霜に耐えられず枯れてしまった園の菊であるが
残りの色は褪せていませんよ
※「園の菊」は亡くなった藤壺女御。
「残りの色」はその娘・女二の宮を喩える。
今朝の間の 色にや賞でむ 置く露の 消えぬにかかる 花と見る見る
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
今朝の朝顔の美しさを愛でようか
置いた露が消えずに残っている
わずかの間のみ咲く花と思いながら
※はかない露より、
よりいっそうはかない朝顔の開花時間に共感する和歌。
はかなく亡くなった大君を思う。
よそへてぞ 見るべかりける 白露の 契りかおきし 朝顔の花
薫 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
あなたを姉君と思って自分の妻にしておくべきでした
白露が約束しておいた朝顔の花ですから
※「白露」を大君に、
「朝顔の花」を中君に喩えている。
消えぬまに 枯れぬる花の はかなさに おくるる露は なほぞまされる
中君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
露の消えないうちに枯れてしまう花のはかなさよりも
後に残る露はよりいっそうはかないものです
※「花」を大君、
「露」を自分に喩えている。
「後に残された私のほうが姉上よりもっと頼りない」の意。
大空の 月だに宿る わが宿に 待つ宵過ぎて 見えぬ君かな
夕霧 ⇒ 匂宮 (贈歌)
【現代語訳】
大空の月さえも宿る私の邸でお待ちしていますが
夕暮れ時が過ぎてもまだあなたはお見えにならないのですね
※夕霧は娘・六の君と匂宮との婚儀を
整えて待っているのに、匂宮がなかなか来ないので
催促の和歌を贈る。
山里の 松の蔭にも かくばかり 身にしむ秋の 風はなかりき
中君 (独詠歌)
【現代語訳】
山里の松の蔭でもこれほどに
身にこたえる秋の風は経験しなかった
※「秋」に「飽き」を掛けている。
匂宮と六の君が結婚してしまい、嘆く和歌。
女郎花 しをれぞまさる 朝露の いかに置きける 名残なるらむ
落葉の宮 ⇒ 匂宮 (贈歌)
【現代語訳】
女郎花が一段としおれています
朝露がどのように置いていったせいでしょうか
※「女郎花」を六の君に、
「朝露」を匂宮に喩える。
六の君への後朝の文の返事だが、
養母・落葉の宮の代作。
六の君は夕霧と藤典侍との娘だが、
実母の身分が低いため、落葉の宮が養母となっている。
おほかたに 聞かましものを ひぐらしの 声恨めしき 秋の暮かな
中君 (独詠歌)
【現代語訳】
宇治にいたら何気なく聞いたであろうに
ひぐらしの声が恨めしく聞こえる秋の暮だこと
※「秋」に「飽き」を掛ける。
うち渡し 世に許しなき 関川を みなれそめけむ 名こそ惜しけれ
按察使の君 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
世間から認められない仲なのに
たびたびお逢いしているという噂が広まるのが辛うございます
※「関川」は逢坂の関の川。
「塞き」「関」、
「見慣れ」に「水馴れ」をかける。
「渡し」は「川」の縁語。
按察使の君は女三の宮付の女房であり
薫の愛人。
早々に帰る薫を恨む和歌。
深からず 上は見ゆれど 関川の 下の通ひは 絶ゆるものかは
薫 ⇒ 按察使の君 (返歌)
【現代語訳】
愛が深くないように表面的には見えますが
心の中では愛情の絶えることはありませんよ
いたづらに 分けつる道の 露しげみ 昔おぼゆる 秋の空かな
薫 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
無駄に歩いた道の露が多いので
昔、あなたに添い寝した時のことが
思い出される秋の空模様ですね
※「露」は涙に濡れていることを暗示する。
薫は前日に、中君の袖をとらえて迫ったが
妊娠している様子を見て自制した。
また人に 馴れける袖の 移り香を わが身にしめて 恨みつるかな
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
他の男に慣れ親しんだ袖の移り香が
我が身にとって深く恨めしいことだ
※「また人」は薫のことを指す。
中君の袖に薫の移り香が匂っていたので、
二人は関係を持ったのではと疑う和歌。
「馴れ」と「袖」は縁語。
みなれぬる 中の衣と 頼めしを かばかりにてや かけ離れなむ
中君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
親しんで信頼してきた私たち夫婦の仲も
この程度の香りで切れてしまうのでしょうか
※「かばかり」に「香」を掛ける。
「馴れ」と「衣」は縁語。
結びける 契りことなる 下紐を ただ一筋に 恨みやはする
薫 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
あなたは他の人と契りを結んでしまったのだから
今さらどうして一途に恨んだりしましょうか
※「結ぶ」「下紐」「一筋」は縁語。
宿り木と 思ひ出でずは 木のもとの 旅寝もいかに さびしからまし
薫 (唱和歌)
【現代語訳】
昔泊まった家だと思い出さなかったら
木の下の旅寝もどんなにか寂しかったことでしょう
※宇治を訪問した際に詠んだ和歌。
荒れ果つる 朽木のもとを 宿りきと 思ひおきける ほどの悲しさ
弁の尼 (唱和歌)
【現代語訳】
荒れ果てて腐った木のもとを昔の泊まった家と
思っていてくださることが悲しいです
穂に出でぬ もの思ふらし 篠薄 招く袂の 露しげくして
匂宮 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
顔には出ないが、物思いをしているようですね
篠薄が招くので、衣の袂が露でいっぱいです
※庭のススキを眺めながら詠んだ和歌。
秋果つる 野辺のけしきも 篠薄 ほのめく風に つけてこそ知れ
中君 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
秋の終わりは野辺の景色の
篠薄をわずかに揺らしている風によって知られます
すべらきの かざしに折ると 藤の花 及ばぬ枝に 袖かけてけり
薫 (唱和歌)
【現代語訳】
帝の插頭のために折ろうとして
藤の花の私の手の届かない枝に袖をかけてしまいました
※「高貴な姫君を畏れ多くも頂戴しました」
という意味の和歌。
「及ばぬ枝」は女二の宮を喩える。
よろづ世を かけて匂はむ 花なれば 今日をも飽かぬ 色とこそ見れ
今上帝 (唱和歌)
【現代語訳】
永い間変わらず美しく咲き匂う花であるから
今日も見飽きない美しさとして見ます
君がため 折れるかざしは 紫の 雲に劣らぬ 花のけしきか
夕霧 (唱和歌)
【現代語訳】
主君のため折った插頭の花は
紫の雲にも劣らない美しい花の様子です
世の常の 色とも見えず 雲居まで たち昇りたる 藤波の花
紅梅大納言 (唱和歌)
【現代語訳】
ありふれた花の色には見えません
宮中まで立ち上った藤の花は
貌鳥の 声も聞きしに かよふやと 茂みを分けて 今日ぞ尋ぬる
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
かお鳥の声は昔聞いた声に似ているだろうかと
草の茂みを踏み分けて今日尋ねてきたのだ
※薫は宇治にて大君に似ている浮舟を見かけた。
「貌鳥(かおどり)」は実体不明であるが、
亡き大君と浮舟が「かお」が似ていることから
このように表現したか。
一説によると、貌鳥とはカッコウ。
東屋(11首)
見し人の 形代ならば 身に添へて 恋しき瀬々の なでものにせむ
薫 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
亡き大君の形代(かたしろ)ならば、
いつも側において
恋しい折々の気持ちを移して流す撫物としよう
※「見し人」は亡き大君。
「瀬々」と「なでもの」は縁語。
形代とは霊が依り憑く依り代の一種で、
撫でて穢れを移した後に川や海に流す風習があった。
浮舟のことを形代に見立てている。
みそぎ河 瀬々に出ださむ なでものを 身に添ふ影と 誰れか頼まむ
中君 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
禊をおこなう河の瀬々に流し出す撫物を
ずっと側に置いておくと誰が期待するでしょうか
※「形代=撫で物は水に流すものだから、
浮舟を生涯の伴侶として添い遂げるとは
思えません」の意。
しめ結ひし 小萩が上も 迷はぬに いかなる露に 映る下葉ぞ
浮舟の母 ⇒ 左近少将 (贈歌)
【現代語訳】
縄を結んで囲いをしていた小萩の上葉は乱れていないのに
どんな露で色が変わった下葉なのでしょう
※「露」を常陸介の実の娘、
「下葉」を左近少将に喩える。
浮舟との縁談を断り、
実の娘に乗り換えた左近少将を非難する和歌。
宮城野の 小萩がもとと 知らませば 露も心を 分かずぞあらまし
左近少将 ⇒ 浮舟の母 (返歌)
【現代語訳】
宮城野の小萩のもとと知っていたならば
露は少しも心を分け隔てしなかったでしょうに
※「宮城野の小萩」は、皇族の血を引く浮舟のこと。
「露」は自分自身の比喩。
「浮舟が皇族の血を引いていると知っていたら、
私は心変わりしなかった」の意。
ひたぶるに うれしからまし 世の中に あらぬ所と 思はましかば
浮舟 ⇒ 浮舟の母 (贈歌)
【現代語訳】
ひたすらに嬉しいことでしょう
ここが世の中で別の世界だと思えるならば
※三条の隠れ家に
心細く隠れ住んでいる浮舟の和歌。
憂き世には あらぬ所を 求めても 君が盛りを 見るよしもがな
浮舟の母 ⇒ 浮舟 (返歌)
【現代語訳】
辛いこの世ではない所を訪れてでも
あなたが幸せになっている世を見たいものです
絶え果てぬ 清水になどか 亡き人の 面影をだに とどめざりけむ
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
涸れ果てていない清水にどうして亡くなった人の
面影だけでもとどめておかなかったのだろう
※「亡き人」は八の宮、大君のこと。
さしとむる 葎やしげき 東屋の あまりほど降る 雨そそきかな
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
扉を閉ざすほど雑草が生い茂っているせいでか
東屋であまりにも待たされて雨に濡れることよ
※催馬楽「東屋」の歌詞を踏まえる。
東屋(あづまや)の 末也(マヤ)のあまりの
その 雨そそぎ 我立ち濡れぬ 殿戸開かせ
この直後、
薫は三条の隠れ家にいる浮舟と男女の契りを交わす。
形見ぞと 見るにつけては 朝露の ところせきまで 濡るる袖かな
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
亡き大君の形見だと思って見るにつけ
朝露がたくさん置くように袖が涙に濡れることだなあ
※大君に似た浮舟を手に入れたことを詠嘆する和歌。
宿り木は 色変はりぬる 秋なれど 昔おぼえて 澄める月かな
弁の尼 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
宿木の色は変わってしまった秋ですが
昔が思い出される澄んだ月ですね
※「宿り木は色変はりぬる」は
薫の気持ちが大君から浮舟に移ったことを言う。
「月」は薫の比喩。
里の名も 昔ながらに 見し人の 面変はりせる 閨の月影
薫 ⇒ 弁の尼 (返歌)
【現代語訳】
「宇治(憂し)」という里の名も私も昔のままであるのに
かつて見た大君が浮舟に面変わりしたかと思われる寝所の月光です
浮舟(22首)
まだ古りぬ 物にはあれど 君がため 深き心に 待つと知らなむ
浮舟 ⇒ 中君 (贈歌)
【現代語訳】
まだ古木にはなっておりませんが
若君のご成長を心から深く祈っております
※「まだ古り」「またぶり」、
「松」「待つ」「先づ」を掛けている。
「君」は中君の息子を指す。
若君の成長を祈る和歌。
浮舟は松が二股になった枝(またぶり)
に文をつけて中君に贈った。
長き世を 頼めてもなほ 悲しきは ただ明日知らぬ 命なりけり
匂宮 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
末長い関係を約束してもやはり悲しいのは
ただ明日も知らないこの命であることよ
※男女の契りを交わした匂宮と浮舟は、
和歌を詠み交わしつつ睦まじく一日を過ごす。
心をば 嘆かざらまし 命のみ 定めなき世と 思はましかば
浮舟 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
心変わりなど嘆いたりしないでしょう
命だけが定めないこの世と思うのならば
※匂宮が「逢いにきたくても
来られない時があったらこの絵を見ていなさい」
と言い訳したのを恨む和歌。
世に知らず 惑ふべきかな 先に立つ 涙も道を かきくらしつつ
匂宮 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
どうしてよいか分かりません
先に立つ涙が道を真っ暗にしますので
※「世」「夜」は掛詞。
「夜」「惑ふ」「立つ」「道」は縁語。
匂宮は京へ帰ることになった。
宇治に残る浮舟との別れを悲しむ和歌。
涙をも ほどなき袖に せきかねて いかに別れを とどむべき身ぞ
浮舟 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
涙も狭い袖では抑えきれません
どのように別れを止めることができるでしょうか
宇治橋の 長き契りは 朽ちせじを 危ぶむ方に 心騒ぐな
薫 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
宇治橋のように末長い約束は朽ちないから
不安に思ってふさぎこまないでください
絶え間のみ 世には危ふき 宇治橋を 朽ちせぬものと なほ頼めとや
浮舟 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
ところどころ壊れていて気がかりな宇治橋なのに
朽ちないものと、なおも頼りにしなさいとおっしゃるのですか
年経とも 変はらむものか 橘の 小島の崎に 契る心は
匂宮 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
何年たっても変わりません
橘の小島の崎で約束する私の気持ちは
※匂宮と浮舟は小舟に乗り、
対岸に渡る途中で橘の小島を見て和歌を詠み合った、
橘の 小島の色は 変はらじを この浮舟ぞ 行方知られぬ
浮舟 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
橘の小島の色は変わらなくても
この浮舟のような私はどこへ流れて行くのでしょう
峰の雪 みぎはの氷 踏み分けて 君にぞ惑ふ 道は惑はず
匂宮 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
峰の雪や水際の氷を踏み分けて
あなたに心は迷いましたが、
京から宇治への道中では迷いません
※昨夜、雪道を踏み分けて宇治まで来たことを
アピールする和歌。
降り乱れ みぎはに凍る 雪よりも 中空にてぞ 我は消ぬべき
浮舟 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
降り乱れて水際で凍っている雪よりもはかなく
私は空の途中で消えてしまうでしょう
眺めやる そなたの雲も 見えぬまで 空さへ暮るる ころのわびしさ
匂宮 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
眺めているそちらの方の雲も見えないくらいに
空までも真っ暗になっている今日この頃の心細さです
※「眺め」「長雨」の掛詞。
匂宮は病に伏し、浮舟は乳母に
監視されているので会うことができない。
さらに長雨が二人の逢瀬を阻む。
水まさる 遠方の里人 いかならむ 晴れぬ長雨に かき暮らすころ
薫 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
川の水が増す宇治の人々は
どのようにお過ごしでしょうか
晴れ間なく長雨が続き物思いに耽っている
今日この頃です
※「をち」(宇治の地名)と「遠方」
「眺め」と「長雨」は掛詞。
里の名を わが身に知れば 山城の 宇治のわたりぞ いとど住み憂き
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
宇治(憂し)という里の名をわが身によそえると
山城の宇治の辺りはますます住みにくいわ
かき暮らし 晴れせぬ峰の 雨雲に 浮きて世をふる 身をもなさばや
浮舟 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
真っ暗になって晴れない峰の雨雲のように
空に浮かんでただよう煙になってしまいたいです
※匂宮の文への返歌。
つれづれと 身を知る雨の 小止まねば 袖さへいとど みかさまさりて
浮舟 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
寂しく我が身の辛さを知らされる雨が
絶え間なく降り続くので
袖までが涙でよりいっそう濡れてしまいます
波越ゆる ころとも知らず 末の松 待つらむとのみ 思ひけるかな
薫 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
心変わりする頃とは知らずに
あなたはいつまでも
待ち続けていらっしゃると思っていましたよ
※薫は、匂宮と浮舟の関係を知ってしまった。
浮舟を責める和歌。
いづくにか 身をば捨てむと 白雲の かからぬ山も 泣く泣くぞ行く
匂宮 (独詠歌)
【現代語訳】
どこに身を捨てようかと思いながら
白雲のかかっていない山がない山道を
泣く泣く帰って行くことだ
※匂宮は宇治へ行ったが、浮舟に
会わせてもらえず京へ帰っていく。
嘆きわび 身をば捨つとも 亡き影に 憂き名流さむ ことをこそ思へ
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
嘆いて思い悩み身を捨てても、亡くなった後に
嫌な噂が流れるのが気にかかることよ
からをだに 憂き世の中に とどめずは いづこをはかと 君も恨みむ
浮舟 ⇒ 匂宮 (返歌)
【現代語訳】
亡骸さえ辛いこの世に残さなかったら
どこがお墓なのかと、あなたもお恨みになりましょう
※匂宮の手紙への返歌。
後にまた あひ見むことを 思はなむ この世の夢に 心惑はで
浮舟 ⇒ 浮舟の母 (返歌)
【現代語訳】
来世で再びお会いすると思いましょう
この世の夢に迷わないで
※「この世」の「こ」には「子」を響かせる。
母の手紙への返歌。
鐘の音の 絶ゆる響きに 音を添へて わが世尽きぬと 君に伝へよ
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
鐘の音が絶えていく響きに、泣き声を添えて
私の命は終わったと母に伝えてください
※この和歌を詠んだ直後、
浮舟は宇治川に身を投げる。
蜻蛉(11首)
忍び音や 君も泣くらむ かひもなき 死出の田長に 心通はば
薫 ⇒ 匂宮 (贈歌)
【現代語訳】
忍び泣くようにほととぎすが鳴いていますが
あなたも泣いていらっしゃいますか
いくら泣いても甲斐のない方にお心を寄せておられるなら
※浮舟の失踪を知り、失意の薫と匂宮の贈答歌。
橘の 薫るあたりは ほととぎす 心してこそ 鳴くべかりけれ
匂宮 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
橘が薫っているところは、ほととぎすよ
気をつけて鳴くものですよ
※「五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする」
(古今集夏)を踏まえた和歌。
「橘が香る薫大将の近くでホトトギスが泣くと、
薫大将は昔の人(浮舟)のことを思い
私(匂宮)を恨むから、気を遣ってくれ」の意。
我もまた 憂き古里を 荒れはてば 誰れ宿り木の 蔭をしのばむ
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
私もまた、嫌なこの宇治の里を離れて
荒れてしまったら
誰がこの山荘のことを思い出すだろうか
※「八の宮、大君、中君、浮舟に続いて
自分までが宇治を捨ててしまったら…」の意。
あはれ知る 心は人に おくれねど 数ならぬ身に 消えつつぞ経る
小宰相の君 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
悲しみを知る心は他人には負けませんが
人の数にも入らない身分ゆえに
遠慮して消え入りそうに過ごしております
※浮舟を失い物思いに沈む薫に贈った和歌。
自分が薫を思う気持ちの深さをアピールした。
常なしと ここら世を見る 憂き身だに 人の知るまで 嘆きやはする
薫 ⇒ 小宰相の君 (返歌)
【現代語訳】
無常の世を長年見て来た辛い我が身でさえ
人に気づかれるほどには嘆いていないつもりです
※浮舟だけを強く思っているのではない
という反発の意を含む和歌。
荻の葉に 露吹き結ぶ 秋風も 夕べぞわきて 身にはしみける
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
荻の葉に露が置いている上を吹く秋風も
夕方には格別に身にしみて感じられる
※薫は正室の女二の宮がいながら、
女一の宮を恋い慕っている。
女一の宮の筆跡を見た薫は
胸をときめかす一方で女二の宮に
見劣りを感じた。
「秋風」に「飽き」をかけて
気持ちを表現している。
女郎花 乱るる野辺に 混じるとも 露のあだ名を 我にかけめや
薫 ⇒ 中将の御許 (贈歌)
【現代語訳】
女郎花が咲き乱れている野辺に入り込んでも
浮気者だという噂を私に立てられるものでしょうか
※「女郎花多かる野辺に宿りせばあやなくあだの名をや立ちなむ」
(女がたくさんいるところに長いしたら浮気者だと言われるな)
(古今集秋上)を踏まえた和歌。
女房たちへの戯れの和歌。
花といへば 名こそあだなれ 女郎花 なべての露に 乱れやはする
中将の御許 ⇒ 薫 (返歌)
【現代語訳】
花と申しますと名前からして
浮ついたように聞こえますが
女郎花はそこらの露になびいたりしません
※薫の贈歌と同じく
古今集の和歌を踏まえた和歌。
旅寝して なほこころみよ 女郎花 盛りの色に 移り移らず
弁の御許 ⇒ 薫 (贈歌)
【現代語訳】
旅寝して試してみなさいよ
女郎花の盛りの色にあなたの心が移るか移らないか
※薫への挑発の和歌。
宿貸さば 一夜は寝なむ おほかたの 花に移らぬ 心なりとも
薫 ⇒ 弁の御許 (返歌)
【現代語訳】
お宿を貸してくださるなら、一晩は泊まってみましょう
ありふれた花には心移しませんけれど
※弁の御許の挑発に応えた和歌。
ありと見て 手にはとられず 見ればまた 行方も知らず 消えし蜻蛉
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
そこにいると見えても、手に取ることはできない
見えたと思うとまた行く方知れずになり
消えてしまった蜻蛉(かげろう)だ
※八の宮の三姉妹との縁のはかなさを
詠んだ和歌。
蜻蛉(かげろう)はトンボに似た昆虫で
風に舞うように弱々しく飛ぶ上に
成虫になって1日で命を終えることから、
はかなさの象徴とされた。
手習(28首)
身を投げし 涙の川の 早き瀬を しがらみかけて 誰れか止めし
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
涙を流しつつ身を投げた宇治川の早い流れを
堰き止めて誰が私を救ってくださったのでしょう
※宇治川に身を投げた浮舟は、
岸に流れ着いていたところを横川の僧都に助けられた。
我かくて 憂き世の中に めぐるとも 誰れかは知らむ 月の都に
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
私がこのように辛い世の中に生きていると
誰が知ろうか、あの月が照らしている都の人で
※「めぐる」「月」縁語。
「月の都」は『竹取物語』のかぐや姫を連想させる。
あだし野の 風になびくな 女郎花 我しめ結はむ 道遠くとも
中将 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
浮気な男に靡いたりせず
私のものになってください
道は遠いけれども
※女郎花は浮舟を喩える。
僧都の妹尼君の亡き娘の婿・中将は
浮舟に懸想する。
移し植ゑて 思ひ乱れぬ 女郎花 憂き世を背く 草の庵に
尼君 ⇒ 中将 (返歌)
【現代語訳】
ここに移ってきて思い悩んでいる女郎花です
辛い世の中を逃れたこの草庵で
※浮舟が返歌しないため、
僧都の妹尼君が代作した。
松虫の 声を訪ねて 来つれども また萩原の 露に惑ひぬ
中将 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
松虫の声を訪ねて来ましたが
再び萩原の露に迷ってしまいました
※「松虫」「待つ」は掛詞。
「萩原」は浮舟を喩える。
秋の野の 露分け来たる 狩衣 葎茂れる 宿にかこつな
尼君 ⇒ 中将 (返歌)
【現代語訳】
秋の野原の露を分けて来たせいで濡れた狩衣を
雑草の茂ったわが宿のせいにしないでください
※浮舟が返歌をしないので、尼君が代作した。
深き夜の 月をあはれと 見ぬ人や 山の端近き 宿に泊らぬ
尼君 ⇒ 中将 (贈歌)
【現代語訳】
夜更けの月をしみじみと御覧にならない方よ
山の端に近いこの宿に泊まっていきませんか
※「月」は浮舟を喩える。
中将の求婚を承諾する和歌。
山の端に 入るまで月を 眺め見む 閨の板間も しるしありやと
中将 ⇒ 尼君 (返歌)
【現代語訳】
山の端に隠れるまで月を眺めましょう
寝所の床に月光が射しこむかも知れませんので
※浮舟に寝所に近づきたい気持ちを詠む。
忘られぬ 昔のことも 笛竹の つらきふしにも 音ぞ泣かれける
中将 ⇒ 尼君 (贈歌)
【現代語訳】
忘れられない亡き妻のことや
冷たい人のことを思うにつけて
声をあげて泣いてしまいました
※「事」「琴」の掛詞。
「琴」「笛」「音」、
「竹」「節」「根」は縁語。
「昔」は亡き妻を、「つらきふし」は浮舟を指す。
笛の音に 昔のことも 偲ばれて 帰りしほども 袖ぞ濡れにし
尼君 ⇒ 中将 (返歌)
【現代語訳】
笛の音に昔のことが思い出されまして
あなたがお帰りになった後も涙で袖が濡れました
はかなくて 世に古川の 憂き瀬には 尋ねも行かじ 二本の杉
浮舟 ⇒ 尼君 (贈歌)
【現代語訳】
はかないまま
この世で辛い思いをして生きていますので
あの二本の杉のある古川には訪ねて行きません
※浮舟は尼君に長谷寺詣でに誘われるが断る。
長谷寺には二本の杉がある。
古川の 杉のもとだち 知らねども 過ぎにし人に よそへてぞ見る
尼君 ⇒ 浮舟 (返歌)
【現代語訳】
あなたが会いたいと思っている人のことは知りませんが
私はあなたを亡くなった娘と思っております
※「古川の杉」は浮舟を喩える。
「過ぎにし人」は亡き娘を指す。
心には 秋の夕べを 分かねども 眺むる袖に 露ぞ乱るる
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
私には秋の情趣も分からないけれど
物思いに沈む私の袖に涙の露がこぼれ落ちる
山里の 秋の夜深き あはれをも もの思ふ人は 思ひこそ知れ
中将 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
山里の秋の夜更けの情趣を
物思いなさる方はご存知でしょう
憂きものと 思ひも知らで 過ぐす身を もの思ふ人と 人は知りけり
浮舟 ⇒ 中将 (返歌)
【現代語訳】
情けない身の上とも分からずに暮らしている私を
物思いに沈んでいると他人が分かるのですね
※「自分では物思いしているかどうか
わからないのに、あなたは私が
物思いしているとわかるのですね」の意。
なきものに 身をも人をも 思ひつつ 捨ててし世をぞ さらに捨てつる
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
亡くなってしまったものだと
我が身をも人をも思いながら
いちど捨てた世をさらにまた捨てたのだ
※浮舟は出家した。
「入水して一度捨てた世を、
出家によってさらに捨てた」の意。
限りぞと 思ひなりにし 世の中を 返す返すも 背きぬるかな
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
これが最期と思って捨てた世の中を
繰り返し背くことになったことよ
岸遠く 漕ぎ離るらむ 海人舟に 乗り遅れじと 急がるるかな
中将 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
岸から遠くに漕ぎ離れて行く海人舟に
私も乗り後れまいと急ぐような気がします
※「岸遠く」は「此岸から彼岸へ」の意。
「海人」「尼」は掛詞。
「乗り」に「法」、「急ぐ」に「磯」を響かせる。
「岸」「漕ぐ」「海人舟」「乗り」は縁語。
「出家した浮舟に、自分も遅れたくない気がする」の意。
心こそ 憂き世の岸を 離るれど 行方も知らぬ 海人の浮木を
浮舟 ⇒ 中将 (返歌)
【現代語訳】
心は辛い世の中を離れたが
行く方もわからず漂っている海人の浮木です
※「海人」「尼」は掛詞。
木枯らしの 吹きにし山の 麓には 立ち隠すべき 蔭だにぞなき
尼君 ⇒ 中将 (贈歌)
【現代語訳】
木枯らしが吹いた山の麓では
もう姿を隠す場所さえありません
※「浮舟が出家してしまったので、
あなたを泊める場所がありません」の意。
待つ人も あらじと思ふ 山里の 梢を見つつ なほぞ過ぎ憂き
中将 ⇒ 尼君 (返歌)
【現代語訳】
待っている人もいないと思う山里の
樹木の先を見ながら、やはり素通りしにくいです
※「あらじ」に「嵐」を響かせる。
おほかたの 世を背きける 君なれど 厭ふによせて 身こそつらけれ
中将 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
俗世間をお捨てになったあなたですが
私を避けていらっしゃるにつけ、辛く感じられます
かきくらす 野山の雪を 眺めても 降りにしことぞ 今日も悲しき
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
降りしきる野山の雪を眺めていても
昔のことが今日も悲しく思い出される
※過去の匂宮、薫との出来事を思う和歌。
山里の 雪間の若菜 摘みはやし なほ生ひ先の 頼まるるかな
尼君 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
山里の雪の間に生えた若菜を摘んで祝って
やはりあなたの将来に期待してしまいます
雪深き 野辺の若菜も 今よりは 君がためにぞ 年も摘むべき
浮舟 ⇒ 尼君 (返歌)
【現代語訳】
雪の深い野辺の若菜も今日からは
あなたのために長寿を祈って摘みましょう
袖触れし 人こそ見えね 花の香の それかと匂ふ 春のあけぼの
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
袖を触れ合った人の姿は見えないが
紅梅の香があの人の香と同じように匂っている
春の夜明けだこと
※匂宮のことを思う和歌。
見し人は 影も止まらぬ 水の上に 落ち添ふ涙 いとどせきあへず
薫 (独詠歌)
【現代語訳】
あの人が影形もとどめず身を投げた川の水面に
落ちる私の涙がますます止めがたいことだ
※薫が宇治の邸の柱に書きつけた和歌。
尼衣 変はれる身にや ありし世の 形見に袖を かけて偲ばむ
浮舟 (独詠歌)
【現代語訳】
尼衣に変わってしまった身で
昔の形見として華やかな衣装を着て
今さら昔を偲ぼうか
夢浮橋(1首)
法の師と 尋ぬる道を しるべにて 思はぬ山に 踏み惑ふかな
薫 ⇒ 浮舟 (贈歌)
【現代語訳】
仏法の師と思って僧都を道しるべにして
訪ねて来た道ですが
思いがけない山道に迷い込んでしまったことよ
※「法の師」は横川の僧都
「思はぬ山」は浮舟への恋を指す。
———————————————–
源氏物語の和歌は全795首。
その中でも有名な和歌を13首、こちらの記事で
厳選して紹介しています。


恋・花・月・春夏秋冬に分けて
代表的な和歌も解説しました。