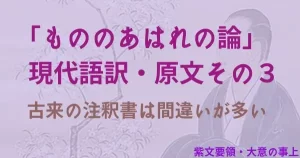この記事では、
本居宣長:もののあはれ論(紫文要領)の
原文・現代語訳を掲載しています。
★大意の事 上
1.物語とは「もののあはれ」を知らせるもの
2.蛍の巻の物語論から紫式部の意図を読み取る
3.古来の注釈書は間違いが多い
4.『源氏物語』の善悪の基準は「もののあはれ」
5.女は「もののあはれ」を知った上でほどよい態度をとるべき
6.「もののあはれ」についての詳述
★大意の事 下
7.恋愛は「もののあはれ」が深い ←この記事
8.「もののあはれ」と浮気っぽいのとは別物
9.『源氏物語』は教訓の物語ではない
10.光源氏と藤壺の密通を書いた紫式部の意図
11.人の真実の感情を知ることが「もののあはれ」を知ること
もののあはれは、恋において最も深い
【現代語訳】
答えて言うことには、前述した通り、人間の感情が強く発揮される点では、恋愛に勝るものはない。だから、恋愛に関しては、人の心が深く感じて、もののあはれを感じることが他の何よりも勝っている。ゆえに、神話の時代から今に至るまで、詠まれた和歌には恋愛の歌ばかりが多く、また優れた作品も恋の歌に多い。これは、(恋愛の)もののあはれが極めて深いからである。物語は、もののあはれを書き集めて、読む人にもののあはれを理解させるものだから、この恋愛の方面のこと以外では、人の感情が深く繊細であることや、もののあはれは抑えていられず深く人の心をとらえるという点の詳細な意味は、表現しづらい。だから、恋する人が色々に思う心の、それぞれにしみじみとした情緒を、非常に繊細に書き記して、読者にもののあはれを伝えているのである。『源氏物語』より後の時代の和歌だが、藤原俊成は「恋をしなければ人は心がないようなものだろう。もののあはれも、恋によって知るのである」とお詠みになった。この和歌によって理解しなければならない。恋愛でなくては、もののあはれの非常に我慢できない点の意味は理解することができないのだ。
【原文】
答へて云はく、前にもいへるごとく、人情の深くかかること、好色にまさるはなし。さればその筋につきては人の心深く感じて、物の哀れを知ること何よりもまされり。ゆゑに神代より今にいたるまで、よみ出づる歌に恋の歌のみ多く、またすぐれたるも恋の歌に多し。これ、物の哀れいたりて深きゆゑなり。物語は物の哀れを書き集めて、見る人に物の哀れを知らするものなるに、この好色の筋ならでは、人情の深くこまやかなること、物の哀れの忍びがたくねんごろなるところのくはしき意味は、書き出だしがたし。ゆゑに恋する人のさまざま思ふ心の、とりどりにあはれなる趣きを、いともこまやかに書き記して、読む人に物の哀れを知らせたるなり。後のことなれど、俊成三位の「恋せずは人は心もなからまし物の哀れもこれよりぞ知る」 とよみ給へる、この歌にて心得べし。恋ならでは、物の哀れのいたりて忍びがたきところの意味は知るべからず。
桐壺帝の恋
【現代語訳】
その我慢できない感情の様子は『源氏物語』の作品中に頻繁に見えるけれど、さらに少し引用して説明するならば、まず最初に「桐壺」の巻において、桐壺帝のことが以下のように書かれている。
決して少しも人の心を傷つけたようなことはあるまいと思うのに、ただこの人との縁が原因で、たくさんの恨みを負うなずのない人の恨みをもかって(以下略)
(桐壺帝は)少しも「人の心を傷つけたことはあるまい」とお思いになるけれど、恋愛はそこがうまくいかないことがあると理解しなければならない。「人の心を傷つけたことはあるまい」とお思いになったその証拠は、「翌年の春に、東宮がお決まりになる折にも、第一皇子を差し置いて、光君を東宮にしたいと思し召されたが、ご後見すべき人もなく、また世間が承知するはずもないことだったので、かえって危険であるとお差し控えになって、顔色にもお出しあそばされず」という記述から理解できる。このように、他の事は世間が承知するはずもないと遠慮なさる。天皇の御心としては、滅多にないものである。このように賢明な帝でいらっしゃるが、恋愛は感情を抑えられないところがあるもので、桐壺の更衣のことについては乱れたことが多い。その抑えられないお気持ちが伝わってきて、非常にしみじみと胸が打たれる。もののあはれが深いのは、この部分である。
また、次のように書いてある。
(桐壺帝は、桐壺の更衣のことに関しては)誰の非難に対しても遠慮なさらず、後世の語り草にもなってしまいそうなお扱いぶりである。(中略)しだいに国中でも困ったことだと、人々の悩みの種となって、
また次のように書いてある。
(桐壺帝は)多くの人の非難や嫉妬に対して遠慮なさらず、桐壺の更衣のことに関しては、理性をお失いになり、今は今で、このように政治をお執りになることも、お捨てになったようになって行くのは(以下略)
前に引用した「世間が承知するはずもない事」を遠慮なさったのと、今引用した文とを合わせて読んで、恋愛の感情が我慢しづらいものであることを理解しなさい。
【原文】
その忍びがたき事のさまは巻々に見えたれど、なほ少々引きていはば、まづ桐壺の巻に帝の御事を書きて云はく、
よにいささかも人の心をまげたる事はあらじと思ふを、ただこの人ゆゑにてあまたさるまじき人の恨みを負ひ云々、
いささかの事も「まげたる事はあらじ」と思し召す御心なれども、恋にはそこの忍びがたきところのあることを知るべし。「人の心をまげたる事はあらじ」と思し召したるそのしるしは、「明くる年の春、坊定まり給ふにも、いと引き越さまほしう思せど、御後見すべき人もなく、また世のうけひくまじき事なれば、なかなかあやふく思し憚かりて、色にも出ださせ給はず」といへるにて知るべし。かやうに他の事は世のうけひくまじきを憚からせ給ふ。 天子の御心にはありがたきものなり。かくのごとき賢君にてましませども、好色は人情の忍びがたきところあるものにて、更衣のことにつきては乱れたる御事多し。その忍びられぬ御心知られて、いとあはれ深し。
物の哀れの深きはここなり。
また云はく、
人のそしりをもえ憚からせ給はず、世のためしにもなりぬべき御もてなしなり云々。 やうやう天の下にもあぢきなう人のもてなやみぐさになりて、
また云はく、
そこらの人のそしり恨みをも憚からせ給はず、この御事に触れたる事をば、道理をも失はせ給ひ、今はたかく世の中の事をも思し棄てたるやうになり行くは云々、
前の「世のうけひくまじき事」を憚からせ給ふと、これらの文とを合せ見て、恋の哀れの忍びがたきことを知れ。
源氏の恋
【現代語訳】
「葵」の巻には、次のように書いてある。
数年来かわいいとお思い申していたのは、片端にも当たらないくらいだ。(中略)それから後は、内裏にも院にも、ちょっとご参内なさる折でさえ、落ち着いていられず、(中略)「妙な気持ちだな」と、自分でもお思いになられる。
これは、源氏の君が、紫の上と初めて男女の契りを交わした時のことである。これによって恋愛の感情がこの上なく深いことを理解しなければならない。初夜を終えた後の心と比べたら、それより前の(紫の上への)一般的な感情は「片端にも当たらない」ということだ。また、自分のことながら不思議だと思うほどに深くお感じになる心を想像しなければならない。
「薄雲」の巻には次のように書いてある。
「このように無理な恋に胸がいっぱいになる癖が、いまも残っていたことよ」と、自分自身反省せずにはいらっしゃれない。
これは、藤壺の宮との密通を冷泉院がお聞きになった後に、その事を恐ろしいとお思いになったけれど、また懲りずに秋好中宮に思いをお寄せになっている源氏の気持ちである。
「胡蝶」の巻には次のような記述が見られる。
恋の山路では孔子も転ぶ(以下略)
これは、世間で言われていることわざなのであろう。恋に迷わない人はいないということを強調して表現しようとして、聖人とされている孔子も恋の山路では転ぶ、ということである。『河海抄』の引用歌「恋の山路の深さゆえに、そこへ入り込む人の誰もが迷ってしまうのだろう」
「若菜上」の巻には、次のように書いてある。
「とんでもなくけしからぬ事」と、ひどく自制なさるのだが、どうすることもできないのであった。
これは、源氏の君が朧月夜の君を思う気持ちである。けしからぬ事だと強いて自制しても、抑えられない気持ちは、自分の思うままにはならないのだ。
【原文】
葵の巻に云はく、
年ごろあはれと思ひ聞えつるは、片はしにもあらざりけり云々。 かくて後は、内にも院にもあからさまに参り給へるほどだにしづ心なく云々、あやしの心やとわれながら思さる。
これ、源氏の君、紫の上に新枕かはし給ひし時のことなり。これをもて恋の哀れのこよなく深きことを知るべし。新枕かはして後の心にくらぶれば、それより前の大方の哀れは「片はしにもあらず」となり。また、われながらあやしと思ふほどに深く思ひしみ給へる情を思ふべし。
薄雲の巻に云はく、
かうあながちなる事に胸ふたがる癖のなほありけるよと、われながら思し知らる。
これ、薄雲の女院と密通の御事を冷泉院の知ろし召して後に、かの事を恐ろしく思ひ給ふが、またこりずまに秋好む中宮に心をかけ給ひての源氏の心なり。
胡蝶の巻に云はく、
恋の山には孔子の倒れ云々、
これ、世の諺なるべし。恋には迷はぬ人なきといふことを強くいはむとて、聖人とある孔子も恋の山には倒るる、となり。『河海抄』引歌、「いかばかり恋の山路の深ければ入りと入りぬる人惑ふらん」。
若菜の上の巻に云はく、
いとあるまじき事といみじく思し返すにも、かなはざりけり。
これ、源氏の君、朧月夜の君を思ふ心なり。あるまじき事といみじく思し返しても忍びがたき心は、わが心にもかなひがたし。
夕霧の恋
【現代語訳】
「夕霧」の巻には、次のように書いてある。
他人の身の上の事などで、このような恋愛沙汰に夢中になってしまうのは、けしからぬことであり、正気とは思えないことのように見たり聞いたりしていたが、自分の事となると、なるほどまことに我慢できないものであるなあ。不思議だ。どうして、こんなに思うのだろうと、反省なさるが、思うにまかせない。
恋をすると夢中になってしまうことを、他人の身の上の事として見たり聞いたりする時は、正気とも思えず、気に食わないと思っていたが、今、自分が恋をしてみたら、なるほど、確かに我慢しがたい事であると、自分の体験をもって納得したのである。夕霧の大将のことだ。『源氏物語』全体の恋は、この心で読むとよい。
また、次のような記述がある。
なるほど、このような方面のことには、人の意見にも、自分の心にも従えないものだということが分かりました。(以下略)
これも夕霧の大将の言葉である。「げに(なるほど)」とは、世間で言われていることが、自分の身に思い当たった時の言葉だ。恋愛ばかりは、他人の意見にも、自分の心にも従わないものと世間で言われているのは、本当にその通りだと思い当たったのである。あの夕霧ほどの真面目な人であってさえ、(恋愛においては)この通りだ。恋の感情に関わらないでいることは、どんな人でも難しいと理解しなければならない。
ところで、上記に引用した『源氏物語』作中の文章に、「妙な気持ちだなと、自分でもお思いになられる。」。「ひどく自制なさるのだが、どうすることもできないのであった」、「反省なさるが、思うにまかせない」、「自分の心にも従えない」なとと言っているのを、よくよく吟味しなければならない。これらの言葉によって、恋愛感情が他のあらゆる感情よりも深いということ、我慢しようとしても我慢できないということ、誰も無縁ではいられないことを理解しなければならない。そうであれば、もののあはれを知ろうとするときに、恋愛よりも深いものはない。
【原文】
夕霧の巻に云はく、
人の上などにてかやうの好き心思ひ入らるるは、もどかしううつし心ならぬ事に見聞きしかど、身の上にてはげにいと堪へがたかるべきわざなりけり。あやしや、などかうしも思ふらんと、思ひ返し給へど、えしもかなはず。
恋すると思ひ入らるるを、人の上に見たり聞きたりする時は、うつし心とも思はれず、もどかしう思ひしが、今わが身の上に恋してみれば、げにいかにも堪へがたかるべき事なりと、わが身に思ひ当るなり。夕霧の大将のことなり。一部の恋はこの心にて見るべし。
また云はく、
げにかやうの筋にてこそ、人の諌めをもみづからの心にもしたがはぬやうに侍りけれ云々。
これも夕霧の大将の詞なり。「げに」とは、世間にていふ事をわが身に思ひ当れる詞なり。恋の道ばかりは人の諫めにもみづからの心にもしたがはぬ物と世にいふは、まことにさることなりと思ひ当るなり。夕霧はさしものまめ人なるさへかくのごとし。この情の人ごとにまぬかれがたきことを知るべし。
さて上に引ける巻々の詞に、「あやしの心やとわれながら思さる」、「いみじく思し返すにも、かなはざりけり」、「思ひ返し給へど、えしもかなはず」、「みづからの心にもしたがはぬ」などいへるを、よくよく味ふべし。右の詞どもをもて、好色の情の万に過ぎて深きこと、忍ばむとすれど忍びられぬこと、人ごとに離れがたきことを知るべし。されば物の哀れを知ること、恋より深きはなし。
柏木の恋
【現代語訳】
「柏木」の巻に、衛門の督(柏木)が、女三の宮との密通をきっかけとして病気になり、最終的には死んでしまいそうになっている時の和歌に、
もうこれが最期と燃える私の火葬の煙もくすぶって、空に上らずあなたへの思いがなおもこの世に残ることでしょう
女三宮の御返歌、
私も一緒に煙となって消えてしまいたいです。辛いことを思い嘆く悩みを競いながら。
『源氏物語』の中にはたくさんの恋が描かれているが、(柏木の恋は)特にしみじみと胸を打つ。柏木の臨終の描写は感慨深いけれど、中でもこの和歌の贈答は、特にしみじみと胸を打つ。だから、柏木が「この煙の歌の贈答だけが、この世の思い出である」というあたりは、読者はただもう涙がこぼれるばかりである。
【原文】
柏木の巻に、衛門の督、女三の宮の御事によりて病づき、つひにはかなくなりなんとするころの歌に、
今はとて燃えむ煙もむすぼほれ
たえぬ思ひのなほや残らん
宮の御返し、
立ち添ひて消えやしなまし憂きことを
思ひ乱るる煙くらべに
この物語の中あまたの恋の中にも、ことに哀れ深し。衛門の督今はの書きざま哀れ深きが中にも、この贈答はことに哀れ深く見ゆ。さればかの人も「この煙ばかりはこの世の思ひ出でなり」といへるわたり、読む者すずろに涙落ちぬべく覚ゆるなり。
空蝉の恋
【現代語訳】
そうであれば、もののあはれを知る人は、貞節を守る人であっても、機会によって、場合によっては、気持ちを抑えがたいことがあるはずだ。「帚木」の巻に、空蝉の君の気持ちが、以下のように書かれている。
無理に源氏の気持ちを分からないふうを装って無視するのも、どんなにか身の程知らぬ者のようにお思いになるだろうと、(拒否を通そうと)心に決めたものの、胸が痛くて、そうはいってもやはり心が乱れる。(中略)情の無い気にくわない女として、押しとおそうと(後略)
これは、もののあはれを知らないことを、貞節を守る場合であっても、「情が無く気に入らない」といっている。「空蝉」の巻には次の和歌が詠まれている。
空蝉の羽に置く露が木に隠れて見えないように、私も人知れず涙を流しています。
空蝉の君の心遣いは、最初から最後までこの和歌の通りである。もののあはれを知っている様子としては、作者(紫式部)の思いとしても、この空蝉の君の有様を本来の意図として見るべきであろう。藤壺の宮も空蝉の君と同じである。「夕顔」の巻には次のように書かれている。
折にふさわしい和歌を好ましくお詠みになる、(源氏の)様子を拝する人で、少し物の情趣を解せる人は、どうして(源氏を)いい加減にお思い申し上げよう。
「物の心を思ひ知るは(物の情緒を解せる人は)」という部分に注意をしなければならない。
【原文】
されば物の哀れ知る人は、節義を守る人とても、折にふれ事によりては忍びがたきことあるなり。帚木の巻に、空蝉の君の心を書きて云はく、
しひて思ひ知らぬ顔に見消つも、いかにほど知らぬやうに思すらんと、心ながらも胸いたく、さすがに思ひ乱る云々。無心に心づきなくてやみなんと云々。
これ、物の哀れを知らぬことをば、貞節を立つるをさへ「無心に心づきなく」といへり。空蝉の巻の歌に、
空蝉の羽に置く露の木隠れて
忍び忍びに濡るる袖かな
この人の心ばへ、始終かくのごとし。物の哀れを知れるさま、作者の心ばへもこれらをや本意とすべからん。薄雲の女院もこの定なり。夕顔の巻に云はく、
さりぬべきついでの御言の葉もなつかしき御気色を見奉る人の、すこし物の心を思ひ知るは、いかがはおろかに思ひ聞えん云々。
「物の心を思ひ知るは」といふに心をつくべし。
もののあはれを知る人は、恋に理解が深い
【現代語訳】
恋愛は、このように誰も無縁ではいられないものであり、その意義を知っているがゆえに、善い人は他人が恋をするのを強くは非難せず、悪い人は強く非難するのである。「賢木」の巻で、源氏の君と朧月夜の君との密通のことを、弘徽殿の大后と父大臣が非難していらっしゃる場面を読みなさい。父大臣のことを、「まことに性急で意地の悪い方でいらっしゃる」といい、
「我が子ながら(朧月夜の君が)恥ずかしいと思っていられるのだろう」と、これほどの身分の方ならば、お察しなさって遠慮すべきである。しかし、まことに性急で、ゆったりしたところがおありでない大臣で、後先のお考えもなくなって。
といい、
勝手気ままで、胸に納めておくことのできない性格の上に、ますます老人の偏屈さまでお加わりになっていたので、
なとど言っている。また、やはり弘徽殿の大后も、悪人として、ところどころに書かれている。
【原文】
好色はかく人ごとにまぬかれがたきものなれば、その意味を知るゆゑに、よき人は人の恋するをも深くとがめず、悪しき人は深くとがむるなり。賢木の巻に、源氏の君と朧月夜の君と密通のことを弘徽殿の大后と父大臣と悪しくのたまふ所を見よ。父大臣をば「いと急に性なくおはします」といひ、
子ながらも恥づかしと思すらんかしと、さばかりの人は思し憚かるべきぞかし。されどいと急にのどめたるところおはせぬ大臣の、思しもまはさずなりて、
といひ、
思ひのままに、籠めたるところおはせぬ本性に、いとど老いの御ひがみさへ添ひ給ひにたれば、
などいへり。また大后を悪しき人にいへることは、なほ所々に見えたり。
玉鬘に対する源氏の配慮
【現代語訳】
ところで、善い人が恋愛を強く非難しないのは、もののあはれを知っているからである。「胡蝶」の巻には次のように書かれている。
(源氏は)右近をお呼び出になり、「このように手紙を(玉鬘に)差し上げる人については、相手をよく吟味して、返事などさせなさい。浮気っぽく遊び半分の当世風のことで、不都合なことをしでかすのは、男の罪とも言えないのだ。(中略)総じて女が遠慮せず、気持ちのままに、ものの情趣を分かったような顔をして、興あることを知っているというのも、結局はよからぬことに終わるものですが、兵部卿宮や、髭黒の大将は、見境なくいいかげんなことをおっしゃるような方ではありません。また、あまり情を解さないようなのも、あなたに相応しくないことです。この方々(宮や大将)より下の身分の人には、相手の熱心さの度合に応じて、愛情のほどを判断しなさい。熱意のほどをも考えなさい」などと申し上げなさるので(後略)
この文章をよくよく吟味しなければならない。作者の真意は、最初から最後までこの文章の通りである。
【原文】
さてまたよき人の深くとがめぬことは、物の哀れを知るゆゑなり。胡蝶の巻に云はく、
右近召し出でて、「かやうにおとづれ聞えん人をば、人選りしていらへなどはせさせよ。すきずきしうあざれがましき今やうの事の、びんない事し出でなどする、男子のとがにしもあらぬことなり云々。すべて女の物つつみせず、心のままに、物の哀れも知り顔作り、をかしき事をも見知らんなむ、その積りあぢきなかるべきを、宮・大将はおほなおほななほざりごとをうち出で給ふべきにあらず。 またあまり物のほど知らぬやうならんも御有様に違へり。その際より下は、心ざしの趣きにしたがひて哀れをも分き給へ。労をもかぞへ給へ」など聞え給へば云々、
この段をよくよく味ふべし。作者の本意、始終かくのごとし。
源氏に対する桐壺院の配慮
【現代語訳】
「末摘花」の巻には次のように書かれている。
上が、(源氏は)真面目でいらっしゃると、お困りになっていらっしゃるのが(以下略)、
「上」とは桐壺帝のことである。「まめにおはす(真面目でいらっしゃる)」とは、源氏のことである。子どもが真面目なのを親がお悩みになるのは、かなり後の時代のことであるが、兼好法師が、若い男が恋愛に無関心なのを「せっかくの宝石の杯の底が抜けている」と喩えた気持ちと同じである。
【原文】
末摘花の巻に云はく、
上の、まめにおはしますともて悩み聞えさせ給ふこそ云々、
「上」は桐壺の帝なり。 「まめにおはす」とは源氏の御事なり。 子の実法なるを親のもて悩み給ふは、いたく後のことなれど、兼好法師が若き男の色好まぬを「玉の杯の底なき」にたとへし心ばへなり。
夕霧に対する源氏の配慮
【現代語訳】
「梅枝」の巻には次のように書かれている。
このようなことは、恐れ多い父帝のご教訓でさえ従おうという気にもならなかったのだから、口をさしはさみにくいが(後略)、
これは源氏の君が、夕霧の大将に対して教え諭した言葉である。「このようなこと」とは恋愛の方面である。「恐れ多いご教訓」とは、昔、桐壺帝が源氏に教訓しなさったことである。この、源氏が夕霧に教訓なさった言葉は、文章が長い。すべて恋愛を注意なさっている。子どもを注意するのは、当然そうするはずのことである。しかし、このように「私も恐れ多い父の教訓に従おうという気にならなかったのだから、今も恋愛の方面のことはあれこれと口出しするのは嫌なのだが」とおっしゃるのは、もののあはれを知っている人の言葉であり、寛容なものである。総じて若い時は誰でも恋愛の道とは無縁でいられなく、やむをえない間違いもあるものだから、それを年をとって落ち着いた気持ちをもって、若い人の浮気っぽいことを非難するべきではないが、ということだ。
「薄雲」の巻には次のように書かれている。
これはまことに不都合な恋だ。恐ろしく罪深いことは多くあったろうが、昔の好色は、思慮の浅いころの過ちであったから、仏や神もお許しになったことだろう(以下略)。
源氏の君の心の声である。「これは」とは、秋好中宮に恋をしていることだ。「恐ろしく罪深いこと」とは、昔、藤壺の宮と密通をなさったことを、今となっては恐ろしく、罪深くお思いになっているのだ。けれど、それは若い頃の過ちだったので、「仏も神もお許しになただろう」ということだ。誰でも年老いれば若い人の恋愛を強く注意するけれど、若い頃は、恋愛の道には気持ちを抑えられない一面があって、間違うことがある。年をとっても、感情は同じであるが、思慮深くなるので、抑えられない気持ちを無理に押さえつける一面がある。今、源氏が秋好中宮を思う気持ちは、「不都合な恋」と我慢なさるようなものだ。だけれど、その上にやはり我慢できないこともまたある。だから源氏は、この後にもさらに朧月夜の君との密通を継続している。その密通の場面の記述として、「とんでもなくけしからぬ事と、ひどく自制なさるのだが、どうすることもできないのであった。」と(「若菜上」の一文。前に引用した)と書かれている。であれば、その自制できないもののあはれを知る人は、他人の恋も強くは非難しない。
「夕霧」の巻には次のように書かれている。
(源氏は)あの事件をお聞きになっていらっしゃったが、どうして知っている顔をする必要があるかと思いになって、ただじっと(夕霧の)顔を窺っていらっしゃると、「実に素晴らしく美しくて、ちょうど今こそ一段と成長なさった絶頂の時期のようだ。あのような浮気事をなさっても、人が非難するようなこともなさっていない。鬼神も罪を許すに違いなく、人目に立ってどことなく清らかで、若々しく今を盛りに美しさをふりまいていらっしゃる。何の分別もない若者ではいらっしゃらず、欠点もなく成人なさっていることから起きた、当然のことなのだ。女として、どうして素晴らしいと思わないでいられようか。鏡を見ても、どうして心奢らずにいられようか」と、ご自分の子どもながらも、そうお思いになる。
「あの事件」とは、夕霧と落葉の宮のことである。「顔を窺っていらっしゃる」とは、源氏が夕霧をじっくりとご覧になっていることである。前の教訓の際には恋愛を強く注意なさったが、心の中ではこのように、「当然のことだ」と思っていらっしゃるのだ。もののあはれを知る人は、このようなものである。
【原文】
梅枝の巻に云はく、
かやうの事はかしこき御教へにだにしたがふべくも覚えざりしかば、言まぜまうけれども云々、
これは源氏の君の、夕霧の大将へ教訓の詞なり。「かやうの事」とは好色の筋なり。 「かしこき御教へ」は、むかし父帝の源氏へ教訓し給ひし事なり。さてこの夕霧へ教訓の御詞、その文長し。みな好色を戒め給へり。子を訓ふる、さもあるべきことなり。しかるにかやうに 「われもかしこき父の教訓にもしたがふべくも覚えざりしことなれば、今もこの筋の事はかれこれと詞をまぜていはむことは憂けれども」とのたまへるは、すべて若き時は誰とてもこの筋は離れがたく、えさらぬ過ちもあるものなれば、それを年たけてをさまりたる心もて、若き人のすきずきしきを難ずべきにはあらねど、とのたまへるは、物の哀れを知りたる御詞、ゆるやかなるものなり。
薄雲の巻に云はく、
これはいと似げなき事なり。恐ろしう罪深き方は多くまさりけめど、古への好きは、思ひやり少なきほどの過ちに仏神も許し給ひけむ云々。
源氏の君の心なり。「これは」とは、秋好む中宮に思ひをかくることなり。「恐ろしう罪深き方」とは、むかし薄雲の女院を蒸し奉り給ひしことを、恐ろしう罪深く今は思し召すなり。されどそれは若気の過ちなりしかば、「仏も神も許し給ひけむ」となり。誰も老いては若き人の好色を強く戒むれども、若きほどは、この筋には忍びがたき方のありて、過つことあるなり。年たけても心は同じことにても、思ひやりが深くなるゆゑに、忍びがたきところをもしひて忍ぶ方あり。いま源氏の秋好む中宮を思ふ心は、「似げなき事」と忍び給ふがごとし。されどもその上になほ忍びぬこともまたあるなり。ゆゑに源氏の、この後にもなほ朧月夜に密通は絶えざりしなり。その所の詞に、「いとあるまじき事といみじく思し返すにも、かなはざりけり」と(若菜の上に見ゆ。前に引く) いへり。さればその忍びぬところの物の哀れを知る人は、人をも深くとがめず。
夕霧の巻に云はく、
かの事は聞し召したれど、何かは聞き顔にもと思いて、ただうちまもり給へるに、 「いとめでたく清らに、このごろこそねびまさり給へる御盛りなめれ。さるさまの好事をし給ふとも、人のもどくべき様もし給はず。鬼神も罪許しつべく、あざやかに物清げに、若う盛りに匂ひを散らし給へり。 物思ひ知らぬ若人のほどにはたおはせず、かたほなる所なう、ねびととのほり給へる理りぞかし。女にてなどかめでざらん、鏡を見てもなどか驕らざらん」と、わが子ながらも思す。
「かの事」とは、夕霧と落葉の宮の御事なり。「うちまもり給ふ」は、夕霧を源氏のつくづくと見給ふなり。前に教訓の詞には好色を強く戒め給へども、心の内にはかやうに、理りぞと思し召すなり。 物の哀れ知る人はかくのごとし。
源氏に対する朱雀帝の配慮
【現代語訳】
「賢木」の巻には次のように書かれている。
尚侍の君(朧月夜の君)のことも、依然として関係が切れていないようにお聞きになって、それらしい様子を御覧になる折もあるが、「いやいや、今に始まったことならばともかく、前から続いていたことなのだ。そのように心を通じ合っても、おかしくはない二人の仲なのだ」と、しいてそうお考えになって、お咎めにならないのであった。
「尚侍の君のこと」とは、源氏と朧月夜の君との密通のことだ。朱雀帝は二人の関係が途絶えていないとお聞きになり、またそれらしい様子をご覧になってのお気持ちである。
【原文】
賢木の巻に云はく、
内侍の君の御事もなほ絶えぬさまに聞し召し、気色御覧ずる折もあれど、何かは今始めたることならばこそあらめ、ありそめにける事なれば、さも心かはさむに、似げなかるまじき人のあはひなりかしとぞ思しなして、とがめさせ給はざりける。
「内侍の君の御事」とは、源氏と朧月夜の内侍の督と密通のことなり。それを朱雀院の絶えぬさまに聞し召し、また気色を御覧じての御心なり。
柏木に対する源氏の配慮
【現代語訳】
「若菜下」の巻には次のように書かれている。
六条院(源氏)も(柏木の病気を)「まことに残念なことだ」とお嘆きになって、お見舞いを頻繁に丁重に父大臣にも差し上げなさる。
これは、柏木が病気におかかりになったのを、(源氏が)このように残念にお思いになるのである。
「柏木」の巻には次のように書かれている。
「(柏木の)ご両親が、せめて子供だけでも残してくれていたらと、お泣きになっているのに、(薫を)見せることもできず、(柏木は)誰にも知られずはかない形見のこの子だけを残して、あれほど高い望みをもって、優れていた身を、自分から滅ぼしてしまったことよ」と、(源氏は)しみじみと残念なので、けしからぬと思う気持ちも思い直されて、つい涙がおこぼれになった。
これは、源氏の君が薫を見て、亡くなった柏木のことをお思いになる気持ちである。「自分から身を滅ぼす」ことを、もののあはれを知らない人はかえって非難するところであるが、逆に(妻に密通された源氏が)いっそうしみじみと残念にお思いになる。このお気持ちは、もののあはれを知っているからである。「けしからぬと思う気持ちも思い直されて、つい涙がおこぼれになった」といっているのを、じっくりと吟味して、もののあはれを感じなければならない。
また次のような記述がある。
六条院(源氏)は、まして気の毒にとお思い出しになることが、月日の経つにつれて多くなっていった。
これも、(源氏は)柏木がお亡くなりになったことを思い出しているのだ。
「横笛」の巻には次のように書かれている。
故権大納言があっけなくお亡くなりになった悲しさを、いつまでも残念なことに、恋い偲びなさる方々が多かった。六条院(源氏)も、特別の関係がなくてさえ、世間に人望のある人が亡くなるのは、惜しみなさるご性格なので、なおさらのこと、この人は、朝夕に親しくいつも参上して親しみ、誰よりもお心を掛けていらっしゃったので、けしからぬと、お思い出しなさることはありながら、哀悼の気持ちは強く、何かにつけてお思い出しになる。ご一周忌にも、誦経などを、特別におさせになる。何も知らない無邪気な幼い子(薫)のご様子をご覧になるにつけても、何といってもやはり不憫でならないので、心の中でひそかに、さらに志立てられて、黄金百両を(薫の分として)別にお布施あそばすのであった。
善い人のもののあはれを知っている様子を想像するとよい。金百両を、(源氏の分とは)別に薫の志として誦経のお布施になさるのは、感動の涙で袖が濡れるばかりである。
「鈴虫」の巻には次のように書かれている。
お琴類を合奏なさって、興が乗ってきたころに、「月を見る夜は、いつでももののあわれを誘うけれど、中でも、今夜の鮮やかな月の色には、なるほどやはり、この世の後の世界までが、いろいろと想像されますよ。故大納言(柏木)を、いつの折にも、亡くなった人だと思うと、いっそう思い出されることが多く、公私につけて事あるごとに物の栄えがなくなった感じがする。花や鳥の色にも音にも、(柏木は)風情を理解して、話相手として、大変に優れていたのだったが」などと(源氏が)お口に出されて、ご自身でも合奏なさる琴の音につけても、お袖を濡らしなさった。御簾の中でも(女三の宮が)耳を止めてお聴きになって入るだろうと、片一方のお心ではお思いになりながら、このような管弦のお遊びの折には、まずは恋しく(以下略)
楽器の音と月とは、特に人を感動させるもので、(源氏は)今、柏木のことを思い出しているのだ。
これらを見なさい。善い人は、もののあはれを知っているがために、恋愛の抑えられない感情を想像して、他人を強く非難しない。特に、朱雀院が源氏を非難なさらないのと、源氏が柏木をしみじみと残念にお思いになるのとは、極めてもののあはれを深く知っているでなくては、とてもこのようにはいかないことである。柏木のことは、源氏の君さえこのように残念にお思いになるのに、後世になって、『源氏物語』を注釈するといって、これらの話を感慨深いように言わず、逆に教訓にせよというように注釈するのは、なんともののあはれを知らず、心の無い人だろうか。確実に紫式部の意図から外れていることを知らなければならない。恋愛はどんな人であっても無縁ではいられず、抑えられない感情があるものだということを知っていらっしゃるがゆえに、(朱雀院は源氏を)非難なさらず、(源氏は柏木を)しみじみと残念にお思いになるのである。
【原文】
若菜の下の巻に云はく、
六条の院にもいと口惜しきわざなりと思し驚きて、御訪らひにたびたびねんごろに父大臣にも聞え給ふ。
これは、柏木の衛門の督のわづらひ給ふを、かく口惜しく思し召すなり。
柏木の巻に云はく、
親たちの、子だにあれかしと歎い給ふらんにもえ見せず、人知れずはかなき形見ばかりを止め置きて、さばかり思ひあがりおよずけたりし身を、心もて失ひつるよと、あはれに惜しければ、めざましと思ふ心もひき返し、うち泣かれ給ひぬ。
これ、源氏の君の薫を見て、過ぎにし衛門の督のことを思し召す心なり。「心もて身を失ふ」をば、物の哀れ知らぬ人はかへりて憎むことなるを、かへりていよいよ哀れに思し召す御心、物の哀れを知るゆゑなり。 「めざましと思ふ心もひき返し、うち泣かれ給ふ」といへる、よくよく味ひて、物の哀れを知るべし。
また云はく、
六条の院にはましてあはれと思し出づること、月日に添へて多かり。
これも衛門の督の失せ給ひしことを思すなり。
横笛の巻に云はく、
故権大納言のはかなく失せ給ひにし悲しさを、あかず口惜しきものに恋ひしのび給ふ人多かり。六条の院にも、大方につけてだに世に目やすき人の亡くなるをば惜しみ給ふ御心に、ましてこれは朝夕に親しく参りなれつつ、人よりも御心とどめ思したりしかば、いかにぞや思し出づることはありながら、哀れは多く、折々につけてしのび給ふ。御果てにも、誦経などとり分きせさせ給ふ。万も知らず顔にいはけなき御有様を見給ふにも、さすがにいみじくあはれなれば、御心の内にまた心ざし給ひて、黄金百両をなん別にせさせ給ひける。
よき人の物の哀れ知るさまを思ふべし。金百両、別に薫の志として誦経にし給ふは、感涙袖をうるほすばかりなり。
鈴虫の巻に云はく、
御琴どもの声々かき合せて面白きほどに、「月見る宵のいつとても物哀れならぬ折はなき中に、今宵の新たなる月の色には、げになほわが世の外までこそ万思ひ流さるれ。故権大納言、何の折々にも亡きにつけていとどしのばるること多く、公私、物の折節の匂ひ失せたる心地こそすれ。花鳥の色にも音にも思ひわきまへいふかひある方のいとうるさかりしものを」などのたまひ出でて、みづからもかき合せ給ふ御琴の音にも袖ぬらし給ひつ。御簾のうちにも耳とどめてや聞き給ふらんと、片つ方の御心には思しながら、かかる御遊びのほどにはまづ恋しう云々。
物の音と月とはことに人の心を感ぜしむるものにて、今柏木のことを思し出づるなり。
これらを見るべし。よき人は物の哀れを知るゆゑに、好色の忍びがたき情を推量りて、人をも深くとがめず。ことに朱雀院の源氏をとがめ給はぬと、源氏の君の柏木を哀れに思し召すとは、いたりて物の哀れを深く知る人にあらずはかくはえあるまじきことなり。 柏木のことは、源氏の君さへかやうに哀れに思し召すものを、後世、この物語を注するとて、これをあはれなるやうにはいはで、かへりて人の戒めにせよといふやうに注せるは、いかに物の哀れ知らず、心なき人ぞや。 必ず式部が本意にそむくこと知るべし。 好色は人ごとにまぬかれがたく、忍びがたき情のあるものといふことを知り給ふゆゑに、とがめ給はず、哀れに思し召すなり。